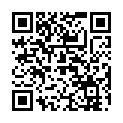過去の記事3
以前の記事(令和4年3月31日まで)はこちらまで
以前の記事(平成30年3月31日まで)はこちらまで
離婚後「共同親権」導入 党部会、民法改正案を了承
出典:令和6年2月21日 公明新聞
公明党法務部会(部会長=大口善徳衆院議員)は21日、衆院第2議員会館で会議を開き、離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」を導入する民法改正案を審査し、了承した。
改正案は、離婚後に父母一方の「単独親権」に限定している現行規定を改め、父母が協議して共同親権も選択できるようにする。協議が調わなければ、家庭裁判所が「子の利益」や家族関係を踏まえて判断。家庭内暴力(DV)や虐待が生じる恐れがある場合は、家裁が単独親権と決める。
会合で大口部会長は、子どもの利益を守る観点から、共同親権の導入と同時に、裁判所の体制やDV、虐待対策の強化、ひとり親支援の充実などが必要だと強調。党として法相などに提言していく考えを示した。
施行前の離婚も共同親権可 民法改正案、変更請求で
出典:令和6年2月21日 共同通信
離婚後の共同親権を導入するため今国会に提出予定の民法などの改正案で、政府が、改正法施行前に成立した離婚についても、家裁への親権者変更の申し立てにより共同親権を選べるようにする方針を固めたことが21日、関係者への取材で分かった。申し立てがなければ、一方の単独親権が維持される。
虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の被害者らは、加害者の元パートナーが共同親権を請求し、関与が続くことを強く危惧している。被害を防ぐ手だてが課題となる。
関係者によると、施行は公布から2年以内で、今国会で成立すれば2026年までに共同親権が始まる見通し。父母が協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断する。離婚時期が施行前か施行後かを問わず、離婚後は家裁に対し、単独親権を共同親権に変えるといった申し立てができる。
改正案は今月19日、自民党法務部会で了承された。政府は3月上旬にも国会に提出し、会期内の成立を目指している。
改正法施行前の離婚も共同親権可能に
出典:令和6年2月21日 共同通信
離婚後の共同親権を導入する民法などの改正案で、政府が、改正法施行前に成立した離婚についても、家裁への申し立てにより共同親権を選べるようにする方針を固めたことが21日、関係者への取材で分かった。
自民、共同親権導入を了承 民法改正案、今国会提出へ
出典:令和6年2月19日 共同通信
自民党法務部会は19日、離婚後の共同親権を導入する民法などの改正案を了承した。離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付ける現行規定を改め、協議で親権の在り方を決めるとし、折り合えなければ家裁が判断する。政府は3月にも改正案を国会に提出。成立すれば、公布後2年以内に施行するとしている。
改正案は、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の恐れがある場合に家裁は共同親権を認めないと定めるが、密室で起きることが多く、見逃されるとの懸念は根強い。離婚後も父母双方が子どもの養育に関われるとして保守派を中心に共同親権を支持する意見がある一方、慎重意見も広がっており、国会では激しい論戦が予想される。
共同親権では、子どもの進学や病気の長期的治療といった重要事項は、父母が話し合って決める。意見が割れて期限に間に合わないなど「急迫の事情」があれば、一方だけで決定できる。急迫の事情には、虐待・DV加害者からの避難も含まれるとされる。日常的な事柄は、同居する親だけで判断できる。
離婚後の共同親権、改正民法の要綱答申 3月国会提出へ
出典:令和6年2月15日 日本経済新聞
法制審議会(法相の諮問機関)は15日、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法改正の要綱を小泉龍司法相に答申した。現在は単独親権しか認めていない離婚後の親権を父母の協議により双方または一方と定める。法務省は与党の審査を経て3月に民法の改正案を国会へ提出する見通しだ。
父母の協議で決まらない場合は裁判所が子の利益のために父母や子との関係などをもとに親権者を判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や子への虐待などの恐れがある場合は単独親権と決める。
子の最低限度の生活の維持に必要な養育費を請求できる「法定養育費」の制度や裁判所が親子交流の試行を促せる仕組みも盛り込んだ。
国会で裁判所の適切な審理や、行政による子への支援体制などが議論になる見込みだ。共同親権の導入への懸念に説明が求められる。
法制審は同日、マンションの建て替え決議要件を緩和する改正区分所有法の要綱も答申した。
離婚後の共同親権、法制審が答申 今通常国会に改正案提出へ
出典:令和6年2月15日 毎日新聞
法制審議会(会長・高田裕成中央大大学院教授)は15日、離婚後も父母双方の親権を認める「共同親権」を選べるようにする民法改正要綱を小泉龍司法相に答申した。政府は今通常国会に改正案を提出する。
要綱では、父母は協議して離婚する際、共同親権か単独親権かを選ぶことができるとし、協議が整わなければ家裁が審判で親権者を決める。家庭内暴力(DV)や児童虐待があり、共同親権がふさわしくないケースを除外するため、家裁が判断の手掛かりとする考慮要素も盛り込んだ。また、養育費の着実な支払いや、別居親と子の早期の交流を促す規定も新たに設けた。
法制審は他にも、老朽マンションの建て替えを促進する区分所有法改正要綱と、逮捕や家宅捜索に必要な令状を捜査機関がオンラインで請求し、裁判所から発付を受ける「電子令状」の導入を柱とする刑事訴訟法改正要綱も答申した。
一方、小泉法相は、デジタル技術を活用した遺言制度と、認知症や知的障害で判断能力が不十分な人を支える成年後見制度の見直しについて法制審に諮問した。【飯田憲】
法制審議会 共同親権導入など 法改正に向けた3要綱 法相に答申
出典:令和6年2月15日 NHK
法制審議会 共同親権導入など 法改正に向けた3要綱 法相に答申
法制審議会は、離婚後にも父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するなど、法改正に向けた3つの要綱を小泉法務大臣に答申しました。
法務大臣の諮問機関である法制審議会は、15日、総会を開き、法改正に向けた3つの要綱を決定しました。 このうち、子どもの養育制度を見直す要綱は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加えて、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入することが柱となっています。 また、「建物区分所有法」、いわゆる「マンション法」を見直す要綱は、建て替えなどを円滑に進めるため、必要な所有者の同意の割合を引き下げることなどが盛り込まれています。 さらに、刑事訴訟法を見直す要綱は、逮捕状などの作成や管理を電子化し、請求や発行などの手続きをオンラインで行えるようにするなどとしています。 このあと審議会は3つの要綱を小泉法務大臣に答申しました。 法務省は、離婚後にも共同親権を導入するなどとした法律の改正案を今の国会に提出する方針です。 一方、小泉大臣は、認知症などの人に代わって財産の管理などを行う「成年後見制度」を利用しやすくする見直しや、遺言書作成の負担を軽減するためデジタル化も含めた見直しを行うよう諮問しました。
<離婚後の「共同親権」導入 父母協議で選択可能に―法制審答申
出典:令和6年2月15日 時事通信
<離婚後の「共同親権」導入 父母協議で選択可能に―法制審答申
法制審議会(法相の諮問機関)は15日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱を、小泉龍司法相に答申した。政府は今国会に改正案を提出する方針だ。
現行民法は、離婚後は父母どちらか一方の「単独親権」に限定している。これを改め、父母が協議して共同親権も選べるようにする。父母が合意できなければ、家庭裁判所が「子の利益」や家族関係を踏まえて判断。DV(家庭内暴力)や虐待が生じる恐れがあると認められるときは、家裁が単独親権に決めると明記した。
法制審は、捜査や公判などの刑事手続きをIT化する刑事訴訟法改正や、老朽化した分譲マンションの建て替え要件を緩和する区分所有法改正も答申した。
「共同親権導入」や「マンション建て替え要件緩和」へ 法制審が法務大臣に答申
出典:令和6年2月15日 テレビ朝日
「共同親権導入」や「マンション建て替え要件緩和」へ 法制審が法務大臣に答申
離婚後の子どもの養育や老朽化した分譲マンションへの対応などを議論してきた国の法制審議会は総会で法改正に向けた要綱案を採択し、小泉法務大臣に答申しました。 法制審議会の部会では、これまで離婚後の子どもの親権や老朽化した分譲マンションの増加への対応などについて議論してきました。 先月には、両親の合意が確認できた場合にはこれまでの単独親権のみではなく「共同親権」を導入することのほか、分譲マンションの建て替えに必要な決議条件を緩和することなどを盛り込んだ要綱案が取りまとめられました。 これらの要綱案について、法制審議会は15日に開かれた総会で採択し、小泉法務大臣に答申しました。 法務省は法改正に向けた作業を行い、今国会に関連法案を提出する方針です。
<主張>共同親権導入へ 健やかな成長守る環境を
出典:令和6年2月6日 産経新聞
離婚後の子供の養育について検討していた法制審議会の家族法制部会が、夫婦の合意を前提に、離婚時に双方が親権を持つ「共同親権」を原則とする要綱案をまとめた。
現在は、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみだ。だが、夫婦が別れた後も、それぞれが子供にとって父親であり、母親である事実は変わらない。養育の責任と権利を父母の双方に認めることは妥当である。
政府は、法相への答申を経て通常国会に改正案を提出する。早期の成立をはかりたい。
最大の論点は共同親権を認めるかどうかだった。反対意見のなかには、共同親権を認めた場合、父母の意見の違いから子供の進路が決まらなかったり、家庭内暴力の被害者であった母子が危険にさらされたりするなどの懸念が寄せられた。
子供の健やかな成長を願っての制度変更が、子供のリスクになることは許されない。
父母が親権をめぐって合意できない場合には、家庭裁判所が審判を行う。暴力の有無や子供への悪影響などを考慮して単独親権とする。家裁は子供にとっての最善を的確に判断する必要がある。
養育費の取り決めにも踏み込む。離婚に際して養育費を決めている母子世帯は現状では半数に満たない。取り決めをした場合でも、継続的に受け取ることが難しい。
要綱案では、養育費に「先取特権」を設け、給与などの差し押さえなどにより、子供と同居する親が優先的に養育費を確保できるようにする。また、父母が養育費の取り決めなく離婚した場合でも、最低限支払うべき金額を「法定養育費」として設定する。
扶養の義務を父母の双方が負うのは、親権の有無にかかわらない。離婚が子供の貧困に直結せぬよう、養育費の確実な受け取りにつなげてほしい。
離婚後の面会交流も重要である。今は事前に取り決めのある世帯は3割程度にとどまる。
新たに、家裁の審判の過程で親子が試行的に面会交流をする制度を設ける。第三者を交えるなどで早期に機会を設けて、離婚後の円滑な交流につなげる狙いだ。子供が父親や母親の愛情を感じながらたくましく育っていけるよう、環境を整えるのは周囲の大人の責務である。
離婚後の共同親権 子どもの幸せを最優先に
出典:令和6年2月5日 毎日新聞
どのような親子のあり方が、子どもの幸せにつながるか。その観点からの仕組みづくりが肝要だ。
離婚後の親権に関する制度の見直し案を法制審議会の部会がまとめた。現行の民法では父母の一方だけに親権が認められるが、共同親権も可能になる。
父母で話し合って、共同親権にするか、どちらかの単独親権とするかを選ぶ。結論が出ない時や、そもそも話し合いができない場合は、家庭裁判所が決める。
親権は、未成年の子の世話や教育、財産管理をする権利・義務を指す。住居や進学・就職、医療などについて責任を持つ。
2022年、子どもがいる夫婦の離婚は9万4565件あった。
共同親権になれば、子どもと同居していなくても親としての自覚を持ち続けられると、導入を求める人たちは訴えてきた。
養育費が支払われないケースが減ると期待されるほか、父母双方との交流が続くことは、子どもの成長に好ましいと指摘する。
一方、配偶者からの暴力(DV)や子どもへの虐待がある場合、親権の行使を盾に、被害が続きかねないと反対派は懸念する。
離婚後も、子どもに関することは父母の合意が必要になるが、関係がこじれていれば、話し合いさえできない可能性もある。
部会では、家族の形が多様化していることを背景に、共同親権の導入賛成派が多数を占めた。
反対派の懸念を踏まえ、見直し案では、DVや虐待がある場合、家裁は共同親権を選択してはならないと規定された。
共同親権の下でも、日常の世話や教育のほか、差し迫った事情がある時は、単独で対応できることが盛り込まれた。
ただ、どんなケースが該当するかは不明確だ。
見直し案では、家裁の役割が重要になる。当事者の事情を的確に把握し、公正に判断するためには体制の充実が不可欠だ。子どもの安全に関わる場合は、慎重な対応が求められる。
子どもの意思に最大限配慮する手立ても欠かせない。
政府は今国会に民法改正案を提出する方針だ。子どもに不利益が及ばないよう、議論を尽くす必要がある。
離婚後の共同親権、導入可能に 法制審部会が民法改正要綱案
出典:令和6年1月30日 毎日新聞
家族法制の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は30日、婚姻中の父母に認められている共同親権を離婚後も可能とする民法改正の要綱案を取りまとめた。離婚後の共同親権が導入されれば1898年の明治民法施行以降初めてで、離婚後の法制度は大きく見直されることになる。2月に予定されている法制審の総会を経て法相に答申され、政府は今通常国会に改正案を提出する方針。
厚生労働省によると、婚姻件数は近年、年間50万件前後で推移する一方、2022年は17万9099組が離婚し、うち9万4565組に子どもがいた。およそ3組に1組が離婚を選択する社会情勢となる中、部会は、これからの家族法制がどうあるべきか、議論を重ねてきた。
要綱案はまず、これまでは法解釈に委ねられていた、子の養育をする上で父母が負う責務を明確化。親権の有無に関係なく、父母には子の人格を尊重して子を養育し、子の利益のために協力する義務があることを明記した。
その上で、離婚後共同親権の道を開き、父母は協議して離婚する際に、離婚後の共同親権か単独親権かを選ぶことができるとした。協議が整わなければ家裁が審判で親権者を決める。家庭内暴力(DV)や児童虐待があり、共同親権がふさわしくないケースを除外するため、家裁が判断の手掛かりとする考慮要素も盛り込んだ。
親権行使のルールも再整備した。婚姻中でも離婚後でも、共同親権の下では父母が共同して親権を行使するのが原則としつつ、子の日常に関する決定については父母が単独で判断できるとの規定を加えた。また、「急迫の事情」があれば、父母のいずれかが単独で親権を行使できるとした。
養育費の着実な支払いや、別居親と子の早期の交流を促す規定も新たに設けた。父母双方が協力して得た財産を分ける財産分与についても請求できる期間を現行の2年から5年に延長する。
部会は21年3月に初会合を開き、2年10カ月にわたって計37回の会合を重ねてきた。30日は21人の委員が要綱案の採決に参加し、3人が反対した。部会は併せて、今回の改正内容が国民に正確に伝わるよう適切に周知する必要があるとする付帯決議をした。【飯田憲】
養育費支払い、面会交流促進へ
部会では、親権と並んで、養育費の着実な支払いや、別居親と子の面会交流の促進が大きな論点となった。2021年度の厚生労働省のひとり親世帯を対象とした調査では、現在も養育費を受けている▽現在も離婚した別居親との面会交流を行っている――と回答した母子世帯は、いずれも3割程度にとどまっており、離婚に伴う社会的課題になっている。
現行制度で不払いとなった養育費を差し押さえるには、公正証書や、家裁の調停や審判で作成された書面が必要となる。そもそも離婚時に養育費の支払いを取り決めない父母も多く、ハードルは高い。
このため要綱案は、養育費の請求に特権を与え、支払い義務がある親に、他の債権者に優先して養育費を支払わせる仕組みを整えた。これにより、養育費の支払いに関する父母間の「覚書」のような文書があれば、公正証書や家裁の書面がなくても給与などの財産の差し押さえが可能となる。
さらに、養育費に関する合意や協議がなくても、子を養育する親がもう一方の親に一定額を請求できる「法定養育費」制度を新設するとした。協議が整わない場合のセーフティーネットと位置づけ、子の最低限度の生活の維持に必要な金額が想定されている。
別居や離婚で離れ離れになった親子を早期に面会させる制度も創設する。親子の交流が長期間滞ると、親子関係にあつれきが生じやすくなるとされることから、調停・審判手続き中に、家裁が親子交流の試行的な実施を促すことができるとした。
併せて、これまで父母のみ認められていた面会交流の申立人の範囲を改める。子の利益のために特に必要である場合には、祖父母や兄弟姉妹らにも広げる。
親権
未成年の子に対して親が持つ権利と義務。主に、子の身の回りの世話(監護)や教育、子の居所指定をする「身上監護」と、子の財産を管理する「財産管理」からなる。民法は818条で「父母の婚姻中は、父母が共同して行う」として婚姻中の共同親権を定める。一方、819条で「父母が離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない」として離婚後の単独親権を規定している。
「共同親権」導入が柱 法改正に向けた要綱案 法制審議会の部会
出典:令和6年1月30日 NHK
「共同親権」導入が柱 法改正に向けた要綱案 法制審議会の部会
離婚したあとの子どもの養育について検討してきた法制審議会の部会は、法改正に向けた要綱案をまとめました。離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入することが柱です。
親権は子どもの身の回りの世話や財産を管理する権利と義務で、現在の制度は、離婚後、父と母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」となっています。
しかし、社会情勢の変化に対応できていないなどとして、法制審議会の家族法制部会は法改正に向けた見直しの議論を行い、要綱案をまとめました。
それによりますと、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子どもへの責務を果たさなければならないと定めるとともに、単独親権に加えて、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
そして、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を定めます。
ただ、共同親権には離婚後もDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがあるとして反対意見が根強いことも踏まえ、裁判所がDVや虐待があると認めた場合は、単独親権を維持するとしています。
さらに子どもが不利益を受けないように行政や福祉などの充実した支援や、国民の意識や考え方の変化に応じた検討を求める付帯決議もつけられました。
法制審議会は、来月中旬にも総会を開いて要綱を決定し、小泉法務大臣に答申することにしています。
要綱案のポイント
親が離婚したあと、子どもをどう育てていくのか。 家族や子育ての在り方が多様化する中、法制審議会の部会が3年近く議論を行い、まとめられた要綱案のポイントです。
【父母の責務を明確に】
まず、大前提となる考え方は「子どもにとって最善の利益となる」ことです。 このため大原則として、 ▽親権の有無にかかわらず、父と母には子どもの人格を尊重し、子どもを養育する責務があり、親と同程度の生活を維持できるように扶養しなければいけないこと ▽父と母は離婚後も含め、子どもの利益のため互いに人格を尊重して協力しないといけないことなどが明記されました。
【共同親権を新たに設ける】
「単独親権」と言われる今の制度では、父と母が離婚した場合、親権はどちらか一方が持つことになっています。 要綱案ではこれを見直し、父と母の双方が持てるようにする「共同親権」を導入することでまとまりました。 離婚する際、共同親権にするか、単独親権にするかは父母が協議によって決め、意見が対立する場合や協議できない場合は家庭裁判所が判断します。 その際、裁判所は親同士や親子の関係などを考慮することになっていて、特にDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがある場合、単独親権にしなければならないとされています。 親権者が決まったあとでも、裁判所が子どもの利益のために必要があると認めるときは、子どもや親族からの請求で変更することが可能だとしています。
【養育費の規律も新たに】
養育費の不払いが問題となっていることから、支払いが滞った場合はほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする規律を設けるとしています。 また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」を設けることになりました。
【親子の面会交流は】
別居する親子が定期的に会う面会交流についても新たな試みを提案しています。 調停などで話し合いが続いている途中でも、家庭裁判所が面会交流を試しに行うことを促せるようにします。 親子の面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待やDVのおそれがある場合などは認めないとしています。 また、親だけでなく、祖父母も子どもの養育に携わる機会が増えていることから、祖父母なども面会交流を求める審判を裁判所に請求することが可能だとしました。
専門家 “家裁の体制・運用 ある程度ガイドラインを”
家族法の専門家で、部会の委員の1人でもある早稲田大学の棚村政行教授は「離婚後もできるだけ協力するという理念を掲げ、単独親権以外の選択肢が新たに入ったことは大きい改革だ」と評価する一方、「共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかった」として、課題が残されていると話しました。 具体的に指摘したのは、家庭裁判所での体制の充実や、判断のための基準づくりです。 家庭裁判所は共同親権か単独親権かなどをめぐって夫婦間で争いがある場合に判断する役割を担い、DV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがある場合は単独親権にしなければならないとされています。 そうした点を踏まえ、棚村教授は「親権の判断に子どもたちの安全への配慮が入ったことは意味がある。今後は、家庭裁判所の体制や運用について、ある程度ガイドラインなどを示していく必要がある」と指摘しました。 面会交流の取り決めなどにも家庭裁判所の役割が大きいなどとしたうえで、「共同親権を含めた新しい制度を本当に子どもの利益になるために生かすには、法整備だけでなく、運用や支援についてもしっかりと体制を整えて基盤を作っていく必要がある」と話していました。
DVの被害者からは懸念の声
要綱案では、DVや子どもへの虐待が続くおそれがある場合、家庭裁判所は単独親権にしなければならないとされています。 しかしDVの被害者からは、裁判所が適切に判断するか懸念する声が上がっています。 要綱案のとりまとめを前にした今月16日、DV被害を受けた当事者や支援する弁護士らでつくる団体が都内で会見を開き、内容に不安があると訴えました。 夫と離婚し、現在は幼い子どもと暮らす40代の女性は「怒って物を壊したりどなったりする元夫から面会交流の調停が申し立てられ、『面会に行きたくない』と泣き、自傷行為をする子どもの状況を伝えても、裁判所から面会を強要された。このような判断基準では共同親権も強要されてしまうのではないか。子どもの利益について加害者と話し合うことは不可能で、なぜ子どもを危険にさらさなければならないのか」と訴えました。 夫との離婚裁判を控え、子どもと暮らしている30代の女性は「監視されたり、ののしられたりするなどのDVを受けたが、その証拠を残せなかった。共同親権の例外となるDVを誰がどういう基準で認定してくれるのか分からないのでとても不安だ」と話していました。 会見をした「『離婚後共同親権』から子どもを守る実行委員会」は30日、要綱案に強く反対するとした声明を発表しました。
導入に積極的な立場の団体代表 “国会の議論を注視”
法制審議会の部会の委員で、共同親権の導入に積極的な立場をとる団体の代表は、要綱案を評価する一方、面会交流の要件などで懸念が残るとして、国会での議論を注視したいとしています。 「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」代表の武田典久さんは30日の部会の終了後、取材に応じ、共同親権の導入を盛り込んだ要綱案について「一定の前進をしたと感じている。離婚したあとも、親子関係と夫婦関係を切り離して子どもと関わりたいと思っている人たちが養育に責任を持つことができる」と評価しました。 一方、懸念する点として「離婚後、親子の面会交流についての要件などが明文化されていない。別居する親子がなかなか会えない状況が変わるかというと定かではない」と話しました。 そのうえで「今後、国会で面会交流などの運用をどのようにしていくかの議論が進むと思う」と述べ、国会の議論を注視したいとしています。
離婚後原則「共同親権」 法制審部会、要綱案決定 支援求める付帯決議も
出典:令和6年1月30日 産経新聞
離婚後原則「共同親権」 法制審部会、要綱案決定 支援求める付帯決議も
離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が30日、開かれ、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」を原則とする要綱案を取りまとめた。ドメスティックバイオレンス(DV)対策など離婚後の家族への支援充実を求める付帯決議も付けた。
2月の法制審総会を経て法相に答申され、政府は通常国会で民法などの改正案を提出する。部会の委員の一部は要綱案に反対しており、法案成立には曲折も予想される。
要綱案は部会で最大の論点となった共同親権について原則、父母の同意で可能とした。裁判所に親権の判断を委ねる場合は、DVや虐待など子供に害を与える恐れがあれば単独親権とする。
子供と別居する親が支払う養育費は、他の債権者よりも優先して支払いを受けられる「先取特権」を同居親に付与。父母で養育費の金額を合意できなくても最低限、支払うべき金額を「法定養育費」として設定する。
家庭裁判所の審判の過程で、別居親と子供の面会交流の試行的な実施を促せる制度も新設する。
離婚後の共同親権導入、要綱案了承 77年ぶり改正へ
出典:令和6年1月30日 日本経済新聞
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は30日、離婚後の共同親権導入を柱とする民法改正の要綱案をとりまとめた。政府は要綱案を基に今国会に法案を提出する見通しだ。成立すれば離婚後の親権に関する家族法制の改正は77年ぶりとなる。
要綱案は子の利益を基準に仕組みを整えた。親権について協議離婚の場合は父母の協議で双方または一方と定める。現在は離婚後は単独親権しか認めていない。
協議で決まらない場合は子の利益や父母関係、親子関係などを考慮し裁判所が判断する。配偶者へのドメスティックバイオレンス(DV)や子への虐待のおそれが認められ、父母で共同で親権を行使できないなどの場合は例外で裁判所が単独親権と決める。
離婚後に共同親権になった場合も、子どもの緊急の手術や入学手続きといった「子の利益のために急迫の事情があるとき」のほか、子の監護や教育に関わる日常の行為は単独で親権を行使することができる。
日本は協議離婚が9割ほどを占める。裁判所の関与が今後増えることが見込まれる。30日の部会は裁判所での適正な審理や離婚後の子どもの養育への支援のありかたの検討などを求める付帯決議もまとめた。
要綱案は親権以外に養育費や親子交流に関しても定めた。子の最低限度の生活の維持に必要な養育費を請求できる「法定養育費」の制度の導入を規定した。
裁判所が親子交流の試行的な実施を促すことができ、子の利益のために特に必要な場合は父母以外の親族との交流の実施を定めることも可能だ。
厚生労働省の調査によると、母子世帯の中で「現在も養育費を受けている」「現在も面会交流を行っている」と答えたのはそれぞれ3割ほどにとどまる。
制度見直しの背景には共働きの家庭の増加や男性の育児休業の取得率の向上といった社会情勢の変化がある。父母が共同で子育てをする機会が増加し、子と親の結びつきが強まっている。内閣府によると日本の離婚件数は年間20万件弱で、そのうち6割ほどの離婚夫婦に未成年の子がいる。
グローバル化の進展も制度見直しの議論の契機となった。国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が14年に日本で発効した。単独親権のみしか認めない現民法は同条約違反との指摘もある。
19年には親権がなく子に会えない父母らが離婚後の単独親権は違憲だと国を提訴した。
主要国では米国、英国、フランスなどが共同親権を導入している。単独親権のみを認めるのはインドやトルコなど少数だ。
立命館大の二宮周平名誉教授(家族法)は要綱案について「(協議離婚で)単独親権と共同親権の両方を選べるという意味で評価している」と話す。
養育費や親子交流の規定に関して「欧米のように国が養育費を立て替えたり、徴収して権利者に渡したりする仕組みや、親子交流は子どもの権利であると定める規定も盛り込むべきだ」と指摘する。
離婚後の共同親権、導入を提言 対立時は家裁が判断 法制審が要綱案
出典:令和6年1月30日 朝日新聞
離婚後の共同親権、導入を提言 対立時は家裁が判断 法制審が要綱案
家族法制の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は30日、離婚後も父母双方の親権を認める「共同親権」を選べるようにする民法改正の要綱案をまとめた。父母の協議で単独親権か共同親権かを選び、折り合わない場合は家庭裁判所が定める。政府は通常国会に関連法案を提出する方針。
厚生労働省の調査によると、未成年の子がいる夫婦の離婚件数は年間約10万件、親の離婚を経験した子は約20万人。法案が成立すれば、単独親権に限ってきた現行制度からの大きな転換となる。
ただ、父母の力関係によって片方が共同親権を強いられたり、家庭内暴力(DV)や虐待が離婚後も続いたりすることへの懸念は根強い。導入の可否をめぐる議論では、こうした懸念への対策が焦点となりそうだ。
要綱案は、父母は婚姻関係の有無に関わらず、子に関わることについては、子の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければならないと明記。離婚後も双方が子の成長に責任を持つ必要があることから、現行の民法で「婚姻中は父母が共同して行う」と定められている親権を、婚姻中に限らず、離婚後も双方が持てるようにした。
共同親権のもとでは、子に関することは父母の話し合いで決めるが、日常的なことについては、どちらか一方の判断で決められるようにした。
離婚件数の9割近くを占める協議離婚では、父母間の協議で親権者を定める。合意できない場合や裁判離婚では、家庭裁判所が親子や父母の関係を考慮し、親権者を定める。
いずれかの親の関与が「子の心身に害悪を及ぼすおそれがある」場合には、家裁は単独親権と定める。DVや虐待などを想定している。協議で共同親権と決めても、協議過程や事情の変化を踏まえ、子のために必要だと認められる場合には、家裁が単独親権に変更できるとした。
離婚後の共同親権、導入へ 単独限定を改正、法制審部会
出典:令和6年1月30日 東京新聞
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後の子どもの養育に関する制度を大幅に見直す要綱案を取りまとめた。父母どちらかの単独親権のみと定めた現行民法を改め、共同親権を選べるようにする。父母の協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断。多発する養育費の不払いに対応し、必ず支払うべき「法定養育費」を創設する。
家裁の判断に当たり、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の恐れがある場合は単独親権と定めるとした。ただ被害者側は「密室の出来事は証明が困難で、家裁が見逃す恐れがある」と指摘。法務省は今国会に民法などの改正案を提出する方針だが、加害行為が続く懸念は払拭できておらず、なお曲折が予想される。
共同親権には、離婚後に父母とも養育に関われるとして支持する意見がある。家族の在り方や価値観の多様化が進んだことを受け、部会が導入の可否を議論してきた。
「養育に責任」「DV続く」…離婚後の「共同親権」導入の要綱案に賛否
出典:令和6年1月30日 読売新聞
「養育に責任」「DV続く」…離婚後の「共同親権」導入の要綱案に賛否
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を柱とする要綱案をまとめた。
※以下、紙面参照ください。
離婚後の共同親権可能に、要綱案 法制審部会、付帯決議検討も
出典:令和6年1月23日 共同通信
離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、今月末に最終取りまとめを目指す要綱案の概要が23日、関係者への取材で分かった。ドメスティックバイオレンス(DV)当事者らは「子どもの安全を守れない」と導入反対を訴えてきたが、父母双方の共同親権を可能とする従来の案から大きな変更はない。
要綱案は30日の部会で採決の見通しで、付帯決議を設けることも検討するとみられる。2月中旬の法制審総会を経て法相に答申され、政府は通常国会で民法などの改正案成立を目指す。
要綱案では、単独親権のみの現行民法を改め、父母が協議で共同か単独かを選び、合意できなければ家裁が決定する。
転機迎える家族法制 「未来の子供に幸せな制度を」当事者の思い
出典:令和6年1月8日 産経新聞
転機迎える家族法制 「未来の子供に幸せな制度を」当事者の思い
離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会の議論が大詰めを迎えている。昨年12月には離婚後に父母双方に親権を認める「共同親権」を原則とする要綱案の試案が示され、今年初めにも部会が要綱案をまとめる。政府は早ければ1月下旬に招集予定の通常国会に民法改正案を提出する見通しで、今年は家族に関する法律が大きく変わる転換点となりそうだ。
▪️ 親から子を中心に
「親を中心にしてきた旧来の民法を子供を中心とした民法に見直す」。法務省関係者は今回の議論のポイントについてそう話す。
現行の民法の規定は子供の身の回りの世話や財産を管理する権利を指す「親権」について、子供は父母の親権に「服する」と父母を主体に記述してきたが、試案では親権は「子の利益のために行使しなければならない」と修正した。
議論の最大の焦点となってきた共同親権については、父母の合意で導入が可能に。裁判所に判断を委ねる場合は原則、共同親権とし、ドメスティックバイオレンス(DV)など子供に害がある場合は単独親権とするようにした。
子供の養育に欠かせない環境整備も進む。これまで支払われないことが多かった養育費について、ほかの債権者よりも優先して支払わせる仕組みを導入。別居している親と子供との面会交流の実施を家庭裁判所が促せる制度を設ける方向だ。
▪️ 月1回、1時間のみの「面会」
子供中心の家族制度は、離婚後の子育てをどう変えるか。
「未来の子供たちが幸せになれる制度になってほしい」と願うのは、妻と長女と別居する警察官の40代男性だ。
ある日、仕事を終えて自宅に戻ると、妻と生後間もない長女はいなかった。中は真っ暗で電灯も点かず、洗濯機や冷蔵庫、カーテンまでなくなっていた。
電話に出ない妻から連絡が来たのは翌朝。生活費の振り込みを求めるとともに、今後は弁護士を通じて連絡するよう伝えるものだった。
その後、子供の養育を巡る家庭裁判所での審判が始まり、娘が父親と会えるのは妻が指定した場所で月1回、1時間のみとされた。
男性は「母親と去った後、娘とはほとんど会えていない。同居するかしないかで過ごせる時間になぜここまで差をつけるのか」と話し、離婚後も双方が養育に関われる制度となるよう期待する。
▪️ 娘から「嘘つき」
同じ願いは、埼玉県の経営コンサルタント、花村憲太郎さん(46)も持っている。
元妻は数年前、生後間もない長女を連れて突然、家を出ていった。
その後始まった週1回の離婚協議のたびに長女と会う機会があり、協議の中でも「週1回の長女との面会交流」を条件とすることで合意。だが離婚が成立すると、約束はほごにされた。
その後、家庭裁判所は花村さんと長女との関係を踏まえて、週1回以上の交流を続けるよう審判を下したが、元妻側が「子供が嫌がっている」などといって実現せず、今年4月末に面会してからは1度も会えていないという。
離婚前、「ずっとお父さんと一緒にいたい」と言うこともあったという長女。だが、離婚後は「病気をうつした」「噓つき」などと攻撃的な言動をされることも増えた。花村さんは「充実した交流ができる環境があれば、拒絶を防げたかもしれない」と思う。
「子供たちにとって、少しでもいい世の中になれば」。花村さんは、親子間で特に問題のない場合は離婚後も親子が自由に会える時代が来ることを願っている。(宮野佳幸)
子に虐待恐れあれば単独親権に、法務省が例外規定
出典:令和5年12月19日 日本経済新聞
法務省は19日の法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、父母離婚後の共同親権の導入を巡り例外規定の素案を示した。親権について父母の協議で合意できないときは裁判所が判断する。子への虐待などの恐れがあるケースは単独親権と定めるようにする。
法務省は8月のたたき台で離婚後の親権に関し「父母の双方または一方を親権者と定める」と示した。これを前提に例外とする事案の整理を進めてきた。
単独親権のみ認めるケースとして主に2点を例示した。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――と認められる場合に適用する。
現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。部会は2024年1月に改正民法の要綱案をまとめ、24年の通常国会への提出をめざす。
日本は協議離婚が主流で、裁判所の関与が必須ではない。裁判所が共同親権か単独親権のどちらにするか判断基準の議論を続ける。
離婚後に共同親権になった場合も、子どもの緊急の手術や入学手続きといった「子の利益のために急迫の事情があるとき」のほか、子の監護や教育に関わる日常の行為は単独で親権を行使することができる。
父母のどちらかが亡くなるなど父母間で話し合いができないケースでは、祖父母や過去に世話をした親族が交流の申し立てを裁判所にできるようになる。これまで父母以外の第三者の交流は父母間の話し合いで決めるのが原則になってきた。
養育費の支払いで合意できず離婚した場合には、最低限の養育費を請求できる「法定養育費」の制度を導入する。
支払いは離婚した月から、父母で費用分担を決めた日や子の成人した日などのうち早い時期の月までの間と定める。
離婚後の「共同親権」導入を 法制審部会が要綱案の素案
出典:令和5年12月19日 NHK
離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の部会は、見直しに向けた要綱案の素案を示しました。離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するなどとしています。
現在の制度は、離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」となっていますが、社会情勢の変化に対応できていないとして法制審議会の家族法制部会は見直しの議論を行い、19日要綱案の素案を示しました。
それによりますと、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子どもへの責務を果たさなければならないと定めるとともに、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は、家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を指定します。
親権者が決まったあとでも子どもや親族からの請求で変更できるとしています。
ただ、共同親権には、離婚後もDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがあるとして反対意見が根強いことも踏まえ、DVや虐待があった場合は、単独親権を維持するとしています。
また、養育費については、不払いを避けるため、支払いが滞った場合は優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。
さらに、面会交流については、調停などで争っている場合、結論が出る前に家庭裁判所が試しに行うことを促せるようにします。
面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待やDVのおそれがある場合は認めないとしています。
部会は、来月にも要綱案を取りまとめたいとしています。
別居の親子の面会交流、祖父母らも申し立て可能に 法制審部会
出典:令和5年12月19日 毎日新聞
家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が19日開かれ、別居している親子が定期的に会う「面会交流」について新たな枠組みを盛り込んだ民法改正要綱の原案が示された。これまで父母のいずれかにしか認められていなかった面会交流の家裁への申立人の範囲を祖父母らにも広げる。
民法は父母が協議離婚する際、「子の利益」を考慮して別居する親との面会交流の仕方を取り決めるよう求めているが、具体的な権利や義務の規定はない。また、面会交流の審判でも申し立てができるのは「父または母」に限られている。
ひとり親世帯を対象にした厚生労働省の2021年度の調査によると、離婚した別居親との交流が実施されているのは、母子世帯で30・2%、父子世帯でも48%にとどまった。親子の交流が途絶えた世帯では、別居親の親族も子と会えない状態になっているとみられ、「孫と会えない」として祖父母らが裁判所に救済を求める動きもある。
原案によると、新たな仕組みでは、面会交流を求める申立人は父母が原則としつつ、父母以外の親族と、子との交流を実施することが「子の利益」のために特に必要である場合には、家裁は、親族と子の面会交流について定めることができるとした。
申立人となれる親族は、子の祖父母や兄弟姉妹ら。父母による面会交流の協議や申し立てが期待できず、他に手段がない場面での活用が想定される。
原案には離婚後の共同親権の導入も盛り込まれており、部会は来年1月にも要綱案を取りまとめたい考えだ。【飯田憲】
法制審部会に「共同親権」の試案提示 離婚後、DVなら単独親権
出典:令和5年12月19日 産経新聞
法制審部会に「共同親権」の試案提示 離婚後、DVなら単独親権
離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が19日、開かれ、離婚後に父母双方に親権を認める「共同親権」を原則とする要綱案の試案を示した。ドメスティックバイオレンス(DV)など「子供の心身に害悪を及ぼす」と裁判所が判断した場合は、どちらかの単独親権とする。来年初めにも要綱案を取りまとめ、政府は早ければ来年の通常国会に民法改正案を提出する見通し。
親権は子供の身の回りの世話や財産を管理する権利の総称。
試案では、親権の有無にかかわらず、両親に子供を養育する義務があることを初めて明記。両親が子供の人格や互いの人格を尊重して子育てに協力することを求めた。
離婚後の親権は双方の合意で共同親権か単独親権を選べる。
裁判所に判断を委ねる場合は原則、共同親権とする。裁判所が判断する際にDVや子供への虐待が懸念されれば、単独親権とし、共同親権を認めない方針を明確化した。
子供と別居している親が同居親に支払う養育費には、他の債権者などより優先して支払いを受けることができる「先取特権」を付与。双方で養育費の金額を合意できない場合でも最低限支払うべき金額を示す「法定養育費」を設定する。
別居している親と子供との面会交流については、家庭裁判所が審判の過程で子供の心身の状態を考慮して試行的な実施を促せる制度を設ける。
また、子供の祖父母らが父母を通さずに家庭裁判所に直接、子供との面会交流を申し立てられる仕組みも提案した。
「子供中心の制度に」
棚村政行・早稲田大教授(家族法)
今回示された家族法制に関する要綱案試案では基本的な規律として父母が子供を養育する責任を負い、子供の関係で人格を尊重して協力すると明記したことが重要だ。
こども家庭庁ができるなど、大人の考え方を子供に押し付けるのではなく、子供の人格を尊重し、子供を真ん中に置く流れを民法の中でも位置づけることになる。
離婚後の親子の関係は多様で、共同親権と単独親権、それぞれが適切なケースがある。試案で裁判所が共同親権の可否について考慮すべき事情として、ドメスティックバイオレンス(DV)などを具体的に示した点は高く評価できる。
離婚後の子育てを適正な制度にするには法改正だけでは不十分。政府は運用の明確化と支援も進め、人的・資金的な投資もすべきだ。
[離婚後の共同親権導入へ 選択可、「DVの恐れ」は単独親権―法制審要綱案
出典:令和5年12月19日 時事通信
離婚後の共同親権導入へ 選択可、「DVの恐れ」は単独親権―法制審要綱案
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は19日、離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」の導入に向けた民法改正要綱案を公表した。離婚後は一方の「単独親権」を規定する現行法を見直し、父母が協議して共同親権か単独親権のどちらとするか選択可能にする。虐待やDV(家庭内暴力)の恐れがあるときは家庭裁判所が単独親権と決める。
政府はこれを踏まえた改正案を来年の通常国会に提出する考えだ。
現行法は離婚のケースについて父母どちらか一方のみの単独親権を定める。これに対し、「一方から親権を奪い、親子の交流を断ち切る制度」「養育費不払い問題の要因となっている」とする批判がある。逆に、「離婚後も虐待やDVが続く恐れがある」として共同親権の導入に反対する声も根強い。
要綱案は離婚後の親権について「父母の協議で、双方または一方を親権者と定める」と規定。父母が合意できなければ、家裁が判断するとした。共同親権を認めると虐待・DVなどが生じて「子の利益を害する」と認められる場合、家裁は「父母の一方を親権者と定めなければならない」と明記した。
共同親権の場合、子の進学といった重要事項を決めるには双方の合意が必要になる。ただ、日常的な教育や居所に関しては、どちらか一方を「監護者」に指定して単独で決められるとした。
養育費の不払い対策として、家裁が当事者に収入・資産の情報開示を命令できる制度を新設。養育費請求の実効性を高めるため、支払いが滞った際に優先的に財産を差し押さえられる「先取特権」を付与する。離婚時に養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」も創設する。
離婚後の共同親権に向けた法整備を要望 研究者や元裁判官ら約60人
出典:令和5年11月20日 朝日新聞
離婚後の共同親権に向けた法整備を要望 研究者や元裁判官ら約60人
離婚後の子どもの養育のあり方をめぐって、家族法学者や元裁判官、弁護士ら63人が20日、小泉龍司法相あてに、離婚後の父母に共同親権を認める制度の導入に向けた法整備を求める要望書を提出した。
要望書は、家族法を専門とする中央大の鈴木博人教授や関西学院大の山口亮子教授ら4人が呼びかけ人になり、家族法や家族社会学などの研究者、元裁判官、弁護士や司法書士など59人(11月19日現在)が賛同者になっている。
要望書によると、日本では毎年約18万件の離婚があり、そのうち約6割に未成年の子どもがいる。現在は、離婚時に必ずどちらか一方に親権を決めなければならないため、「親権者になれないと子どもに会えなくなるのではないか」という不安から親権争いが激しくなったり、合意のないまま子どもとの同居を確保した親が、別居親との交流を著しく制限したりしていると指摘。父母の養育責任の継続を明確にするためにも、子どもの利益を優先的に考えられる仕組みが必要だとしている。
現在、離婚後の子どもの養育については、有識者や当事者団体の代表を集めた法制審議会の家族法制部会で議論されている。同部会は今年4月、共同親権を導入する方向で検討する方針を確認している。
======
「mネット 民法改正情報ネットワーク」が法務省に提出した要望書
「離婚する親に情報提供を」 共同親権賛同の学者ら要望
出典:令和5年11月20日 共同通信
法制審議会(法相の諮問機関)の部会で検討が進む離婚後の共同親権に関し、導入に賛同する民法学者らが20日「父母が親としての責任を自覚し、子の意思を優先的に考えることができる仕組みが不可欠」とし、離婚手続きに入る親への情報提供や、関係省庁や家裁の支援体制構築を検討するよう求める要望書を法務省に提出した。
立命館大の二宮周平名誉教授らが呼びかけ、弁護士や元裁判官、大学教授ら約60人が賛同。法相宛てで、法務省民事局長に渡した。
要望書は「親権者になれないと子に会えなくなるという不安が親権争いを峻烈にさせ、つらい思いをする子も少なくない」と指摘。共同親権導入を評価した。
子の利益侵害なら単独親権 離婚後の「共同親権」で家裁判断時、法制審部会の修正案
出典:令和5年10月29日 産経新聞
子の利益侵害なら単独親権 離婚後の「共同親権」で家裁判断時、法制審部会の修正案
離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会(法相の諮問機関)部会の、要綱案取りまとめに向けた「たたき台」修正案の概要が29日、関係者への取材で分かった。離婚後に父母双方の「共同親権」を可能とし、父母が合意できなければ家裁が判断する枠組みは維持。その上で、家裁の判断時に、共同親権なら「子の利益を害する」場合、家裁は父母どちらかの単独親権と定めなければならないと新たに記す。
共同親権には、離婚後に父母とも養育に関われるなど、家族関係の多様化に対応できるとの意見がある一方で、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害が続くとの懸念が強い。修正案では、子供の利益が侵害されるような場合、共同親権は認めないと打ち出した。
修正案は31日の部会で示され、今後の議論で内容をさらに詰める。
※以下、紙面参照。
「子、連れ去り勝ち」の絶望 裁判所は違法認定、親権争い強行
出典:令和5年10月18日 毎日新聞
他方の親の同意を得ない「子の連れ去り」が社会問題化している。母親による子連れ別居はよくあることとして受け止められてきたが、子の身の回りの世話をしていることが離婚後の親権争いで有利に働くと広く知られるようになり、近年は父親による子の切り離しも顕在化している。「連れ去り勝ち」とも言われる、家族間紛争の実態に迫った。
【飯田憲、山本将克】
※以下、紙面参照。
我が子に会えず、この国に絶望 違法認定も「連れ去り勝ち」の現実
出典:令和5年10月6日 毎日新聞
我が子に会えず、この国に絶望 違法認定も「連れ去り勝ち」の現実
他方の親の同意を得ない「子の連れ去り」が社会問題化している。母親による子連れ別居はよくあることとして受け止められてきたが、子の身の回りの世話をしていることが離婚後の親権争いで有利に働くと広く知られるようになり、近年は父親による子の切り離しも顕在化している。「連れ去り勝ち」とも言われる、家族間紛争の実態に迫った。
「子どものことを思い出さない日は一日たりともありません」。神奈川県の女性(40)は小学校低学年だった長男と幼児の次男=当時=を夫に連れ去られた。もう4年、会えていない。
大学の先輩だった夫と2009年に結婚し、程なく長男を妊娠した。その頃から家庭内暴力(DV)が始まり、殴る蹴るの暴行を受けた。「稼げないお前は寄生虫だ」「ろくでもない人間に子どものしつけはできない」――と毎日のように人格を否定された。
次男が生まれ、長男の小学校入学が間近になると、DVは激しさを増した。アイロン台でたたかれたことをきっかけに、母子でシェルター(一時保護施設)に避難したこともあるが、「自分が家族を壊すわけにはいかない」と思い直し、自宅に戻った。
夫は「子どもは連れ去ったもん勝ち」
夫の変化に期待していた。だが、家庭にはそれまでとは違う不穏な空気が流れた。「母さんはおかしいから、あっちで遊ぼう」。夫は、子どもを巻き込んで嫌がらせをするようになった。「子どもは連れ去ったもん勝ちだ」と繰り返し、自宅には堂々と「男の離婚」というハウツー本を置いた。女性は19年7月、離婚を切り出した。
直後のことだ。夫は、中国地方にある自身の実家に子どもを連れて帰ると言い、長男を飛行機に乗せた。1週間後、今度は嫌がる次男を強引に車に押し込み、追いすがった女性を突き飛ばして家を出た。女性が夫の実家を訪れると、夫側から「殴られたのは夫を立てないからだ。子どもは諦めろ」と告げられた。
女性は裁判所に救済を求めた。高裁は21年12月の決定で、離婚後の親権争いが現実問題となる中で、夫が強行した子連れ帰省について「連れ去り、またはそれに準じる違法な態様によって子の監護を開始した。違法性の程度は高い」と認定。子ども2人を女性に引き渡すよう夫に命じた。決定は後に確定した。
※以下、本文参照。
「子の連れ去り」が社会問題に 子の利益とは? 日本の制度の欠陥
出典:令和5年10月6日 毎日新聞
「子の連れ去り」が社会問題に 子の利益とは? 日本の制度の欠陥
近年、日本で社会問題化する他方の親の同意を得ない「子の連れ去り」。父母間で子の奪い合いが激化するケースも多く、今夏には、卓球元日本代表の福原愛さんの元夫が、福原さんに対して長男を引き渡すよう求める記者会見を開いたことでも話題となった。問題の解決のために、どのような取り組みや姿勢が求められるのか。米国の事情に詳しい関西学院大の山口亮子教授(家族法)に日米の文化や制度の違いについて聞いた。
――子の連れ去りを巡る日米の考えの違いは。
◆まず「子の利益」に対する考え方は日米で違います。欧米諸国では、親の別居や離婚後も、子どもが双方の親と頻繁かつ継続して交流することが子の利益だとみなされ、それを保障することが公的政策であると法律に明記されています。
一方、日本は戦後の高度経済成長期の男女性別役割分担の名残で、母親が子育てをし、そのまま継続して子どもを養育することが「子の利益」だとされがちです。子どもの安定性を考える時も、別居後は、ひとりの親と暮らす方がいいと思われているようにみえます。同じ子の利益という言葉を使いながら見方が全く違うのです。
連れ去りによって他方の親と会えなくなるだけでなく、地域や友達といった生活実態も変わります。いきなり離されるため、子どもにとっては不利益に当たります。
――米国の離婚後の法制の特徴は。
◆離婚後も父母がともに子どもを育てる仕組みが定着しています。例えば、父母は離婚する際、子どもと過ごす時間の配分や教育・医療の方針、意見の食い違いがあった場合の対応をまとめた「養育計画書」を裁判所に提出する義務があります。父母が合意できずに対立している場合は別々に計画書を提出し、裁判所の判断を仰ぎます。
米国でも連れ去り自体はあるものの、別居時にもう一方の親に知らせず、子を家から連れて出ることは禁止されています。転居の必要があれば、その後の養育計画を作り直すことになります。親子の関係や交流を妨げないという社会観念が日本に比べて強いのです。
――日本の現状をどうみるか。
◆日本では、子の養育をする親の子連れ別居や、家庭内暴力(DV)から逃れるための別居は、違法な子の連れ去りとみなされていません。
ただ、無断別居は抑制される必要があります。また、DVの際に自力で家を出て別居するしか手段のない日本の制度にも問題があります。制度の不備に対する負担をDV被害者に課すことはできませんが、その不備のために、あらゆる無断別居を正当化することも許されません。結果的に実力行使を行った親が優先されがちな実情も見直されるべきです。
――「子の利益」をどう浸透させていくべきか。
◆米国では父母間の取り決めに対する裁判所の決定を守らなければ、裁判所を侮辱したとしてペナルティーが科されます。日本にはこのような制度がありません。
父母による子の奪い合いの解決には国家が介入すべきですが、子の利益とは何なのかについて社会全体で検討し、合意を形成しておくことが重要です。法的争いに発展する前に、別居や離婚後の子の養育のあり方について父母間で取り決められるよう社会的支援を整え、子の奪取を予防することが必要なのではないでしょうか。【聞き手・飯田憲】
離婚して別居の親、子どもの学校行事に参加できる? 文科省の説明は
出典:令和5年10月5日 朝日新聞
離婚して別居の親、子どもの学校行事に参加できる? 文科省の説明は
「学校行事、授業参観及び習い事の発表会に参加することを認める」
埼玉県の女性(48)は、2017年末に裁判で離婚が成立した際、こんな和解条項を元夫と交わした。
幼稚園児と小学生だった男の子2人の親権は、元夫が持つことになった。ただし、女性も学校行事などに参加してもよいということを取り決めたものだ。
ところが、離婚して2カ月後から、幼稚園の参観日や音楽発表会、運動会はすべて行けなくなってしまった。
幼稚園に聞くと、「お父さんがダメと言っているからダメ」と言う。元夫は「園がダメと言っている」と濁した。
結局、幼稚園との話し合いもできないまま、次男は卒園した。
元夫は、面会交流の調停で小学校の全ての行事参加にも反対だと主張していた。それでも小学校に一度は受け入れられた。教頭は、「父母に見てもらうことが子どもの成長につながり、父母は、家では見られない子どもの社会性を見る機会になる。お母さんを拒む理由がない」などと説明した。
ところが、その後、元夫は学校に対し、「保護者とは親権者だ」「母親を学校に入れないように」などと抗議。女性は行けなくなってしまったという。
運動会や文化祭など、秋は学校行事のシーズン。離婚などで子どもと離れて暮らしている親にとっても、学校行事は成長した姿を見られる機会になる。しかし、そこで元夫婦の間でもめたり、学校などとの間でトラブルになったりするケースは少なくない。
昨年、裁判で離婚が成立した千葉県の会社員男性(49)の場合。
※以下は紙面を参照ください。
子の「連れ去り」再び敗訴 国への損害賠償認めず
出典:令和5年9月27日 産経新聞
配偶者に子どもを連れ去られたと訴えている男女12人が「子の連れ去りを防ぐ立法措置を国会が怠り、親権や監護権が不当に制約された」として、国に1人当たり11万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(志田原信三裁判長)は27日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
原告側は、親権や監護権は憲法が保障する基本的人権だと主張したが、一審判決は否定。立法措置の必要性に関しては「国民の共通認識が形成されておらず、立法の具体的内容も検討すべき事項が多数あり、国民の議論が十分な状態だとはいえない」とし、憲法違反は認めなかった。
小泉法相が就任会見 在留資格ない子への特別許可、方針「引き継ぐ」
出典:令和5年9月14日 朝日新聞
小泉法相が就任会見 在留資格ない子への特別許可、方針「引き継ぐ」
内閣改造で法相に就いた小泉龍司衆院議員が13日夜、法務省で記者会見をした。日本で生まれ育ちながら強制退去処分となり、在留資格がない外国籍の子どもらに法相の裁量で「在留特別許可」を与えるという斎藤健・前法相の方針について「良いアイデアだ。考え方を引き継ぎ、実態を見ながら、より多くの子どもたちを救えるように取り組みたい」と述べた。
法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、離婚した父母の双方が親権を持つ「共同親権」の導入を視野に検討されていることについては「もちろん反対論も消極論もある。ぶつかり合いながら議論が高まっていくのは良いことだ。子どもの利益を確保する観点から、実効性の高い議論を期待したい」と語った。
また、死刑制度について問われると、「慎重に検討すべきだ」としつつ、世論調査の結果も踏まえ「廃止することは、現時点では適当ではないと考えている」とした。(久保田一道)
離婚後の親権 “共同親権も可能” 具体的ルールが焦点に
出典:令和5年8月30日 NHK
離婚したあとの子どもの親権について、法制審議会の部会は、父と母双方が持つ「共同親権」とすることも可能だとした要綱案のたたき台を示しました。今後の議論で実情に即した具体的なルールを定められるのかが焦点になります。
現在、夫婦が離婚したあとは、いずれか一方が親権者となる「単独親権」という制度が採用されていますが、社会情勢の変化に対応できていないなどの指摘もあることから、法制審議会の家族法制部会は29日、見直しに向けた要綱案のたたき台を示しました。
それによりますと、夫婦は離婚したあとも子どもを養育する責務があるとして、父と母の双方が親権を持つ「共同親権」とすることも可能だとしています。
ただ、配偶者からの暴力や子どもへの虐待があった場合などは、例外として父か母のいずれか一方が親権者になれるとしています。
また養育費については、事前の取り決めをせずに離婚した場合の不払いを避けるため、一定額を請求できる「法定養育費制度」を設けることも検討するとしています。
法務省によりますと、29日の議論ではたたき台におおむね賛同が得られたということです。
家族法制部会はことし中に要綱案を取りまとめたいとしていて、今後の議論で「共同親権」を認めないケースや、子どもと同居していない親の権限の範囲など、実情に即した具体的なルールを定められるのかが焦点になります。
「共同親権」海外の事例から見たメリットと課題 日本で導入するならどんな問題が?
出典:令和5年8月30日 東京新聞
「共同親権」海外の事例から見たメリットと課題 日本で導入するならどんな問題が?
法制審議会の29日の部会で、離婚後も父母双方が子の親権を持ち続ける「共同親権」の導入に向けた民法改正案の方向性が示された。早ければ来年の通常国会での法改正で、離婚後の親権は父母のいずれかが持つという現行制度が大きく変わる可能性がある。諸外国の類似の制度から、共同親権の利点や課題を探った。(大野暢子)
◆定着したアメリカ「両親に養育されることが子の利益」
離婚後も両親が共に子を育てる仕組みが定着しているのは米国だ。離婚数が増加し、男女平等の原則が普及していった1970年代以降、共同監護法が各州に広がり、これまでにほぼ全土で立法化されている。
両親は離婚する際、子と過ごす時間の配分や教育・医療の方針、意見の食い違いがあった場合の対応などをまとめた「養育計画書」を裁判所に提出する義務がある。対立している両親は別々に計画書を提出し、裁判所の判断を仰ぐ。
関西学院大の山口亮子教授(家族法)は「養育を分担し、子を互いの家に行き来させる例もあれば、定期的に面会交流し、重要事項を話し合いで決める父母もいる」と説明。婚姻の有無とは別に、両親に養育されることが子の利益につながるとの考え方が浸透しているとして「日本も同様の仕組みが望ましい」と話す。
◆厳格なドイツ「容易に親権を剥奪される」
ドイツも97年に民法を改正し、離婚後の共同親権を導入。京都大の西谷祐子教授(比較法)によると、米国と違って日常の養育は子と暮らす親が担い、重要なことは両親で決めるのが通例。虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の問題もあまり聞かれず、社会に根付いているという。
日本では、離婚後に子と疎遠になっている親たちを中心に、諸外国を手本に共同親権の導入を望む声がある一方、関係が悪化した父母の間では、子の面前でのDV、虐待、紛争といった負の影響が続く恐れがあるとして慎重論が消えない。
諸外国の仕組みがそのまま日本社会になじむのかという懸念もある。西谷教授は「ドイツでは養育費の不払いは刑事罰の対象で、DVや虐待をする親は、離婚前でも日本より容易に親権を剥奪されるなどの厳格な制度がある」と指摘。日本で導入する場合には、弱い立場にある親や子にしわ寄せがいかないような環境整備が必要だと語る。
◆被害が表面化しづらくなったオーストラリア
オーストラリアは95年に連邦家族法を改正し、子が父母の両方から世話をされる権利を明記。2006年には、主な世話を担う「監護親」を決める際、別居する親と子の交流に前向きな親を優先する条項を設けたが、わずか5年後の11年に削除された。
大阪経済法科大の小川富之教授によると、この条項によって、監護親が「DVや虐待の被害を訴えて認められなかったら、交流に消極的と見なされて監護親でいられなくなる」と考え、被害が表面化しづらくなったという。「暴力などがないかを見極める支援機関や相談窓口を整備したのに、子に危害が及ぶ事件も起きた。海外で成功したから日本でもという主張は乱暴だ」と訴える。
共同親権に関し、法務省に届いたパブリックコメントは約8000件。賛成意見の多くは団体から寄せられ、個人では単独親権の現行制度を支持する声が目立った。導入の是非を巡る国民的な議論はまだ深まっていないのが実情だ。
共同親権導入を明記…法制審がたたき台、「暴力で離婚」は対象外
出典:令和5年8月30日 読売新聞
共同親権導入を明記…法制審がたたき台、「暴力で離婚」は対象外
法務省が共同親権導入案 離婚後、父母双方または一方に
出典:令和5年8月29日 日本経済新聞
法務省は29日、法相の諮問機関である法制審議会の部会で、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入する案を示した。離婚後の親権に関して「父母の双方または一方を親権者と定める」とした。父母どちらかの単独親権に限る現行制度を見直す議論に入る。
法務省が民法改正要綱案のたたき台を部会に提示した。2月までに集めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえた。
現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。日本は慣例として協議離婚が多いため、裁判所などが関与する仕組みが整っていない。離婚後も父母で子育てするための環境を整備する。
法制審のこれまでの議論では、父母が離婚時に共同親権で一致できなかった際の取り扱いが論点の一つだった。
法務省の案によると、父母間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所が親子や父母の関係を考慮して親権者を指定できる。親権が決まった後も裁判所の判断で変更できるようにする。
虐待などが起きている事案も想定した。子の利益に関して「急迫の事情があるとき」は離婚前であっても単独の親権を行使できると明記した。
共同親権に関連して、子の日常の面倒をみる「監護者」についても考え方を示した。
親権を持つ者のうち一方を日常の世話などをする「監護者」と決めることができる。監護者の判断は、他の親権者よりも優先される。教育などには監護者ではない親権者も関わることができる。
離婚後の養育費を巡っては、養育する親がもう一方の親に請求しやすくする仕組みを整える。
優先的に養育費を請求する「先取特権」を付与することで、一般的に認められる額を差し押さえる権利を持たせる。現在は差し押さえを申し立てるには裁判所の調停や公正証書が必要になる。
今の制度では父母間の取り決めや裁判所の調停がないと金銭を請求することができない。父母が養育費に関する協議なしに離婚した場合、最低限の経済的支援を請求できる「法定養育費制度」を検討対象に加えた。
共同親権の導入はドメスティックバイオレンス(DV)などへの懸念から反対意見が根強い。意見公募は個人のおよそ3分の2が反対だった。
法務省の担当者は「今後の議論次第で要綱案の記載は変わる可能性がある」と説明する。同省は民法改正案を国会に提出する時期を示していない。離婚後も父母が納得して子育てに関わる制度を設計できるかが焦点だ。
海外の制度は議論の参考になる。たとえば養育費に関して海外には公的機関が関与する制度が整う。米国や英国は公的機関を通じて給与から天引きをする仕組みだ。オランダでは離婚前に養育費を定めることが義務付けられている。未払い者に対しては国の徴収機関がより高い額を回収する。
親権の見直し論議を後押ししたのはグローバル化の進展が背景だった。共同親権を導入する国で国際結婚して生まれた子を日本に連れ去る事例が問題となった。
主要国では共同親権が一般的だ。米英のほかドイツ、フランス、韓国などが定める。単独親権は少数派でインド、トルコが採用する。日本では2014年に国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が発効した。単独親権は同条約違反という指摘がある。
共同親権」導入案 法制審部会、事務局がたたき台
出典:令和5年8月29日 産経新聞
離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で29日、一定の条件を満たせば父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を柱とした要綱案のたたき台が事務局から示された。
昨年11月に部会が公表した中間試案では、共同親権を「認める」「認めない」の両論併記にとどまっていた。パブリックコメント(意見公募)やその後の議論を踏まえ、共同親権導入に向けて一歩踏み込んだ形。
現行の民法は、離婚後は父母いずれかの単独親権しか認めておらず、共同親権が認められれば家族法制が大きく変わることになる。ただ、部会内には慎重な意見もあり、法相に答申する要綱案の策定に向け、さらに議論を進める。
たたき台では、離婚協議の中で父母が合意すれば、共同親権か単独親権を選べると明記。合意がなければ、裁判所に判断を委ねる。判断に際しては、子の利益や父母同士の関係を考慮するよう求め、ドメスティックバイオレンス(DV)が確認された場合などは単独親権とする。
養育費については、他の債権者に優先して取り立てられる「先取特権」や、合意がなくても最低限の金額を要求できる「法定養育費」の制度の創設も盛り込んだ。
別居親と子供との面会を、早い段階で裁判所が促せる手続きも設けた。
北村弁護士、福原愛さん長男連れ去り問題解説「国際的に見て日本の恥」「置いていかれた方の親の親権を」
出典:令和5年8月22日 スポニチ
北村弁護士、福原愛さん長男連れ去り問題解説「国際的に見て日本の恥」「置いていかれた方の親の親権を」
弁護士の北村晴男氏(67)が、23日までに公式YouTubeチャンネルを更新。卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん(34)と、元夫で16年リオデジャネイロ五輪台湾代表の江宏傑氏(34)の長男の引き渡しをめぐる争いについて言及した。
江宏傑さんは7月27日に東京都内で緊急会見を開き、福原さんが長男を日本に連れて帰り、長男と接触できない状態が続いていると主張。福原さんへ向けて「長男を返して」と呼び掛け、強制執行の申し立ても行ったとした。これに福原さん側が法律上さらに上訴して争う手段が認められているとして反論の声明を出すなど、対立の根深さをのぞかせている。
この件に関して北村氏のもとに、「共同親権を持つ親同士、元夫婦の間で誘拐罪は成立するのでしょうか?」という質問が寄せられた。北村氏は「誘拐罪が成立する一般的なケース」として、「国際基準でいうと、婚姻中は共同親権を持っている。そこである日、お母さんが子供を連れて出ていくと、国際標準で言えばこれだけで誘拐罪にあたります」と説明。「ところが日本では、長いこと誘拐罪として立件してこなかった。現在も立件されているケースは少ない」と指摘した。
日本でよく見られる「子供を連れた別居」のケースについて、北村氏は「暴力を振るわれるなどの正当な理由があればさておき、そこで正当な突然理由なく連れて行ってしまうと、これは置いていかれた方の親の親権を害している。これは誘拐罪にあたります」と主張。日本ではこのケースが「いまだに横行している」といい「結婚して子供をつくった以上は、お子さんについてどのように育てていくかは2人で話し合って決めることで、これは誘拐に違いないんです」と、改めて強調した。
これらのケースについて、現在は「ようやく法務大臣・警察庁も認めて、通達も出されているようです」というが、「しかしながら、国民の意識・母親・父親の意識はそこまで変わっていないので、いまだに子の連れ去りが横行しているように思います」と、国民の意識に変化がないことを嘆き「これは大変な日本の間違え、国際的に見て日本の恥なんです」と厳しく追及した。
国際的に見て日本が特異なため、この問題が「国際結婚で顕著に出る」という。「日本は、誘拐罪という重罪を犯したものを野放しにするとんでもない国だ…という非難をずっと浴びている。これについて、きちんとした国民の意識の変化がないものですから」と指摘し「そもそも父親と母親も、子供と十分に交流する権利がある。それだけではなくて、お子さんにとっても、お父さん・お母さんと交流して愛情を受ける権利を持っています。その権利を妨げるような単独親権は、とんでもない悪法なんですよね」と、日本の現行を悲観した。
北村氏らは、「どちらか一方が会わせることを拒んだ場合には、速やかに裁判所に申し立て、親権を一時停止できるという制度をつくればいい」として、「我々は民間法制審の立場でもって、そういう案をつくって法務省にも出し、一般にも公開している」と、制度の見直しを求めているという。しかし「残念ながら法務省は共同親権をつくろうとしません。日本では、絶対に共同親権にしたくないという活動家を、法制審議会の中に何人も入れて“共同親権になってしまったら困る”と。絶対にそれを阻止しようという人たちなんですね」と持論を展開。「我々は声を上げてきました」と、この問題への危機感を繰り返し主張した。
約6割が親子の面会取り決めず…『離婚後の子供の養育』に関する個別相談支援 石川県が無料実施へ
出典:令和5年8月22日 石川テレビ
約6割が親子の面会取り決めず…『離婚後の子供の養育』に関する個別相談支援 石川県が無料実施へ
石川県は離婚後の子どもの養育に関する相談支援について、専門相談員による個別の相談を無料で実施することを明らかにしました。
馳知事は22日の会見で、離婚後の子どもの養育に関する支援についてFPIC・家庭問題情報センターと連携して取り組むことを発表しました。
具体的には、離婚後の親子の面会について家庭裁判所の元調査官など専門の相談員による個別のオンライン相談を無料で実施するということです。
馳知事:
「DV被害などにより離婚した家庭があることに十分留意しながら、子どもの権利や利益を最優先にしっかりと取り組みたい」
県の調査によりますと、離婚した夫婦の約6割が親子の面会について取り決めていないということです。
オンライン相談は8月27日に始まり、2カ月に1回の頻度で実施します。県ではこのほか県内の相談員に対する研修も実施する予定です。
離婚後の親権のあり方は 橋下徹氏「共同親権を原則にして、単独親権を例外に」 山口真由氏「もう少し離婚しやすくしたほうがいい」
出典:令和5年8月17日 ABEMA TIMES
離婚後の親権のあり方は 橋下徹氏「共同親権を原則にして、単独親権を例外に」 山口真由氏「もう少し離婚しやすくしたほうがいい」
元財務官僚で信州大学特任教授の山口真由氏が、5日のABEMA『NewsBAR橋下』に出演。日本の親権制度について、橋下徹氏と議論を交わした。
橋下氏は「日本は単独親権制度だ。ただ、共同親権にも問題はあって、DV・暴力などがあって離婚した場合、その後も連絡を取り合わなければならないというのは難しい。この両者は心情的に激しい対立関係にある」と説明。
山口氏は「特に日本は“母子一体”という考えが強く、離婚した後の父親との継続的な連絡があまりうまくいっていないように思う。お子さんが小さい頃は“ママ、ママ”という感じかもしれないが、大きくなるにつれて父親に相談したいことが出てくるし、大学進学などの話になれば支援が必要な時もある。そこが今まで軽視されすぎていたのではないか」と指摘する。
7月、卓球のオリンピックメダリスト・福原愛さんに対し、元夫の江宏傑さんが長男を引き渡すように求めて会見を開いたことが話題となった。このケース以外でも、国際結婚が破綻した2人の間では子どもの親権をめぐるトラブルが相次いでいる。
橋下氏は「共同親権の不都合さとして、単独親権派の人たちは“離婚したのに何でもかんでも相手に相談して、同意をもらわなければいけないのか”と言うが、それは仕方がないことだと思う。共同親権では引っ越しもできなくなるというのも、正当な理由があれば相手の同意がなくてもできると思うが、子どもがいるならやはり協議は必要だろう。しかし、子どもを海外に連れて行かれてしまうと、単独親権ではハーグ条約(※1)で取り戻すことができない。やはり共同親権が原則だと思う」と述べた。
※ハーグ条約:国境を越えて不法に連れ去られたり、元の居住国に戻されない子どもを迅速に返還するよう求めている条約。日本を含む103カ国が締結。台湾は未締結
山口氏は「子どもにとってどちらの国で生きていくかはすごく大事な問題であると同時に、慣れない国では片方の親に密着した関係になっていく。その過程で、もう片方の親の悪口を言って、子どもが“ママ・パパを守らなきゃ”という感じになっていく例もある。そうなると、“本来見られたであろう広い世界を狭めるかもしれない”“子どもの可能性の扉を開いているのかな?”と思うところがある」と教育の視点から語る。
こうした話を受け、橋下氏は「日本も共同親権を原則にして、夫婦間の状況でDVなどがある時など、例外的な場合に単独親権にする。これに整理し直さなければいけないと思う」と提案した。
一方で山口氏は「もう少し離婚をしやすくしたほうがいい」との持論を展開し、「かなり揉めてから離婚するので、お互いに“協力していこう”とはならない。もう少し手前の、“夫婦としてはバラバラになったけど、親としては同じ方向を向いて歩けるよね”という段階でできたほうがいいかもしれない」と述べる。
橋下氏は「離婚を厳しくしているのは、1つは宗教的な理由、日本は関係ないと思うが。もう1つは昔、専業主婦が多かったから女性を守るという部分があったと思う。でも今は、専業主婦世帯が3割未満で、共働き世帯は7割以上。もちろん経済的なサポートはしっかりした上で、離婚をしやすくしてもいいのではないか。ただ、うちの家庭は別ですよ 笑」とした。(ABEMA『NewsBAR橋下』より)
「子どもの視点に立った調停をしてほしい」長期化する離婚・面会調停、当事者が家庭裁判所に望むこと
出典:令和5年8月12日 Yahoo!ニュース
「子どもの視点に立った調停をしてほしい」長期化する離婚・面会調停、当事者が家庭裁判所に望むこと
毎年、およそ18万人の子どもが親の離婚を経験する。どちらが子どもの親権を持つか、監護するか、面会交流は、などについて夫婦間で協議が整わない場合、家庭裁判所を利用することになるが、その運用に不満を抱く当事者は多い。ある男性はもう4年以上も家庭裁判所通いを続けている。「妻もぼくも子どもも誰も幸せになっていない。ただ時間ばかりが過ぎる」。離婚・面会調停の当事者が家裁に求めるものとは。(取材・文:上條まゆみ/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
このままでは一生子どもに会えないかもしれない
「え、またそこから?」
関東近郊に住む会社員、沖田裕二さん(仮名、45)は、この春異動してきたばかりの家庭裁判所の裁判官に「離婚事由から確認したい」と言われ、激しい徒労感に襲われた。
「『記録は引き継いでいるが、自分で聞きたい』と言われました。今までの聞き取りはなんだったんだと思いますよね。2019年4月に調停を始めて、4年4カ月で裁判官が4人も代わっているんです」
沖田さんは月1回1時間の子どもとの面会交流のために、自宅から400キロも離れた地方都市に車で通う日々をもう1年以上も続けている。
子どもと会うときは、妻の希望で面会交流支援団体の付き添いがつく。レンタルルームを借りてゲームやおもちゃで遊ぶときも、室内に支援員がいる。
「DVも虐待もないのに、なぜ付き添いが必要なのでしょう。わずか1時間しか子どもに会えないのも理不尽だと感じます。家庭裁判所調査官の調査では、子どもは『もっとパパに会いたい』と話していたのに。妻には婚姻費用を払っているうえ、面会交流支援団体の費用もレンタルルーム代も、もちろん交通費も宿泊代もこちらもちです。子どもの養育のためにためておきたいお金なのですが……」
2019年1月、沖田さんの妻は当時5歳の子どもを連れて家を出たまま、帰ってこなかった。妻から離婚調停を申し立てられると、沖田さんはすぐに面会交流と子の引き渡し、保全処分を申し立てた。
「離婚はともかく、子どもと離れたくありませんでした。家計は9割以上、家事・育児も4割くらいはぼくが担当していたし、休日は父子で外遊びをして過ごすことも多く、子どもとは仲がよかったんです。面会交流や子どもの養育について取り決め、しっかり子どもと会えるようにしてから、離婚の話し合いをしたいと思いました」
ところが、近隣のマンションに住んでいた妻が、子どもを連れて実家近くの現在の住所に引っ越した。そちらの家庭裁判所に管轄を移して調停を始めることになったが、コロナを理由に延期となった。子どもには2020年3月に2時間だけ会えたが、その後は面会できないまま。1年後にやっと、Zoom越しの面会交流が許された。Zoomをつなぐとき、沖田さんは「子どもが自分の顔を忘れていたらどうしよう、人見知りしたらどうしよう」と不安だったという。画面の向こうから「パパ!」とうれしそうに呼びかける姿を見て、ようやく安堵した。
その後も、面会交流の拡大をめぐる話し合いは折り合いがつかず、「子どもに会いたい」沖田さんと、「会わせたくない」妻の葛藤は大きくなっている。
調停委員も頼りなかった。
「調停委員はいい人で親身になって話を聞いてくれましたが、逆に言えばそれだけなんですよ。ぼくの味方をしてほしいのではなく、もっと子どもの視点に立って調停を進めてほしいのです」
このままでは一生子どもに会えないかもしれない。危機感をもった沖田さんは2022年4月、「月1回、第三者機関の付き添い型支援を利用して面会交流する」との内容に合意して、面会交流調停を終わらせた。内容には不満だらけだが、子どもに会えることを優先させた。
一方の離婚調停は不成立に終わり、裁判が進行中だ。争点は親権。
「離婚事由は『夫婦の気持ちのすれ違い』。浮気もDVも悪意の遺棄もないぼくが親権を奪われるのは納得がいかない。どちらかに親権者を決めなければならないのであれば、別居親と自由に交流させる寛容性をもったぼくのほうが、親権者としてふさわしいと主張しています」
しかし、沖田さんの主張はなかなか通らない。統計データによれば、令和になった今でも、離婚後の親権の約9割は母親が持つ。母性優先、「現状維持の原則」(今現に暮らしている親との暮らしを優先する原則)の考え方は根強い。
「子どもの心身の成長にコミットしたい」別居親の望み
民法の離婚後の子の監護に関する条文に、「面会及びその他の交流」について協議すべしという文言が盛り込まれたのは2011年。条文には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とある。
しかし、それから10年後の2021年度の面会交流の実施状況は、母子世帯で30.2%、父子世帯で48.0%。実施している場合でも、その回数は「月1回」が最多だ。これは「子の利益」を優先した結果なのか?
家事事件を多く手がける弁護士の梅村真紀さんは、「子の利益」を考慮することの難しさについて、こう話す。
「例えば、面会交流で言えば、『子の利益』につながる面会頻度を決めるべきなのですが、同居親の拒否感情が強い場合、回数を決めても守られないことが多い。守られないなら意味がないということで、家裁は『最低限、これくらいなら同居親も応じるだろう』という程度にしか出さない傾向があるのです。しかし、それでは別居親がつらい。だからといって、面会交流を増やすための調停を再度申し立てると夫婦間の葛藤がさらに高まることになり、面会頻度が減る危険性がある。悩ましいところです」
離婚した元夫婦の関係や子どもとの関係は一様ではないため、「子の利益」を一律に評価することは難しい。とはいえ、以前は親が離婚すると子どもは別居親と没交渉になることが「ふつう」だったが、1994年に日本が批准した子どもの権利条約では、子どもには両親から引き離されない権利があると認めている。つまり、特段の事情がない限り、離婚後も子どもが両親と交流をもつことは子どもの利益につながると考えられる。
沖田さんの望みは、父親として継続的に子どもと関わり、心身の成長にコミットすることだ。
「思い切り体を動かしたり、小さな冒険に出かけたり。もう少し大きくなったら仕事の話をしたり、社会問題について語り合ったりしてみたいです」(沖田さん)
また、離婚にともない話し合わなければいけないことは、子の親権や面会交流だけではない。
「調停では、離婚するかどうかに始まり、慰謝料や婚姻費用、離婚するのであれば財産分与や年金分割についても話し合わなければなりません。これらは基本的に同時に進めていきますから、子について話し合う時間はどうしても限られてくるのです」(梅村さん)
当事者のあいだでささやかれる「調停委員ガチャ」
では、家庭裁判所の側は「子の利益」をどう見ているのか。
家庭裁判所で扱う家事事件は、調停前置主義といい、審判の前に調停から始めなければならない。調停委員会は、裁判官または調停官と、2人の調停委員、子どもがいる場合は家庭裁判所調査官が加わる。
西日本の某県で調停委員を務めた加山仁美さん(仮名、57)。家庭の主婦で自営の手伝いをしていたが、面倒見のよい人柄を買われて、調停委員をしていた知人に声をかけられた。
加山さんは、子どもがいる家庭の事件では、まず初回に子どもの状況を聞き取り、子どもが両親の紛争で不安な気持ちでいることや、親と子どもの気持ちは別であることを理解してもらうよう、申立人・相手方双方に働きかけをしていたという。
「調停委員になると、研修の機会がたくさんあるんです。すべての調停委員に義務づけられているものから、特定のテーマに絞った任意のものまで、さまざまなものがありますが、積極的に参加して、傾聴について心理学的に学んだり、家族関係について理解を深めたりするうちに、『ふつうの家族』なんかない、と思うようになりました。こちらが『ふつう』と考える価値観を押しつけてはいけないと肝に銘じていました」
家族に関する価値観は、時代によって変化する。しかし、価値観をアップデートする努力をしない調停委員も多く、不満をもつ当事者は多い。当事者界隈では「調停委員ガチャ」などという言葉もささやかれている。加山さんは、「学んでほしい人ほど、研修に出てこなかったですねえ」と振り返る。
「面会交流は過去の清算ではなく、子どもの将来の問題」
当事者が家庭裁判所に抱く不満のもう一つは、「調停で取り決めたことが守られない」ということだ。家裁から履行勧告をしてもらうことはできるが、相手が応じない場合、強制することは難しい。
香川県の増田卓美さん(78)は、調停のあり方に限界を感じて、面会交流支援団体を立ち上げた。増田さんは公務員を定年退職後、調停委員に。それから5年後に民法が改正され、面会交流について協議するように定められた。
「あるとき、面会交流について合意し、調停合意書にもきちんと取り決め事項を書いて離婚したご夫婦がおられたのです。よかったよかったと思っていたら、1年後、再調停を申し立ててこられた。要するに、約束した取り決めが守られなかったんですね。『法律に書いてあってもダメなんだな。面会交流についての調停は、調停成立に漕ぎつけるだけでは、子どもの福祉とはいえない。最後の受け皿も必要なんだ』と気づきました。『面会したい』『面会させたくない』という親同士の間に入る第三者機関として面会交流支援センターを立ち上げることになったのです」
2015年12月にNPO法人面会交流支援センター香川を設立。支援を始めてみると、調停の場ではわからなかった子どもの心が見えてきた。
「調停で同居親が『子どもが嫌がっているから別居親に会わせたくない』と言うことは多いのです。でも実際には、別居親に会ったとたん、バーッと走っていったりするのです。反対に、同居親のところに戻るときは、それまでニコニコしていたのがパッと顔色を変えて、楽しかったことなんかなかったかのようにふるまう。子どもが嫌がっているというのは同居親の気持ちに配慮する忠誠心、葛藤だと思うんです。子どもの本当の気持ちは違うんだな、両親に挟まれて一番しんどいのは子どもだなと、強く思うようになりました」
増田さんが提唱するのは、子どもがいる夫婦が離婚するときは調停前に必ず親ガイダンスを受ける仕組みだ。子どもにとって望ましい離婚の形を夫婦ともに学ぶ。一部の家庭裁判所ではすでに任意で実施している。これを全国的に義務化する。夫婦で「子の利益」が共有できれば協議は整いやすくなり、調停となった場合も進行はスムーズになるはずだ。
「制度というのは、行政や司法だけでは賄いきれないのが世の常だと思います。子どもの権利、最善の利益を目的にした面会交流に関しては、財産分与などの紛争解決方法とはちょっと違います。デリケートな問題を含む面会交流は過去の清算ではなく、子どもの将来の問題です。父母の歩み寄りが不十分で第三者機関の支援が必要となる場合の面会交流については、公正・中立性が大原則の家庭裁判所であったとしても、何らかの形で民間と連携または委託があってもよいと思うのです」
「家裁は対立型ではない合意形成を支えて」
家族法に詳しい二宮周平さん(立命館大学名誉教授)も、「家庭裁判所の福祉的な機能の一部を民間団体に委託することは、有効な手立ての一つだと思います」と話す。
「韓国では、家裁が離婚前の親ガイダンスを行いますが、カウンセリング等は家裁が委託した外部機関が行っています。日本でも家庭裁判所と外部機関が連携する仕組みをつくることは、現行法のもとでも十分に可能です」
家裁の裁判官の異動サイクルが早いことも、改善の余地がある。
「赴任して数年で異動になるので、裁判官が家事事件に必要な専門知識を身につけられない、あるいは身につけてもすぐにいなくなってしまう。それも、子どもの視点がないがしろにされがちな理由の一つなのです」
台湾では、家庭裁判所の裁判官は、自分から希望しない限り、異動することはない。韓国でも、最長7年まで同じ裁判所にいることができる。
「家庭裁判所はほかの裁判所と違い、司法的機能と福祉的機能を併せ持ちます。問題を法的に解決するだけではなく、当事者や子どもが幸せに生きていくために必要なサポートをする役割を担うべきなのです。離婚をしても父母が親として子どもの健全な成長を見守り、支える責任があります。家庭裁判所の裁判官も調査官も調停委員も弁護士も、対立型ではない合意形成を支えてほしい。それが何より子どもの利益につながると思うのです」
「子どもをめぐる課題(#こどもをまもる)」は、Yahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。子どもの安全や、子どもを育てる環境の諸問題のために、私たちができることは何か。対策や解説などの情報を発信しています。
日本の親権制度見直しへ、オーストラリアが与野党一致で対日攻勢強める 外相が梅村参院議員と会談も
出典:令和5年8月9日 SAKISIRU
日本の親権制度見直しへ、オーストラリアが与野党一致で対日攻勢強める 外相が梅村参院議員と会談も
オーストラリアは昨年5月の総選挙で9年ぶりに政権交代したばかりだが、野党保守連合が日本人配偶者による自国民の実子連れ去り被害の打開へ向け、労働党政権に協力し、日本政府に対して親権制度見直しを求める動きを加速している。現地紙シドニー・モーニング・ヘラルド(SMH)が8日報じた。
野党側の外交政策のスポークスマンを務めるサイモン・バーミンガム上院議員はSMHの取材に対し、「子供たちの最善の利益に焦点を当て、この状況を改善するオーストラリア政府によるあらゆる行動に超党派の支援を提供するだろう」と全面的に協力する意向を示した。バーミングガム氏はモリソン前政権で財務相や貿易相を歴任。政権交代後は野党・自由党の指導的立場にある。
ここにきて政権側はペニー・ウォン外相が連れ去り被害について「あまりにも悲痛だ」と述べ、今月3日には同国を訪れた参院維新会派所属の梅村みずほ氏と会談するなど新たな動きを見せている。ウォン外相が外国の野党議員と会うのは極めて珍しいといい、日本の国会議員の中で共同親権推進に積極的な1人である梅村氏と敢えて接触した。SMHは同国外務省が自国民に日本の単独親権制度を警告した経緯も挙げ、「オーストラリア政府が非常に敏感になっている」と指摘している。
過去20年、3度の政権交代があった中で、歴代政権が日本に対し連れ去り被害への対処を求めてきたが進展はなかったものの、日本で親権制度見直しを検討している動きを踏まえ、与野党が歩調を合わせた格好だ。
オーストラリアでは今年3月、日本人配偶者らによる連れ去り被害を取り上げるテレビ番組の特集が放映。オーストラリア人との間に生まれた子どもが2004年以来、少なくとも82人が連れ去られたと報じ、国内での関心を改めて高めた。今年3月にも駐日大使が斎藤法相に会談し、改めて親権制度の見直しを申し入れている。
福原愛さん元夫会見、台湾ではどう受け止められたのか 「ここまでくると醜すぎる」「道徳あるべき」
出典:令和5年7月27日 JCASTニュース
福原愛さん元夫会見、台湾ではどう受け止められたのか 「ここまでくると醜すぎる」「道徳あるべき」
卓球の元日本代表で五輪メダリストの福原愛さん(34)の元夫で卓球台湾代表の江宏傑氏(34)が2023年7月27日、東京都内の日本外国特派員協会で会見を開き福原さんに子供の引き渡しを求めた。
会見には大渕愛子弁護士(45)と台湾の代理人弁護士が出席し経緯を説明した。代理人弁護士によると、江氏と福原さんは21年7月に離婚し、2人の子供に関しては江氏と福原さんの共同親権とする合意がなされ、子供は台湾で暮らしていた。
■「よく1年間も我慢できたね」
22年7月23日に面会交流のために江氏が台湾の空港で息子を福原さんに引き渡したところ、福原さんは1週間後に江氏との連絡を絶った。江氏と息子はそれから一切の接触が遮断されている状況だという。
福原さんと江氏は16年リオデジャネイロ五輪後に結婚し、17年に長女、19年に長男が誕生した。
世界的な卓球選手だった福原さんは台湾でも知名度が高く、江氏の会見を複数の地元メディアが速報した。
地元メディア「自由時報」(WEB版)は、「福原愛さん、1年間音信不通に台湾ネット民も叱責『「道徳はあるべき』」とのタイトルで記事を展開した。
記事では、江氏が長男を引き渡した昨年7月から福原さんと連絡が取れない状態にあるとし、福原さんが重要なルールを破ったことに国内のインターネットユーザーが激しく憤っていることを伝えた。
インターネットでは「ここまでくると醜すぎる」「(福原さんは)必要なモラルを持たなければならない」「(江氏は)よく1年間も我慢できたね」「もう本当に耐えられない」などの声が寄せられたという
大渕弁護士は江氏と長男が引き離されている状況に関して、「福原愛さんは世界卓球のゼネラルマネジャーを務められたり、日本の上場企業の社外取締役を務められたり、国内外において活躍をされています。そういった立場の方がこのような行動をしてよいものか、ということは問題提起すべき事項であると考えております」との見解を示した。
そして「まずは一日も早く一刻も早く江さんに子供を引き渡して頂きたい。この点を切に訴えさせていただきたいと思っております」と訴えた。
福原愛さんに東京家裁が異例の子供引き渡し保全命令 大渕弁護士は強制執行手続き明かす 引き渡し拒否なら未成年誘拐で刑事告訴も
出典:令和5年7月27日 デイリー
福原愛さんに東京家裁が異例の子供引き渡し保全命令 大渕弁護士は強制執行手続き明かす 引き渡し拒否なら未成年誘拐で刑事告訴も
卓球女子12年ロンドン、16年リオデジャネイロ五輪団体メダリストの福原愛さん(34)の元夫でリオ五輪台湾代表の江宏傑氏(34)が27日、都内の日本外国特派員協会で緊急会見を開いた。大渕愛子弁護士、台湾の弁護士とともに登壇した。
江氏は「本年7月20日、日本の裁判所の審判結果を受け取りました。福原愛さんに対し、息子を私に引き渡すように命ずる内容です。私からは、日本の裁判所が審判を出してくださったことに感謝申し上げるとともに、『早く息子に会いたい』ということを申し上げたいです。私も諦めない。早く子供に会いたいです。早く弟をお姉ちゃんに会わせたい」と、涙を浮かべながら訴えた。東京家裁での審判だという。
江氏によると、昨年7月23日に台湾の空港で江氏が長男を福原さんに引き渡したが、1週間後から福原さんが連絡を絶ったという。面会交流期間は「夏休みが終わるまで」だったが、現在に至るまで長男には会えていないという。
同席した大渕弁護士によると、日本の裁判所において、福原愛さんの方から親権指定の審判申し立てがなされ、江さん側も子の引き渡しを求める審判を申し立て、緊急性があることから保全の命令を求める審判も申し立てたという。1週間前の7月20日に福原さんに対して子の引き渡しを命ずる審判が出された。
大渕弁護士は「通常の審判に加え、保全の命令も出された。ただちに子を引き渡せという、非常に珍しい。余程のことがない限り、裁判所は認めてくれない審判。福原さんはただちに子供を引き渡す必要がある。不服申し立てをするしないに関わらず、引き渡しをする必要がある」と、説明した。
福原さん側に子供の引き渡しを求める連絡をしたが、「現在に至るまで応じるという連絡を受けていない。息子さんがどこにいるのかも分からず、大変不安に思っています」と明かし、「中止するように求めるメール、FAXを受け取ったが、その連絡にも子の引き渡しについては一切の連絡がなかった。なぜこのように江さんが会見を開かざるを得なくなっているのか。福原さんには自身の行動を振り返ってしっかり客観的に考えていただきたい」と、語った。
さらに「強制執行の申し立てを行った。しかしながら、福原さんは日本に子供をとどめ置いてる期間に、子供を連れて複数回、シンガポールを訪れていたという情報に触れていますので、任意の引き渡しや強制執行の結果を待っていたら、出国の可能性も否定できないと考え、大変心配しています。ただ、引き渡しの強制執行は難しい。子供を傷つける面もある。引き続き、強制執行を待つと共に、任意の履行を求めていく。強制執行という形ではなく、平和に引き渡して欲しいのが江さんの強い思い。紛争がずっと続くことは望まないこと」と、21日に強制執行手続きを行っていることを明かした。仮に出国した場合については「先ほどシンガポールという名前も出たが、例えばシンガポールはハーグ条約の締結国。ハーグ条約に基づいてまず日本に戻してくれという返還命令が出て、引き渡してくれと。また手続きに時間がかかる。いつまでも江さんに子供が会えない。心配している」と語った。
また任意の引き渡しが実現しなかった場合について、大渕弁護士は「江さんとはまだ話し合っていない」とした上で、「選択肢としては未成年者誘拐罪での告訴が考えられる」と、考えを示した。
その上で大渕弁護士は「福原愛さんはWTT(ジャパン)のゼネラルマネージャーを務められたり、日本の上場企業の社外取締役、国内外で活躍されている。そういった立場の方がこのような行動をしていいのか、問題提起すべき事項と考えている」と、訴えた。
父母の合意なしで共同親権の適用も? 裁判所が判断との新制度案、法務省が初めて提示
出典:令和5年6月7日 東京新聞
父母の合意なしで共同親権の適用も? 裁判所が判断との新制度案、法務省が初めて提示
離婚後も父母がともに子の親権を持つ「共同親権」の導入を巡り、法務省は6日、裁判で離婚する父母の間で意見が対立した場合、裁判所が単独親権か共同親権かを決定できるようにするとの考え方を法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会に示した。これまでは協議離婚する父母が合意した場合、共同親権を認める方向で議論してきた。
6日の部会では、裁判で父母のどちらが親権を持つのか合意できない場合の制度設計などを議論した。法務省はこれまでの議論を踏まえた上で、たたき台として、単独親権と共同親権のどちらが▽子の利益になるのか▽子の世話を円滑に行えるのか▽子や父母の安全を害する恐れがないのかーなどを考慮した上で、裁判所が判断するという制度案を初めて示した。同制度案が採用されれば、父母のどちらかが反対しても、共同親権が適用される可能性もある。
関係者によると、この制度案について、民法の専門家らを中心に「父母が合意できるかどうかよりも、子の利益が優先されるという考え方は自然だ」など、支持する意見が目立った。その一方、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者らへの影響を懸念する複数の委員からは「父母が合意できたケースに限り、共同親権を認めるという話ではなかったのか」「意見対立時の共同親権の強制は危うく、議論すること自体が不適切だ」などの批判が出た。
共同親権を巡っては、別居親が子育てに関わりやすくなり、子の利益になるとの意見がある一方、DVや虐待の被害が続く恐れがあるとの見方もある。部会は、今月下旬の次回会合でも今回と同じテーマを引き続き議論し、秋以降に法相に答申する改正民法の要綱案に反映させる方針。 (大野暢子)
「原則共同親権」を提言 超党派議連
出典:令和5年5月26日 時事通信
超党派でつくる「共同養育支援議員連盟」の柴山昌彦会長(自民)らは26日、斎藤健法相を法務省に訪ね、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を原則とする制度導入を求める提言を手渡した。
法相は「問題の重要性は十分認識している」と応じた。
民法は、離婚後は父母どちらか一方が親権を持つ「単独親権」を規定する。提言は「子の養育環境に悪影響を及ぼしているケースが相当数に上る」と主張し、「原則共同親権」導入のための早期の法案提出を求めた。
記憶の中では”怖い父親”、久しぶりに会ったら違った 離婚後の面会交流「子が選択を」
出典:令和5年5月16日 読売新聞
記憶の中では”怖い父親”、久しぶりに会ったら違った 離婚後の面会交流「子が選択を」
「怖い父親」イメージ変わった
久しぶりに会った父親は、昔の印象と違って見えた。記憶の中では「怖い父親」。けれど、「性格が丸くなっていた。イメージが変わった」と大阪府の中学3年の男子生徒(15)は話す。
小学5年の時に両親が離婚。中学入学後に不登校になり、家での言動が荒れた。母親(39)は迷いながら、離婚後に初めて父親に助けを求めた。
「頭を冷やしに行こう」。父親は男子生徒をドライブに誘い、その後も何度か車で海辺などを走った。次第に進路の相談をするようになり、高校のオープンスクールも一緒に行った。
「将来に色んな選択肢があることを教えてくれた。男同士なんで、話しやすい」と男子生徒。母親は「最初はすごく緊張していたけど、少しずつ2人にしかわからない信頼関係ができたのでは。どうしたって父親は1人しかいない。印象が悪いままではなく、関係性をまた築けたのは良かったのかな」と語る。
◎
日本では親の離婚後、多くの子どもが母親と暮らし、父親との関係は希薄になる。
関わり合いたくない 26%
厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査(2021年度)によると、母子世帯の45%は面会交流を行ったことがなかった。66%は取り決めもなく、その理由は「相手と関わり合いたくない」(26%)が最多。「なくても交流できる」(16%)、「相手が希望しない」(12%)が続いた。
NPO法人「ハッピーシェアリング」(大阪)では、面会交流支援のほか、親同士が直接やりとりしなくても面会日を調整できるオンラインシステムを提供する。代表理事の築城由佳さん(45)は「夫婦の関係は終わっても、親としての責任は続く」と力を込める。
自身は10年前、長女が1歳の時に離婚。調停中から面会交流を行っていたが、当初は「なぜ会わせないといけないのか」と否定的で、娘も「行きたくない」と話していた。けれど数年たち、元夫を責める気持ちを手放した頃から、長女が「パパと遊んで楽しかった」と口にするように。娘に我慢をさせていたことに気がついたという。
「自分のルーツを知ることは、子どもの成長や人生の選択に大きく影響する。親の感情で関係を切らないようにしてほしい」と語る。
◎
ひとり親へ食材支援を行うNPO法人「ハッピーマム」(大阪)代表理事の玉城ゆかりさん(48)は小学4年の時、両親が離婚。大好きだった父親の話はタブーになり、一切連絡を取れなくなった。
重要なのは子どもの気持ち
「見捨てられた」。深いショックが刻まれ、どこか自信を持てないまま思春期を過ごした。「両親に恨みつらみがあったり、愛されたいと思ったり。毎日感情が違い、気持ちが安定しなかった」と振り返る。
20歳の時、母親から預金通帳と手紙の束を渡された。「もう中学生ですね」「お母さんの言うことをよく聞いて」……。手紙には優しい言葉が並び、通帳は毎月一日も遅れず養育費が振り込まれていた。「私のこと忘れてなかったんや」。胸に詰まった10年分の苦しさが流れ出るようだった。
離れて暮らす親の愛情が自己肯定感にいかに重要か痛感する一方、支援する母子家庭の多くはDVに苦しんだ経験を持つ。子どもを元夫に会わせることを恐れる母親の心理もわかるだけに複雑だ。
「ただ重要なのは子どもの気持ち。親と会うかを決める選択権を、子ども自身が持っていることが大切なんだと思います」
〈面会交流〉
離れて暮らす親と子どもが遊んだり、手紙や電話で連絡を取ったりすること。2012年施行の改正民法で、離婚時に定める事項として明文化された。
(年齢などは2023年2月の新聞掲載当時の情報)
※この記事は読売新聞が制作し、Yahoo!ニュースが企画したテーマに参加したものになります。
離婚後の親権 子供への責任を果たす制度に
出典:令和5年5月12日 読売新聞
離婚した夫婦の対立が深まり、そのしわ寄せが子供に及ぶケースが少なくない。子供の生活をいかに守るか、国は議論を尽くしてほしい。
子供の親権について、法制審議会の部会が、離婚後に両親の双方が親権を持つ「共同親権」を導入する方向で検討することを決めた。今後、具体的な制度設計を議論していくという。
離婚は年20万件近くに上り、未成年の子供がいる夫婦は6割を占めている。現行の民法は、離婚した夫婦のどちらかが親権を持つ「単独親権」を規定している。このため、親権のない親が子育てに関われないという批判がある。
親権は、未成年の子供の世話や教育、財産管理に関する親の権利であり、義務でもある。夫婦関係を終えても、双方が子育てに責任を持つのが本来の姿だろう。
海外では共同親権が主流だ。日本人と国際結婚した外国人が婚姻の破綻に伴い、子供を連れ去られたと訴える事態が問題視されており、単独親権に対する海外からの風当たりも強い。
共同親権の導入により、離婚した夫婦がともに子育てに関与する機運が高まることを期待したい。子供にとっても、両親と接点を持ち続け、愛情を感じながら成長できる意義は大きいはずだ。
ただ、検討すべき課題は多い。両親が離婚した子供の大半は、母親と暮らしているが、母子家庭の6割は父親から養育費を受け取ったことがないという。離れて暮らす親と子供が会う「面会交流」も、十分に実施されていない。
共同親権が導入されても、現実には子供は両親のどちらかと暮らすことになる。子育てについて、離婚時によく話し合っておかなければならない点は変わらない。
日本では、当事者同士の話し合いによる協議離婚が大半を占め、裁判所などの第三者が関わらないケースが多い。養育費や面会交流に関する事前の取り決めが十分に行われているとは言い難い。
海外には、離婚の際、養育費や面会交流の内容を書面にまとめ、社会福祉事務所の認可を得る制度を設けている国もある。こうした事例も参考にしてほしい。
家庭内暴力(DV)や子供への虐待が離婚の原因になる場合がある。加害者には親権を認めないなど、柔軟な運用が必要になる。
夫婦関係がこじれると、離婚した相手に養育費を渡したくないといった気持ちになりやすい。養育費や面会交流は、子供のためにあることを改めて周知したい。
共同親権問題“裏バトル”、国の養育費受け取り「28→40%」は高いか低いか
出典:令和5年5月11日 SAKISIRU
共同親権問題“裏バトル”、国の養育費受け取り「28→40%」は高いか低いか
マスコミが報じない「抜本改革」求める声
''こども家庭庁が所管業務として力を入れる養育費の支払い確保策が、自民党や法務省で議論している共同親権導入の成り行きによって微妙な影響を受けつつある。
政府は4月に養育費の受け取り率(受領率)を、現状の28%から2031年までに40%に引き上げる目標を掲げたが、現行の単独親権制度では限界が多く、欧米と同じく共同親権に移行し、不払いには罰則などを徹底化する「抜本改革」を求める声が上がっている。''
維新・梅村氏「限りなく100%を」
日本の養育費不払いは先進国の中でも特に低いとされる。背景には日本では協議離婚が可能で、養育費の支払い取り決めが法的に義務化されていないことや、不払いの別居親に対する罰則や強制執行が十分に機能していないことが挙げられている。兵庫県明石市が養育費の取り決め支援や不払い時には市が立て替えるなど独自の対策を行った事例が注目されたが、国全体としては養育費の受領率が3割に満たない。
海外では、強制執行制度が整備されたアメリカは受領率が6割程度。スウェーデンは未払いが起きた場合に国が一時的に立て替え、不払いの親から強制で徴収しており、実質的に未払いが起きないようにするなど、公的な制度が充実している。韓国はかつて受領率が日本を下回る惨状だったというが、養育費履行管理院を2015年に創設し、一時立て替えや罰則を強化。悪質な不払い親には収監や運転免許停止も可能にしており、2020年の受領率が36%に達した。
この問題について維新の梅村みずほ参院議員が9日の参院法務委で質問。政府が目標とする養育費受領率40%について「あまりにも低い数値だ。裏を返せば60%の子どもたちが(養育費を)受領できなくてもいいと受け取られかねない」と厳しく指摘した上で「限りなく100%を目指すべきだと思っている。見直しが必要ではないか」とただした。
梅村氏の質問に対し、こども家庭庁を担当する内閣府の自見英子政務官は目標値について「養育費の取り組みをしている場合の受領率を70%、養育費の取り決めの有無にかかわらない全体の受領率を40%と掲げたところだ」と改めて説明。「こども家庭庁としても重大な問題だと認識している」と歩み寄りを見せつつ、弁護士などによる相談支援や、保証会社における保証料の補助などの養育費の履行を確保する自治体のモデル事業を支援していることなどを挙げた。
「単独親権が大前提では」
梅村氏が「限りなく100%」と強気な背景には、親権制度の見直しがある。日本が継続している単独親権では親子断絶が起きた場合、支援や罰則などの制度面の不十分さも加わって受領率が低迷しやすい構造になっている。これに対し、欧米はDVなどの問題がある場合を除き、共同親権が原則だ。別居親との親子関係が安定的に継続できることで養育費の支払いを後押ししやすいとの見方がある。
共同親権の適用に反対するひとり親の支援団体の中には「養育費と親子の交流は切り分けて論じるべきだ」と反発する声もあるが、共同親権導入を推進する団体の関係者は「親子関係を継続し、養育費支払いを制度的に義務づけることで、受領率100%とは言わないまでも政府目標よりはるかに高い数値は実現できる」と強調する。
梅村氏もこども家庭庁の取り組みについて「単独親権制度が大前提になっているのでは」と核心を指摘。法務省の議論を見ながら対応している同庁の対応についても「子どものために親権制度がどういうものが理想なのか、 縦割りの弊害をぶち壊して子どもの味方に立つのがこども家庭庁の役割だ」との持論をぶつけた。
これに対し、自見政務官は「一般論としては父と母の離婚後も適切な形で親子交流が 実施されることは、子どもの権利の観点から非常に重要」と述べるにとどめた。
議論が行われている背景について、霞が関の関係者は「共同親権反対派が最近、旗色が悪くなり、法務省への働きかけからこども家庭庁へのアプローチに軸足を移し始めているとの情報が出ている。養育費支援に関与することで補助金や助成金を意識しているのではないか」と指摘する。
マスコミではこのあたりの実相は全く報じられていないが、法務省法制審家族法制部会のパブリックコメントに共同親権の賛成・反対含めて約8000件もの意見が提出されたとされる裏で、こども家庭庁が“新たな主戦場”になろうとしている。
《秋田・小4女児を母親が絞殺》霊安室で7年ぶりに会った娘は冷たく…「救える機会は何度もあった」8000万円の損害賠償を請求した実父が憤る行政の“ずさんな対応”
出典:令和5年5月10日 週刊女性PRIME
《秋田・小4女児を母親が絞殺》霊安室で7年ぶりに会った娘は冷たく…「救える機会は何度もあった」8000万円の損害賠償を請求した実父が憤る行政の“ずさんな対応”
母親は児童養護施設で生活する娘を迎えに訪れた。駆け寄る娘をギュッと抱きしめていたその手は、我が子を絞め殺すために使われた――。
「娘の顔は赤紫色で、口を大きく開けていました。何かを叫んで、何かを訴えているような表情に見えました。柔らかい紐のようなもので、十数分にわたって首を絞めて殺害されたそうです。それだけ長い時間をかけたのに、どうして我に返らなかったのか」
「統合失調症」と診断された母親
そう話すのは、亡くなった千葉愛実(めぐみ、享年9)さんの実父である阿部康祐(やすまさ、50)さんだ。
事件は2016年6月、秋田県秋田市で起こった。愛実さんの母親であるY子は、自宅アパートで無理心中を図り、施設から一時帰宅中だった娘の首を絞めて殺害したのだ。
Y子は殺人容疑で逮捕されたが、秋田地裁は心神耗弱を認定し懲役4年の実刑判決を下した。しかし、Y子は判決を不服として控訴。最高裁まで争ったが、2018年に刑が確定した。
「たったの4年……軽すぎますよ。裁判では“覚えてない”“わからない”ばかりで謝罪の言葉はありませんでした。 Y子の服役後には、刑務所での様子を通知してもらう制度を利用しましたが、生活態度はいつも5段階中の最低評価。説明には《反抗的》などと書かれていました。他責的な人間ですから、反省していないはずです。すでに出所をしていますが、Y子に会ったら、取り返しのつかないことをしてしまいそうで……。今も彼女を許せないんです」(阿部さん、以下同)
その心中に渦巻くのは、Y子への怒りだけではない。2019年、行政の対応に落ち度があったため愛実さんが殺害されたとして、阿部さんは秋田県などを相手取り、約8000万円の損害賠償を求める裁判を提訴した。
「行政がしっかりと連携していれば、救えた命だったはずです。それなのに行政間で情報共有がなされず、対応を誤った。Y子は生活保護を受給していましたが、ケースワーカーは、Y子に娘がいることを知らなかったそうです。ありえないことが、いくつも起こっていたんです」
しかし、秋田地裁は4月14日に阿部さんの請求を退ける判決を下した。これを受け、阿部さんは即日控訴している。本当に行政の対応に問題はなかったのか。一家に何が起こったのか。時を遡る。
◆ ◆ ◆
2002年、6年間の交際を経て阿部さんとY子は入籍。秋田県大仙市に居を構えた。幸せな新婚生活が待っているはずだった……。
「結婚してほどなくしてY子が“私は何かしらの精神疾患を患っている”と訴え、いくつもの精神病院を受診して回るようになりました。最終的に『統合失調症』と診断され、Y子も納得した様子でした」
次第に病状は悪化。妄想が酷くなり、薬を大量服薬する自殺未遂を起こしたことも。そんなY子に代わり、阿部さんはすべての家事をこなした。
「Y子は思うように動けず寝てばかりでした。親族との関係も悪く、孤独だったんです。そんな妻を私が支えなくてはいけないと思っていました」
ここで生活に大きな変化が起こる。2006年12月に愛実さんが誕生するのだ。
住民基本台帳に閲覧制限が
「すっごく嬉しかったのを覚えています。初めて抱いたときは、壊れてしまいそうなぐらい小さくて怖かったのですが、本当に可愛くって……。父親になったという自覚が沸き、もっと頑張らなくてはいけないと強く思いました」
Y子にも変化はあったのか。
「可愛がっていましたが、正確には教育熱心だったという印象です。“幼い時の教育が大人になって影響するんだから”と話し、食べさせる物へのこだわりは強く、知育玩具を買い与えていました。勉強って歳でもないんですが……。Y子は学生時代に“いじめ”に遭っていたことから、娘をいい学校へ進学させて周囲を見返してやりたいという思いがあったようです。子どもは自分の分身ではないのに……」
その一方で、阿部さんの負担は増大していた。
「Y子が病気で昼間は子どもの世話をできないため、保育園に預けていたのですが、その送迎やお風呂といった育児に加えて食事の支度など、家事育児のほぼすべてを私が担っていたんです。愛実の世話について、Y子は口頭で私に指示をするだけ。私の母にも助けてもらいましたが、少しでもY子の思った通りでない育児をすると、すごい剣幕で罵倒されるのです。腫物に触るように接していました」
父親として家族を支えなければいけない。そんな思いだけが阿部さんを突き動かしていた。しかし、心が壊れる。
「仕事から帰っても家事育児で休まる時間がなく、限界がきていました。当時は配達の仕事をしていたのですが、あるときから配達先を1軒回ると気分が悪くなり、休憩しないと動けなくなって……。1日30軒回っていたのが、3軒回るのがやっとでした。そんな状態でしたから、仕事をクビになってしまいました」
それが2008年9月末のこと。ほどなくしてY子の病状が悪化したなどの理由から、夫婦は別居し、2009年8月には調停離婚が成立。親権はY子が持つことになる。
「絶対に愛実を渡したくなかったのですが、親権争いは母親が優位ですから勝ち取ることは難しかった。私が納得しないでいるとY子が面会交流をさせると言ってきたんです。月に1回会えるなら愛実の様子もわかるし、問題があれば即座に親権変更ができると考え、私は渋々承知したんです。まさか完全に会えなくなるとは思いもしませんでした」
Y子はさまざまな理由をつけ面会交流を拒絶する。
「家族で住んでいた家からY子が転居したため、どこに行ったのかわからなくなってしまいました。愛実に会う方法を必死に模索するなか、住民票を取得しようとしたら、住民基本台帳に閲覧制限がかけられていたんです」
2009年11月、Y子は元夫からストーカー被害を受けていると虚偽の訴えをして『DV等支援措置』を申請していた。同制度は、DVや児童虐待の加害者から被害者の情報を保護してもらうよう自治体に求めることができるもの。
「1度も実施されない面会交流の履行勧告をしようにも、Y子の住所が必要でした。携帯番号も変えられて、連絡をとる方法がなくなるのです」
7年ぶりに会った娘は、冷たかった
その一方で、Y子は離婚後に大仙市内の県営住宅に転居。2011年3月には行政に愛実さんの養育が困難だと訴え、愛実さんの一時保護を求めた。これにより愛実さんは児童養護施設で生活することになる。
「そんな状況になっているとはつゆ知らず、Y子の父親に何度も頭を下げて、引っ越し先を教えてもらいました。2012年4月にはその住所を基に面会交流の履行勧告をするのですが、 Y子は私を愛実から遠ざけるため、今度は警察に虚偽のストーカー被害を訴えたのです。私を苦しめるため、何が何でも愛実と会わせたくなかったんでしょう」
誰もがY子の主張を鵜呑みにし、阿部さんを阻み続ける。
「警察から“ストーカー行為はやめなさい。繰り返したら逮捕します”と電話がありました。それでも安否確認だけはしたくて県営住宅に何度も足を運んでいたんです。しかし、娘の姿を見ることはできず、諦めの気持ちが大きくなっていきました」
阿部さんから少しでも離れようと考えたのか2013年2月、Y子は秋田市内へと転居する。周囲が見えなくなるぐらい、阿部さんの頭の中は愛実さんのことでいっぱいだった。
「複数の探偵社に“娘を探してほしい”と依頼しましたが、全部断られます。手立てのない絶望的な状況にふさぎ込む日々が続きました。そんなとき、私の母親が“大人になったら愛実から会いに来るよ”と言ってくれたんです。もし愛実が会いに来たとき、こんな姿は見せられない。立派なお父さんでよかったと思ってもらえるように頑張ろうと、それを日々の糧にして前向きに生きることを決めました」
だが、希望は無残にも打ち砕かれる。新聞報道で事件を知り、警察署に駆け付けた。霊安室で7年ぶりに会った娘は、何も話さず、冷たかった。
「娘の遺体を目のあたりにしても、自分の娘だと思えなかった。成長していたからではありません。悲しいという感情が沸いてこず、現実を受け止めることができなかったんです。愛実の葬儀は、Y子の親族が執り行いました。参列したいと伝えると“やっと縁が切れるんだから遠慮してくれ”と言われ、最後の別れをすることは叶いませんでした」
阿部さんは、愛実さんが通っていた学校や児童養護施設から引き取った遺品すべてに、今も目を通せないでいる。
「楽しそうな娘の姿を知ると、つらくなってしまうんです。なんで助けてあげられなかったんだろう。本当はそんな楽しい日々がずっと続いていたはずなのにって……」
そして、行政の対応について怒りを滲ませる。
「Y子が秋田市へ転居した際、愛実は施設で保護されており安全だとして、秋田市は大仙市から要請のあった情報の引き継ぎを拒否したんです。注意深く見守る必要がある要保護児童の対象からも除外しました。最終的に愛実と関わっていたのは児童養護施設だけでしたし、Y子と接していたのはケースワーカーだけでした。愛実を一時帰宅させるなら、母子両方の状況を複数人で注意深く見守るべきなのに……」
生前の娘と最後に会った時の思い出
母子への手厚い支援が失われていた。Y子は当時『統合失調症』(※編集部注:刑事裁判では『妄想性障害』と認定)と診断されており、主治医も「母親の病気は重く、子の養育は無理である」と述べていた。
今回の判決で秋田地裁は、一時帰宅中にネグレクトや暴力による虐待はあったと認定。にもかかわらず、母子の関係は良好で、愛実さんに重大な危害が加えられることは予測できなかったと判断した。
「死なない程度であれば、虐待しても問題ないと言っているようにしか聞こえない。危険な判決だと思います」
愛実さんを一時帰宅させる判断も、大仙市から秋田市へ転居してから変化していた。転居前は家庭訪問や医師との面談によりY子の生活状況や病状の把握に努め、児相が会議で帰宅の可否を決定していた。しかし、秋田市に転居してからY子の情報が把握されないまま、児童養護施設にその判断が一任されていたのだ。
「児童養護施設への帰宅時間も毎回遅れていたのに、それを容認していたのもおかしい。事件発生時、行政が即座に警察へ通報して自宅内の状況を確認していれば、愛実は助かっていたかもしれないんです。DV法の運用も、被害者の意見を聞くだけでなく、申請後に事実の確認が行われるべきでしょう。愛実の命を救える機会は何度もあったはずです」
行政の不備を痛烈に批判するが、裁判を提起したのには、こんな思いがあったと続ける。
「間違いがあったと純粋に謝罪をしてほしいだけなんです。私に対して“金が欲しいんだろう”と話す人もいますけど、お金が目的ではありません。2度と同じことが起こらないように、真摯に反省する誠意を見せてほしいだけなんです」
ここ数年で、阿部さんの両親や祖母が他界した。今は実家にひとりで暮らす。
「広い家なので、寂しいですね。死んでしまいたいと思うこともありますが、私が生まれてきた意味は今回の問題を伝えることなのだと思っています。生前の愛実に会えたのは、離婚直前の2009年3月22日でした。2歳の娘は“おとーしゃん、あそぼー”と駆け寄ってきたので、たくさん“高い高い”をしたんです。喜んでくれて、嬉しかった。遊び疲れて寝てしまった愛実の姿が、今も忘れられません」
そう話し、かつて娘を抱き上げたその両手を、阿部さんはじっと見つめた――。
【共同親権問題】「連れ去られた初孫は、2年間小学校に行かせてもらえなかった」それでも家庭裁判所が夫婦に下した判断とは
出典:令和5年4月24日 デイリー新潮
【共同親権問題】「連れ去られた初孫は、2年間小学校に行かせてもらえなかった」それでも家庭裁判所が夫婦に下した判断とは
現在、国会で「共同親権」を導入すべきか、大詰めの議論が行われている。そもそも、「共同親権」とは、子どもの親権を、父親と母親の双方が共同で行使しなければならないことをいう。父親または母親のいずれか一方のみが親権を行使しているように見える場合であっても、他方の親がそれに同意し、許容していることが必要である。一方、現在の日本では、もし両親が離婚した場合、親権はどちらか一方にしか認めないという「単独親権制」が導入されている。
どれだけ理不尽であっても
こうした法体制を背景に現在頻繁に起きているのが、「連れ去り事件」だ。これは、子供がいる夫婦間でトラブルが起きたり、特にトラブルが生じたわけではなくとも離婚を考えていたりする際、どちらかが、相手に無断で子供を連れ去った上で別居するというもの。無論、どちらかの親からの暴力や虐待から子供を守るためというケースもあるが、その場合であっても、法的な保護手続によらなければならないにもかかわらず(当然のことながら、一方的な主張で決まるわけではなく、相手方にも反論の機会が与えられる必要がある)、一方的に子供を連れ去ることで解決しようとするケースが多い。既成事実化された事実状態を追認するだけの判断を行う傾向が非常に強い裁判実務を悪用し、離婚裁判を有利に進めるために行われる場合も少なくないという。子供を連れ去られ、子供との関係を断絶され、それが既成事実化されてしまい、実の子に会う機会を奪われたもう一方の親は、我が子会いたさに、どれだけ理不尽であったとしても、相手の要求を飲まざるを得なくなってしまうというケースが後を絶たない。
公立の学校に
いわば“駆け引き”の材料として片方の親に引き取られた子供たちの中には、あろうことか、満足に教育を受けさせてもらえないという事態となっていたり、満足に食事も取れない状態(いわゆる「子供の貧困」と呼ばれる状態だ)に陥っていたりするなどの問題も起きている。3年前のある日、母親と共に姿を消した真央ちゃん(仮名)もその一人。真央ちゃんの誕生から側で見守り続け、育児にも積極的に協力してきた父方の祖父が、その状況を語る――(議論沸騰【共同親権問題】“私の初孫はある日突然姿を消した”も合わせてお読みください)。
※この記事は取材を元に構成しておりますが、個人のプライバシーに配慮し、一部内容を変更しております。あらかじめご了承ください。
***
私の初孫の真央ちゃんは、いわゆるお受験を経て、都内にある私立の小学校に通っていたのですが、小学1年生の秋に息子の妻である綾子さん(仮名)に連れ去られて以降、通学していないことがわかりました。学校から私の息子に問い合わせがあり、それが発覚したのです。さらに、弁護士を通じて、相手方に確認を取ったところ、「公立の小学校に転校した」という驚きの答えが返ってきました。
とんでもない事実が
私立の小学校には、息子がずっと学費を払い続けていましたし、念の為学校にも確認したところ、「転校の事実はない。学籍はこちらにある」とのことでした。加えて、「そもそも転校の手続きは、ご両親の承諾がなければできない」とも言っていただいた。うちの息子は、当然ながら転校を望んでいませんから、真央ちゃんの学籍はずっと、私立の方にあるのです。
となると、真央ちゃんは今、どこに通っているのか、そして「転校」とは、一体何を指しているのか。改めて調査を進めると、とんでもない事実が明らかになったのです。
というのも、真央ちゃんは、ある都内の公立の小学校に通っている、ということになっていた。ただし、先ほどもお話した通り、学籍は私立の方にあるわけですから、正式な転校ではありません。そのため出席番号もないし、通知表もない。あくまで見学、オブザーバーとしての参加、体験学習だということだったのです。しかもその後、綾子さんは、真央ちゃんを、その“仮の通学”にすら行かせていないことまでわかったのです。
高いハードル
真央ちゃんを学校に通わせていない――。これは明らかな虐待行為に他なりません。一刻も早く、この問題を解決しなければならない。そのためには、真央ちゃんを取り戻すしかない。とはいえ、現行法の下では、力ずくで真央ちゃんを取り返そうとすると、「連れ去り」については不問に付すのに、「連れ戻し」については誘拐罪に問われる可能性が高い。そこで、何か方法がないか、弁護士さんに相談すると、家庭裁判所に、「監護者」指定の申し立てをするという手があるということを教わりました。
監護者とは、いわゆる「親権」の中に含まれる、「監護権」、平たく言えば、子供の衣食住や教育環境を確保したり、子供の身の回りの世話をしたりする権利を有する者のことです。別居中でも、家庭裁判所から監護者指定をもらえれば、真央ちゃんを取り戻すことができるですが、当然ながら、ハードルは高い。親権同様、圧倒的に母親の方が監護者として選ばれやすく、さらに、既成事実を追認するだけの裁判実務がまかり通っている現状では、子供と現在同居しているとなれば、家裁はますます、母親を指定してくる可能性は高い。
調査官の質問
しかし、母親が、義務教育期間の子供を学校に通わせていなかったとしたら、話は違います。監護者としての義務を果たせていないわけですから。弁護士さんもそこに一縷の可能性を見出して、家庭裁判所への申し立てを決めたのです。
申し立てをしてから、数ヶ月後のことでした。私の息子は調査官に呼び出され、家庭裁判所に向かいました。そこで3時間、別居前のことを根掘り葉掘り聞かれたそうです。特に、親子関係についてはしつこく聞かれたそう。ときには、「真央ちゃんを怒ったことはあるか」「そのとき真央ちゃんはどんな表情をしていたか」などと、息子と孫の関係性に溝があったと決めてかかっているような質問もあったそうです。
さらに、家裁の調査官は、真央ちゃんの祖父母である、私どもの自宅にも来ました。そこでも同じように、別居前の様子について聞かれ、私たちはありのままを話しました。息子も、私たちも、真央ちゃんの育児をしっかりやっていたこと、息子の妻である綾子さんは、一人の時間を大切にしていたこともあり、そういう時には、息子が真央ちゃんを外に連れ出し、一緒に遊んでいたこと。祖父母としても、できる限り、真央ちゃんのお世話をしていたこと。母親側が主張しているような、虐待やネグレクトなどはなかったこと。やはり3時間ほど、全てを隠すことなくお話しました。もちろん、綾子さんや真央ちゃんにも、同じように調査官から、聞き取りをされたようです。
裁判所の存在意義
その後、調査報告書が開示されたのですが、そこでは母親側の主張だけが一方的に採用され、息子側の主張は無視されていました。連れ去った側に監護権がある、という前提のもとに作られた印象は否めない。ある程度予想はしていましたが、やはり、目の当たりにすると、ショックは大きかったですね。
ただ、報告書の中で希望があったのは、孫は、「私立の小学校に通いたい」と発言していたこと。つまり、こちらの要望と、孫の意見は一致していたのです。綾子さん側の弁護士は、この孫の主張を覆すべく、裁判所に対し、孫が書いたとされる、「公立の小学校に行きたい」という文書を提出してきたのです。これには流石に裁判所も困惑していましたが、困惑するにとどまり、特に何も措置を取ろうとはしませんでした。
こうして大人が不毛なやりとりをしている間にも、真央ちゃんはずっとまともに学校に行けていないのです。それでもなぜ、監護者は母親なのでしょう。学校に行かせない親が、監護者になる、そんなおかしいことはありません。ですが、裁判所は、なんの判断も下さないどころか、「報告書でも監護者は母親と出ているし、早く和解した方がいい。このままだと子供もかわいそうだし、あなたも損をする」と、息子に言ってきたのだそうです。これには怒りを通り越して、呆れるばかりでした。裁判所の存在意義が、どこにも見出せません。こういう事態だからこそ、裁判所に判断を仰いで、問題を解決しようとしているのに……。
二度と戻らない
そのまま時が流れ、ついに今年3月に、審判の日を迎えました。結果は、調査報告書の通り、監護権は母親、というもの。もちろん、すぐに不服を申し立てました。そして真央は、度重なる主張の結果、ようやく、この4月から私立の学校に通学できているとのこと。しかし、本当であれば楽しい時間であった、真央の貴重な小学校生活の2年間は、もう二度と戻ってこないのです。明らかな虐待であるにも関わらず、それでも頑なに慣例を重視し、監護者を母親にし続けた家庭裁判所に対しては、違和感しかありません。
離婚後養育「共同親権」導入の方向 法制審部会が議論へ
出典:令和5年4月19日 産経新聞
離婚後の子育てについて検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を条件付きで導入する方向で議論を進めることが確認された。一部の委員からは導入について慎重な意見が出ており、今後、具体的な制度設計を議論する。
離婚後の親権については①原則、共同親権で例外的に単独親権②原則、単独親権で例外的に共同親権③現行の単独親権のみを維持-の3案を軸に議論されている。関係者によると、18日に開かれた部会でこれまでの議論を踏まえた「今後の議論の大きな方向」に関する資料が共有され、大半の委員の賛同を得たという。
資料では、家族によって離婚を巡る事情が多様であることを確認した上で、父母が合意し共同親権を望む家庭も想定されることから、単独親権しか認めていない現行の規定は「見直す必要がある」としている。
今後は、父母が話し合いを経て別れる「協議離婚」で双方が合意した場合、共同親権が可能になるような制度の検討を進める。共同親権を導入する際、子供と同居する親、別居する親とで、子育ての役割をどう分担して担うかなどが議論の対象になるという。
また、一部の委員からは「共同親権に関する父母の合意が、きちんと確認できない可能性がある」などと慎重な意見も出されており、合意を確認する具体的な方法などについても検討を進める見通し。
法制審、共同親権導入に向け議論 父母合意で、民法見直しも
出典:令和5年4月19日 東京新聞
離婚後の子どもの養育について検討する法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が、「共同親権」を導入する方向で議論を進める見通しになったことが18日、関係者への取材で分かった。父母双方の真摯な合意が確認できた場合、共同親権を選べるようにすることが軸。どちらか一方の「単独親権」のみとする現行民法が見直される可能性が出てきた。
関係者によると、18日の部会では「真摯な合意がある場合も、単独親権のみを維持するのは合理性がない」といった意見が多かった。一方、複数の委員が共同親権に強い反対意見を示した。
このほか、共同親権導入の方向性には理解を示しながら「慎重に検討すべきだ」と留保を示した委員も複数おり、合意がきちんと確認できるかや、ドメスティックバイオレンス(DV)があるケースで被害者を保護できるかなど詳細が決まらないと議論できないとの指摘があったという。
部会は今後、真摯な合意を確認する具体的な方策などを検討し、裁判所が関与する仕組みも視野に入れる。
共同親権、導入の方向 制度設計議論へ 法制審が確認
出典:令和5年4月19日 朝日新聞
離婚後の子どもの親権について法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、父母双方が持つ「共同親権」を導入する方向で検討することを確認した。父母のどちらか一方に限る現行の「単独親権」の維持を求める意見も根強く、具体的な制度設計をめぐっては激しい議論が予想される。
※以下、紙面を参照ください。
現在の親権制度見直し「共同親権」導入に向け具体的検討へ
出典:令和5年4月18日 NHK
親が離婚した場合の子どもの養育について、国の法制審議会の部会は、現在の制度を見直し、父と母双方を親権者とする「共同親権」を導入する方向で具体的な検討を進めることで合意しました。
国の法制審議会の部会は去年11月に中間試案をまとめ、身の回りの世話や財産管理をする権限であり義務でもある「親権」の扱いについては、親が離婚した場合、
▽父母双方を親権者とする「共同親権」を導入する案と
▽いずれか一方のみの、今の「単独親権」を維持する案が、併記されました。
そのうえで、「共同親権」を導入する場合は、
▽「共同親権」を原則とし、例外的に「単独親権」を認める案と
▽「単独親権」を原則とし、例外的に「共同親権」を認める案などが、示されました。
これについて18日に非公開で開かれた法制審議会の部会では、国民から広く募った意見や、これまでの議論を踏まえ「離婚後に単独親権しか選べない現行制度は、社会情勢の変化によって合理性を失っている」といった意見が多数となりました。
そして現在の制度を見直し、父と母双方を親権者とする「共同親権」を導入する方向で具体的な制度設計について検討を進めることで合意しました。
一方、18日の部会では、婚姻中のDVなどへの懸念から、「共同親権」の導入に慎重な意見もあったことから今後、そうした対策も議論していくことにしています。
「共同親権」導入の方向 法制審部会、制度設計を議論へ
出典:令和5年4月18日 日本経済新聞
法相の諮問機関である法制審議会は18日に開いた部会で、離婚後に父母双方に親権を認める「共同親権」の導入に向け議論を始めると合意した。2022年11月に決めた中間試案は片方だけが親権を持つ現行の「単独親権」を維持する案も併記した。検討の幅を絞り制度設計の議論に入る。
部会は非公開で開催した。関係者によると、会合では離婚時に父母双方が親権を持つことに同意した場合の対応を話し合った。複数の委員から導入に慎重な意見が出たものの、共同親権の採用を前提として今後の会合を開くことで折り合った。
現行民法は婚姻中であれば父母がともに親権を持つ「共同親権」で、離婚した場合はどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」になると規定する。
22年11月の中間試案は共同親権を採り入れる場合の制度として①原則は共同親権で一定の要件を満たせば例外として単独親権も認める②原則は単独親権で一定の要件を満たせば例外として共同親権も認める③具体的な要件を定めず個別ケースごとに単独か共同かを選択可能にする――の3案を記した。
父母で離婚時に共同親権で一致できなかった際の取り扱いなどが議論の焦点になる。父母同士の関係が残り虐待やドメスティックバイオレンス(DV)が続くとの指摘がある。
部会ではこうした懸念に配慮しつつ、どういった場合に共同親権を認めるかを具体的に検討する段階に移る。結果を法相に答申する時期はメドが立っていない。
▼共同親権 離婚後も父母の双方に親権を認める制度。現行の民法は「単独親権」を規定し、どちらか片方のみが親権を持つことになっている。海外の主要国は共同親権が一般的で、米国や英国、オーストラリアなどが導入している。イタリアやフランスは共同親権を原則としつつ、虐待リスクなど子どもの利益に反すると裁判所が判断すれば単独親権を認める。
「共同親権」の導入で法制審部会が合意…離婚の協議で父母双方が同意なら
出典:令和5年4月18日 読売新聞
「共同親権」の導入で法制審部会が合意…離婚の協議で父母双方が同意なら
離婚後の親権のあり方などを議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を前提に議論を進めることで合意した。
関係者によると、この日の会合では、離婚の協議を行う際に父母双方が共同で子の親権を持つことに合意した場合には、共同親権を認める方針を確認したという。原則で共同親権とするかどうかや具体的な制度設計は今後さらに議論を行う。
現行民法は、婚姻中は父母が共同で親権を持つが、離婚後は片方が親権を持つ「単独親権」を規定している。「単独親権」は離婚時の親権争いや、子どもの連れ去りなどのトラブルの原因とも指摘されている。
部会では、昨年11月に共同親権を導入するか、現行の単独親権を維持するかについて、両案を併記した中間試案を公表していた。
離婚後の「共同親権」導入に向け議論で合意 法制審部会
出典:令和5年4月18日 毎日新聞
家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、離婚した父母の双方が親権を持つ「離婚後の共同親権」の導入を前提に今後の議論を進めていくことで合意した。部会は2022年11月に中間試案をまとめ、離婚後は単独親権のみとしている現行制度を維持する案を併記していたが、議論の方向性を絞った。
部会は非公開。関係者によると、共同親権の導入に消極的な声も上がったが「離婚後に単独親権しか選べない現行制度は社会情勢の変化によって合理性を失っている」などとする意見が多数を占めた。ただ、賛成の立場からも「慎重に議論を進めるべきだ」との意見が示されたという。
婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権とする制度は1947年の民法改正で採用された。婚姻中は父母が協力して親権を行使できるが、離婚後は通常、父母が別々に暮らすため、共同親権の行使は難しいとする考えがあったとされる。
しかし、この法改正から70年以上が経過し、家族のあり方は多様化した。女性の社会進出が進み、育児に関心を持つ男性も増加している。結婚しても3組に1組が離婚する現状があり、離婚後も子の養育に関わりたいと願う別居親の存在が顕在化。離婚後の単独親権が、父母による親権争いや片方の親の同意のない「子の連れ去り」を誘発しているとの見方もある。国際的にも離婚後の共同親権が主流だ。
法務省は22年12月~23年2月、離婚後の共同親権の是非について国民に意見を公募した。その結果、離婚によって協力関係が失われた父母による共同親権では子に関する取り決めがしにくくなり、婚姻中のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を引きずることになるとする懸念も寄せられた。
しかし、全ての離婚家庭でDVや虐待があるわけではなく、少なくとも協力関係が良好で双方が離婚後の共同親権を望む父母については離婚後の共同親権が「子の最善の利益」にかなうといった意見が多くあったという。
部会の今後の議論は、具体的な制度設計に焦点を移す。離婚後の共同親権が導入されれば、父母が離婚時に共同親権か単独親権かを選択する仕組みが想定されるが、意見の対立があった場合の親権者の決め方が問題となる。また、離婚で別居すると婚姻中と同じように共同で親権を行使することが事実上難しくなるため、子に関するいかなる決定を共同親権の対象とするのかも課題となる。【山本将克】
親権
親権は、未成年の子に対して親が持つ権利と義務を指し、子の身の回りの世話をする「身上監護」と、子の財産を管理し子に代わって法律行為をする「財産管理・法定代理」からなる。民法は818条で「成年に達しない子は、父母の親権に服する」として婚姻中の共同親権を定める。一方、819条で「父母が離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない」として離婚後の単独親権を規定している。
子供連れ去り 「法の不備」波紋
出典:令和5年3月26日 産経新聞
夫婦の一方が相手の同意を得ずに子供と家を出る「連れ去り」を防ぐ法規制がないのは、国として許されるのか-。子供と離れて暮らす親らがこう訴えた訴訟で東京地裁は1月、国に対する賠償請求は退ける一方、法規制が存在しないとして法の不備を認める初の司法判断を示した。ドメスティックバイオレンス(DV)被害者が子供を連れ出すなどやむをえない例もあるが、国際機関からは法整備の勧告も相次いでおり、別居中の子育てのルールを巡る議論にも一石を投じそうだ。
ミラー越しの面会
訴訟で原告となったのは、配偶者から同意なく子供を連れ去られたとする男女14人。刑事・民事ともにこうした事態を抑止する法律が存在せず、国が法整備を長期間怠っていると主張。違法性を追及できないため、子供の養育を巡って不利な立場に置かれているなどと訴えた。
※以下、紙面を参照ください。
日本に「共同親権」導入促す 子供連れ去り多発で―豪政府
出典:令和5年3月22日 時事通信
【シドニー時事】オーストラリア政府は22日までに、離婚後に父母どちらか一方の単独親権しか認めていない日本の民法の見直しに関し、父母双方が親権を持てるようにする「共同親権」制度の導入を促す意見書を日本法務省に提出した。日豪間で、片方の親が子供を無断で連れ帰る「連れ去り」が多発している現状を踏まえ、親子の面会・交流が容易になるよう法改正を要望した。
豪紙シドニー・モーニング・ヘラルドの調べによると、2004年以降、婚姻が破綻した日豪カップルの一方が連れ去った子供は少なくとも82人に上る。日本は14年に、子供をいったん元の居住国に戻して親権問題を解決することを定めたハーグ条約に加盟したが、日本の単独親権が障壁となり、連れ去られた子供との一時的な面会すらかなわない豪州人の親も多いという。
日本法務省は昨年12月から、離婚後の親権の在り方を巡り意見公募(パブリックコメント)を実施しており、豪政府はこれに対応した。ウォン外相は豪メディアに「当該家族の苦痛は計り知れないと理解している。子供が両親と有意義な関係を保つための解決策を日本が見つけることを促したい」と強調した。
一方、在豪日本大使館は「子の連れ去り事案については、子の利益の観点から法にのっとって適切に対応していると認識している」とコメントした。
※ 3月19日に報道された豪紙シドニー・モーニング・ヘラルドの記事はこちらを参照ください。
共同親権「政争の具にするのは大変悲しい」嘉田参院議員が予算委で訴え
出典:令和5年3月18日 SAKISIRU
共同親権「政争の具にするのは大変悲しい」嘉田参院議員が予算委で訴え
報道されない質疑「DV被害者保護と離婚後共同親権制は両立」
''共同親権導入を巡り、統一地方選を前に政治的に混迷している。法務省側の家族法制見直し中間試案については、昨年12月から2か月間に渡ってパブリックコメントを実施し異例の注目を集めたものの、大手メディアで実相が伝えられることは相変わらず少ないままだ。
2月下旬には東京新聞が法務省の民法改正案の提出見送りと報道するも、関係者が直後に同省に確認した結果として「決まっていない」と否定したことがSNS上で暴露されるなど“情報戦”の様相も濃くなっている。''
そうした中、マスコミでは報じられていないが、無所属の嘉田由紀子参院議員が15日の予算委員会で「政府の動きは大変に遅い」と指摘し、選挙を前に懸案先送りの観測ムードを牽制する一幕があった。
嘉田氏はG7で日本だけが単独親権を残している事実を指摘した上で、共同親権反対派が、母親へのDVが続くリスクを懸念していることについて「解決策はある」と主張。
「離婚時、子どもの生活教育、あるいは精神の安定などを守るために、共同養育計画合意書を作り、公正証書化して法的権限を持たせる」
「弁護士などが仲介をして、いわばADR裁判外紛争解決手続きを活用することで、共同養育計画を作ることができる」などの方向性を提言した。
また、共同親権反対派の有識者や同調する一部メディアから「共同親権を導入した国の中には、単独親権に戻す動きがある」などと言説が流されているが、嘉田氏は「離婚後共同親権制を採用している国でも、DVは当然存在している。DV被害が守られないとの理由で単独親権制度に戻そうという国はあるのか?」とただしたのに対し、法務省は金子修民事局長が同省の調査内容を答弁。
「DV被害者が守られないとの理由によるかどうかとわからない」との留保をつけたものの、「離婚後共同親権制度から離婚後単独親権制度への法改正をした国があるということは承知していない」と言明した。さらに離婚後共同親権制を採用している国でのDV事案の対応について「フランスでは家庭内暴力や虐待がある場合は、裁判所が父母の一方の親権を取り替え上げることができるような仕組みがある」などの具体例に言及した。
パブリックコメントは賛成・反対派を問わず、多数の反響があったが、東京新聞が法務省の法案提出見送りをフライングで報道して物議を醸すなど、統一地方選を前に「先送り」したい政治的意向がにじみ始めている。
嘉田氏はこうした動きを牽制。現行民法の834条でもDV事案の親権剥奪の条項があることから、「 DV被害者を保護しながら離婚後共同親権制を実現する民法改正法案は今すぐにでも国会に提出できる状態」との認識を示した上で、「政府の動きは大変に遅い」と指摘した。
そして永田町や霞が関で「共同親権制度に賛成すると、DV被害者に冷たいと批判され『選挙に不利になるから』との声がえる」と紹介した上で、4年前に自身が出馬した参院選でも「離婚後共同親権を選挙公約に入れたことで、ネット上で落選運動をされた」と述懐。
「落選運動をされる辛さは当事者として大変よくわかるが、選挙を目の前にする政治家の弱みにつけ込んで、政争の具にするのは大変悲しい。この問題は日本の子どもの命運をかける大問題だ。政争の具にしてはいけない」と熱弁。斎藤法相に対し、「 DV被害者を保護しながら、共同親権を心から望む親や子どもたちは、全国にたくさんいる。そういう希望を叶える法制度の整備が、今こそ求められている」と訴えた。
これに対し、斎藤法相は「法制審議会において調査審議中であること、委員が今ご指摘されたような特定の見解の是非について、法制審議会に諮問をお願いしている立場である私が、個別にコメントすることは差し控えたい」と慎重な姿勢を示しつつ、法制審の調査審議の状況や外国法制調査の結果などの情報発信をしていることを改めて伝えた。
DV防止法改正案を閣議決定 精神的暴力でも裁判所が保護命令へ
出典:令和5年2月24日 NHK
DV防止法改正案を閣議決定 精神的暴力でも裁判所が保護命令へ
DV=ドメスティックバイオレンスへの対策を強化するため、政府は身体的な暴力だけでなく、ことばや態度による精神的な暴力でも、裁判所が被害者に近づくことなどを禁止する「保護命令」を出せるようにするDV防止法の改正案を、24日の閣議で決定しました。
今のDV防止法では、身体に対する暴力によって生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合にかぎり、裁判所が加害者に対し、被害者に近づくことなどを禁止する「保護命令」を出せるとしています。
改正案はこれに加え、生命や身体、それに自由や名誉、財産に対する脅迫により、精神的に重大な危害を受けるおそれが大きい場合でも、裁判所が「保護命令」を出せるようにしています。
例えば「部屋に閉じ込めるぞ」とか「裸の写真をばらまくぞ」などと脅されて精神的な苦痛を覚え、病院で治療を受けている場合などが新たに対象となります。
このほか改正案では「保護命令」の期間を、今の「6か月」から「1年」に延長するとともに、命令に違反した場合の罰則を、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に引き上げるとしています。
さらに「保護命令」の1つとして、被害者の子どもへの電話を禁じることを新たに加えています。
政府は、今の国会で改正案の成立を目指すことにしています。
小倉少子化相「暴力防止と被害者保護を強化」
男女共同参画を担当する小倉少子化担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「被害の発生から生活再建まで、切れ目のない支援を可能とするべく、他の機関との連携を強化する仕組みも設けている。配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を強化をするため、法案の成立に向けて努力をしていきたい」と述べました。
やす子、20年以上音信不通の父親と再会も「心の整理ついてない」家庭複雑「母とも疎遠」
出典:令和5年2月20日 デイリー
やす子、20年以上音信不通の父親と再会も「心の整理ついてない」家庭複雑「母とも疎遠」
タレント・やす子(24)が20日、日本テレビ系「しゃべくり007」に出演し、23年間会ったことのなかった実の父親と再会したことを明かした。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「ブレイクしたことで奇跡的なことが起こった」という話題を出した。やす子は2歳のころに父親と別離したと説明。その後、音信不通だったという。しかし、芸人となってブレークし、テレビなどにも出るようになると、ある日、SNSに「生まれた時間、日にちなどを知っている人物からリプライが来た」という。この人物が父親であることが分かった。「再会することができてっていうのが、芸人になってよかったなっていうことです」とまじめに語った。
父親の記憶は一切なかった。「自分のお父さんはいないと思って生きてきたので、ビックリしました。すごく」と感慨深げだった。さらに番組は、父親からの手紙を紹介。本名「安井かのん」の「かのん」宛の手紙だった。「20年もの間会うことができず、父親として何もできなくて、いっぱい寂しい思いをさせてごめんなさい」と謝罪。もう一度、父と娘の親子関係を築きたいという希望が書かれていた。
やす子は「うちの家庭はけっこうバラバラなんですね。母親とも疎遠でした」と家庭環境を告白。「それをつなぎとめられたらいいなと思ってたので、それがまず、父親という部分がかなってよかった」と喜んだ。一方で「まだ心の整理はついてない」と複雑な思いも吐露した。
父親と再会したのは昨年。父親も元自衛官で、やす子と同じ水泳や柔道も行っていたことも分かった。「しゃべり方とか見た目とか、会ってなかったのに生き写しを見てるようで、血ってつながってるんだなぁって。自分を娘と思ってくれてる人がいるっていうのがうれしかったです」と語った。
一方的な子供の「連れ去り」 裁判所が初認定「法の不備」が問うもの
出典:令和5年2月3日 産経新聞
一方的な子供の「連れ去り」 裁判所が初認定「法の不備」が問うもの
夫婦の一方が相手の同意を得ずに子供と家を出る「連れ去り」を防ぐ法規制がないのは、国として許されるのか-。子供と離れて暮らす親らがこう訴えた訴訟で東京地裁は1月、国に対する賠償請求は退ける一方、法規制が存在しないとして法の不備を認める初の司法判断を示した。ドメスティックバイオレンス(DV)被害者が子供を連れ出すなどやむをえない例もあるが、国際機関からは法整備の勧告も相次いでおり、別居中の子育てのルールを巡る議論にも一石を投じそうだ。
ミラー越しの面会
訴訟で原告となったのは、配偶者から同意なく子供を連れ去られたとする男女14人。刑事・民事ともにこうした事態を抑止する法律が存在せず、国が法整備を長期間怠っていると主張。違法性を追及できないため、子供の養育を巡って不利な立場に置かれているなどと訴えた。
※以下、紙面を参照ください。
【記事に関する参考:原告側・作花弁護士ブログ】
子の連れ去り違憲訴訟/東京地裁令和5年1月25日判決を産経新聞に取り上げていただきました
“配偶者の子ども連れ去り” 法整備求める訴え棄却 東京地裁
出典:令和5年1月25日 NHK
配偶者に子どもを連れ去られたと主張する男女14人が「親権や教育する権利を侵害されたのは国が連れ去りを防ぐ法整備を怠ったためで、憲法に違反する」と国に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「法律の制定は今後、議論されるべきだが、立法していないことが憲法に違反するとはいえない」と指摘し、訴えを退けました。
未成年の子を持つ男女14人は、配偶者が一方的に子どもを連れて家を出たのは国が連れ去りを防ぐ法整備を怠ったためだと主張し「親権や教育する権利を侵害され個人の尊厳などを定めた憲法に違反する」として、国に賠償を求めていました。
25日の判決で、東京地方裁判所の野口宣大裁判長は「子どもに対する監護や教育の権利などは親権者に一定程度の裁量を与えるものにすぎず、憲法が保障するほかの人権とは性質が異なる」と指摘したうえで「国が立法していないことが憲法に違反するとはいえない」として、訴えを退けました。
一方、判決は家族に関する法制度について「日本が批准する条約と整合させるよう国際機関から勧告を受けるなどしていて、国際的にみても問題視する立場がある。原告たちが主張する法律の制定は、今後、1つの選択肢として議論されるべきだ」と言及しました。
原告の男性「非常に悲しい思い」
判決のあと原告側が記者会見し、40代の男性は「親としての養育の義務を果たそうとしているのに、子どもを連れ去られたことで機会を失った。司法にはよい判決を期待していたが非常に悲しい思いだ」と話していました。
原告側は控訴する方針だということです。
子連れ別居めぐる訴訟で原告敗訴 「法の未整備」との主張認めず
出典:令和5年1月25日 朝日新聞
子連れ別居めぐる訴訟で原告敗訴 「法の未整備」との主張認めず
別居した夫婦の子どもが一方の親と引き離された状態のまま放置されているのは法の未整備が原因だとして、子と離れて暮らす親ら14人が国に慰謝料など計約150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁(野口宣大裁判長)であった。判決は「国会が立法義務を負っているとは言えない」として原告側の請求を棄却した。
訴状で原告側は、夫婦の一方が他方の親の同意を得ないまま子どもを連れて別居することを防ぐための法整備を国が長期間怠っている、と主張。「親権や面会交流権など、子どもを育て教育する権利が不当に制約され、幸福追求権を定めた憲法13条に違反している」などと訴えていた。
国側は、原告側が主張する権利は憲法で保障されているものではないと反論。親が子どもを連れて別居する背景には様々な事情があるとし、「(一方の親が)子と引き離されたことを一律に違法とする立法は相当ではない」などと主張していた。
判決は、親権や面会交流権について「憲法で保障された基本的人権とはいえない」と指摘。原告側は「家庭裁判所は子どもを連れて別居した親側を親権者と指定する傾向があり『連れ去り得』だ」と主張したが、判決は「家裁は親側、子側の事情を総合的に考慮していて、現状の監護状況を特に重視する判断をしていない」と述べた。(村上友里)
【速報】子どもの「連れ去り」めぐる国賠訴訟 東京地裁が訴え退ける
出典:令和5年1月25日 TBS NEWS DIG
【速報】子どもの「連れ去り」めぐる国賠訴訟 東京地裁が訴え退ける
配偶者が一方的に子どもを連れて家を出るのは「連れ去り」で、これを防ぐ法律がないことで精神的苦痛を受けたなどとして、男女14人が国に賠償を求めた裁判で、東京地裁はさきほど訴えを退ける判決を言い渡しました。 訴えを起こしたのは配偶者と別居後、子どもと別れて暮らす親ら男女14人です。 14人は配偶者が同意なく子どもを連れて家を出るのは「連れ去り」だとして、これを防ぐ法律がないために精神的苦痛を受けたなどと主張し、国に1人あたり11万円の損害賠償を求めています。
裁判で原告側は、▼憲法で保障された子を育て、教育する権利を不当に制約されている▼外国では「連れ去り」を防ぐための法律がある国もあり、これが日本にないのは国際条約に違反する▼別居後、家庭裁判所は同居する親を子どもの親権者に選ぶ傾向があり、「連れ去り得」というべき事態が起きている、などと訴えていました。 一方、国側は、▼一方の親が子どもを連れて転居する事情は様々で、子どもの連れ去りを一律に違法とするのはふさわしくないなどと反論していました。 きょうの判決で東京地裁は、原告側が主張した権利については、子を育て、教育するうえで「親権者に一定の裁量を与えたものに過ぎない」「憲法上保障された基本的人権であると解釈できない」と指摘しました。 その上で、国際条約との整合性についても「立法の判断は締約国の裁量に委ねられている」「我が国で子の連れ去りを防ぐ法規制が必要であることについて国民的に共通認識が形成されているとはいい難い」と指摘しました。 さらに「連れ去り得」という主張については「家庭裁判所は親権者を指定する際に親と子の事情を総合的に考慮している」と述べました。 子どもの「連れ去り」をめぐり、国が法律を整備していないことへの責任を求めた裁判は初めてです。
親の離婚で子どもが板挟みに-共同親権導入に賛否の声
出典:令和5年1月22日 Bloomberg
北條康雄さんはある日、6歳になる息子が玄関で「妻の方をきょろきょろと見て、どうしたら良いか分からない表情」を浮かべているのを目にした。
数日後、仕事から帰ると2人ともいなくなっており、家には妻の弁護士から離婚調停の申し立てを伝える通知が残されていた。
それから約1年、埼玉県にある2階建ての自宅に一人で暮らす北條さん(49)は、自分の子に会えないつらさをかみしめている。「同じ年齢ぐらいの子ども連れの人を見掛けると、なぜ自分はこんな当たり前のことができないのだろうと息苦しくなる。特に休日の公園などは一人ではとても近寄れない」と話す。
北條さんは監護者指定および面会交流などを求めているが、日本の法制度の下ではそれらの実現は容易ではない。ブルームバーグが取材した北條さんら男女十数人の親たちは、離婚後に子どもと会えなくなっただけでなく、100年余りの歴史の中で、政権の優先課題に応じて変遷し構築された曖昧な家族法制に阻まれている。
日本の子連れ別居
日本の親権は、「親権(医療・進学・居住などをめぐる重要事項決定権)」と「監護権(身の回りの世話)」の2つに大きく分かれる。離婚すると、父母どちらかに全親権に相当する権利が与えられることが多く、もう片方の親は子どもの人生からほとんど締め出されるリスクがある。離婚の手続きが簡単な上に、裁判所の介入が小さい日本において、排他的な単独親権の制度は婚姻関係の破綻をずっと複雑なものにしている。
日本は主要7カ国(G7)で唯一、離婚した夫婦に法律上の共同親権を認めていない。離婚の大半は協議か調停で解決されるが、合意できなければ裁判を行う。8割以上のケースで母親が親権者となっており、調停や裁判離婚に限れば、この割合は9割に上る。裁判所が命じる面会交流は1カ月につき数時間に限られることもある。
一方の親が他方の親の同意なしに子どもを連れて出ていくことは珍しくない。家庭内暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)が疑われる事案などもあることから、正当な行為だと見なされることが多い。日本の裁判所や法律は、主に育児を担っている親が子どもと別居する行為を容認している。一方、残された親が子どもを連れ戻そうとすれば、違法な連れ去りと判断されることが多い。
しかし、こうした状況が近く変わるかもしれない。家族法制を他の国々の制度により近いものにする画期的な提案が昨年11月に法務省から示された。離婚後の共同親権を導入する案も盛り込まれている。
同案の賛成派はこうした改革が大きな社会的・経済的利益につながると主張。反対派は特に虐待が疑われるような離婚のケースで、事態を悪化させる可能性があると警告する。双方とも政府の介入がもっと必要だという点では一致している。
母親が親権を獲得するケースが増加
日本では20世紀前半ごろまで、ほぼ全てのケースで父親に親権が与えられ、離縁された妻は実家に戻るよう迫られた。父系中心の19世紀の「家制度」に由来している。
しかし第2次世界大戦後、単独親権の制度が導入され、裁判所が子どもの親権を主たる監護者に与える傾向が定着していった。日本経済は1946年から76年の間で55倍に飛躍した。しかしこの経済成長の背後で、長時間労働の「サラリーマン」の台頭に伴う配偶者控除といった制度は、女性を家にとどめるか、働く場合でもパートタイム労働にとどめるよう促すインセンティブとして働いた。働く女性は減り、母親に親権が与えられるケースは急増。その一方で養育費の未払いに対応する制度が不十分なこともあり、夫と別れて子どもを引き取った女性の生活は苦しくなった。
この数年、単独親権制度を巡る批判がますます高まっており、離婚後も子どもと関わりたいと訴える親たちによる集団訴訟が相次いでいる。北九州市立大学の濱野健教授(文学部)は「日本人は従来、離婚して子どもに会えないのは仕方がないことだと諦めていた。今では多くの人が諦めることができなくなっている」と述べた。
支払われない養育費
2021年1月、上川陽子法相(当時)は、養育費が支払われない問題や親子交流の断絶といった子の養育への深刻な影響に懸念を表明。昨年11月、国の法制審議会の部会は「家族法制の見直しに関する中間試案」を取りまとめた。その中で、共同親権の選択肢のほか、一定の養育費を支払う義務が生じる新しい制度や、養育費の請求にかかる負担を軽減するための試案も示されている。
ただ、多くの専門家は共同親権の導入が親権争いの特効薬になるとは予想していない。紛争の根底には、家庭に潜むあらゆる暴力から個人を保護するシステムの貧弱さや、日本社会にはびこるジェンダー不平等がある。
未成年者の人口が減少している日本で、両親が離婚した子どもの数は年間約20万人と、50年前の2倍に増加。21年の政府調査によれば、そうした子どもの3分の1は別居親との関わりが最終的に絶たれているという。
1993年から断続的に日本に居住し、日本における離婚に関する著作がある人類学者のアリソン・アレクシー氏は「日本では、片親を失うことで子どもの心がどれほど傷付けられるかについて十分な認識がない」と述べた。過去40年間の調査60件に関する2018年の分析は、共同親権の対象となった子どもは心理的・身体的健康により良い影響が認められると結論付けている。
早稲田大学・法学学術院の法学部教授で、法制審の部会委員を務める棚村政行氏は、「家族に対する国家介入はしない方がよい、家族自身がやればよい」との考え方から「日本の家族法では家族が責任を負ってきた」と説明。「離婚後も共同で養育する選択肢が一切ない現状の制度は、社会の実情にそぐわない」ため、共同親権の選択肢も含め「さまざまな家族や親子の在り方に合った法的な仕組みが必要」だと述べた。
棚村氏はさらに、法改正にとどまっては「絵に描いた餅」だとし、養育費の確保を促すなどひとり親家庭の支援を強化する必要があるとも指摘した。
この40年間で日本の母子家庭は46%増えた。うち養育費を常に受け取っている家庭はわずか28%で、養育費の総額は月平均5万485円。養育費は母子家庭の家計全体の16.2%を占める。こうしたこともあって、日本は経済協力開発機構(OECD)加盟国の中でひとり親世帯の相対的貧困率が最も高い。
日本の母子家庭の子ども2人に1人が相対的貧困層にある。
昭和女子大学の宮坂順子研究員は、夫との離婚交渉や育児を一手に担う「プレシングルマザー」は、「最も過酷な状況に置かれたシングルマザーだ」と指摘。実質シングルマザーであるにもにもかかわらず、法的に婚姻関係が継続しているため、制度的に「ひとり親世帯」とは見なされず、公的支援はほとんど受けられないという。
制度の狭間に置かれるプレシングルマザーの多くは、「経済的にも精神的にも疲弊してしまい、離婚後の生活準備を行う余力もないのが現状だ」と宮坂研究員は見ている。
ブルームバーグ・エコノミクスのシニアエコノミスト、増島雄樹氏は「新しい共同親権の制度は、より多くの子どもが高等教育を受け、貧困の再生産を生まない持続可能な仕組みとなる可能性を秘めている」と分析
「追加的な財政負担も限定的で、人的資本の蓄積を通じて日本経済の長期的な成長に寄与することが期待される。共同親権によって離婚時に養育費を夫と妻で負担を協議できる制度を作ることは、ひとり親の子どもが受ける教育水準を向上させ、現在OECDで加盟国平均より大幅に高い日本の相対的貧困率を改善させる要因となる」と指摘した。
増島氏はさらに、「高齢化が進み、医療・年金の支出が年々増える中で追加的な財政支出には限界もある」とし、「養育費を両親で負担する新しい公的枠組みを通じて、支払いの『逃げ得』や親権の『囲い込み』を防ぐことは、マクロ的観点からも日本経済にプラスになるのではないか」と述べた。
親権争い
子どもの親権や面会交流を巡る争いはますます激化している。最高裁判所によれば、2020年には子どもに関する調停・審判の数が07年の2倍余りに増えた。調停の平均期間は約10カ月と、過去最長となった。
子どもを巡る夫婦の争いが激化
係争の増加は、家庭および職場における変化とも関連しているようだ。週60時間以上働く男性労働者の割合は2020年に8%と、1990年の22.4%から減少。育児休暇制度の拡充もあり、育休を取得する父親の割合は過去5年間で3倍に拡大し14%となった。ただ、妻が家事や子どもの世話に費やす時間はなお夫の4.5倍だ。
それでも日本の男性は子育てでより大きな役割を果たしつつあり、それに伴って離婚の際に親権を争う人も増えている。
北條さんはそうした男性の一人だ。1996年に大学を卒業し、道路や河川などのインフラ整備の仕事に携わっている。2012年に結婚し数年後に息子が生まれた。
北條さん夫妻は昨年夏、結婚から9年を経て調停手続きに入った。家裁調停委員の昨年9月の調査報告書は、息子の「父に対する拒否や不信感」に言及。北條さんから提供された同報告書のコピーによれば、「幼少の子にとっては、その出生時からの継続性が重要であること」と「長男自身も母と一緒に生活することを強く望んでいる」ことから、「母による現状の監護態勢を大きく変更するべき事情まではうかがえない」としている。その一方で、こうした状況に置かれた子どもは「別居親に対して同居親と同じ立場に立った否定的な言動を取る」傾向があるとも指摘している。
北條さんの妻はコメントを控えている。北條さんは息子と会えないまま、調停は不成立となった。手続きは審判へ進んだが、決着するころには息子に完全に疎外されてしまうのではないかと心配している。
神奈川法律事務所の大村珠代弁護士は「面会交流を申し立てても半年や一年以上かかることもある。その間に良好な親子関係が崩れてしまう危険性が高い。別居したらすぐに会える仕組み作りが不可欠だ」と話す。
作花法律事務所の作花知志弁護士によると、「片方の親が勝手に子どもを連れ去ってしまい、会わせないと主張した場合、現状の法制度では、子どもを取り戻すことは非常に難しい」という。最高裁のデータによれば、この10年間に約1000件の「子の引き渡しの強制執行」が認められたが、引き渡しに成功した割合は約3割にとどまる。
日本ではそうした命令を他国と同じようには強制できないと、同志社大学のコリン・ジョーンズ教授は指摘する。家庭裁判所の判断は「最終的にあまり意味がない」という。
斎藤健法相は親権制度について、現時点で大臣として意見を言うべきではないとし、「多くの人の意見に耳を傾けながら、結論を出していきたい」と述べた。
最高裁の広報によると、子の監護に関する事件については、個別の事情を考慮しつつ、「子の利益を最優先にした運用がされている」という。子の引き渡しの強制執行については「子の心身に重大な影響を及ぼさないように配慮」しながら行わなければならないと指摘。執行できない主な原因は引き渡されることへの子の拒絶や親、祖父母の抵抗だとした。
日本で共同親権に反対する声が一部で上がる理由の一つは、離婚の原因にDVの懸念があることが多いことだ。
警察庁によると、配偶者などパートナーからのDV相談は2001年以降に5倍に増えており、被害者の75%を女性が占めた。夫による精神的な暴力が認められず、調査官に面会交流を誘導されたケースもあると、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子理事長は話す。
目に見えない暴力
赤石氏は「共同親権を導入したら、子どもと女性にすさまじい影響が及ぶ」恐れがあると指摘。「別居から何年たっても妻への執着を消さない夫に襲われている妻は一生危険と隣り合わせ」になると警鐘を鳴らした。
最高裁のデータによると、女性が離婚を申し立てる際に挙げる最も一般的な動機の一つは「生活費を渡さない」など経済的DVとなっている。
元家庭裁判所調査官で、現在は富山大学専任講師の直原康光氏は、家裁では近年、親と子どもの双方から複数回にわたって面接を行うなど、より丁寧なアセスメントを実施するようになったと指摘する。ただ、家裁のリソース不足などを背景に「DVのリスク評価は、それでもなお難しい」という。
親権制度を巡る問題を最も大きく浮き彫りにしているものに、親が外国出身のケースが含まれる。キャサリーン・ヘンダーソンさんはその一人だ。オーストラリア出身の高校教師であるヘンダーソンさんは、1997年にメルボルンで元夫と出会った。結婚後に東京に移動し子ども2人ができた。夫から結婚15周年に離婚を切り出され、ヘンダーソンさんは拒否したという。
ヘンダーソンさん(52)によると、元夫は子どもと共に去り、彼女が子どもに会うことを認めなかった。元夫はコメントを控えている。ヘンダーソンさんは調停を求め、監護の計画や面会スケジュールの案を出したが、そこから一向に前進しなかったと話す。2人の子どもの親権は元夫に与えられ、ヘンダーソンさんの不服申し立ては退けられた。
この3年間、子どもと話す機会がなかったヘンダーソンさんは日本で暮らすのは「非常にストレスがかかる」としながらも、何かが変わることを期待し、できる限り長く住み続けるつもりだと語る。約2年前に電車内で娘を見かけたが、彼女を混乱させることを恐れ、話しかけずに電車を降りたという。
日本は、一方の親による子どもの連れ去りを巡って西側諸国から批判を浴びてきた。長年にわたる外交的圧力を受け、日本はG7メンバーでは最も遅い2014年にハーグ条約締約国となった。発効後の日本による同条約の運用は「他の締約国と比べても遜色ない」と京都大学の西谷祐子教授はみている。同条約は、一方の親に国境を越えて不法に連れ去られて留置された子どもについて、両親の国籍は問わず、原則として元の居住国へ返還すると定めている。
ただ、子どもの親権や面会交流を巡って日本国内で争っている親たちは、異なる扱いをますます不公平と感じている。
特につらいのは調停ペースの遅さだと北條さんは語る。妻と子が過ごしていた家の2階に行くのがつらく、2人がいなくなってからほとんど足を踏み入れていないという。
「父親として子どもの成長を見て感じて共に人生を歩みたい」と北條さんは話す。「会えたら、たわいもない話をしたい。定期的に会えるようになったら、子どもが喜ぶところに連れて行ってあげたい。野球とか釣りとか。息子はウルトラマンが好きだったが、今でも好きなのかなと、思いながら過ごしている」。
原題:Japan Tries to Fix Child Custody System Under Fire on All Sides(抜粋)
親権、養育費…転機迎える離婚後の子育て
出典:令和5年1月22日 産経新聞
子育てに関する法制度を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会が昨年11月に公表した民法改正の中間試案について、法務省がパブリックコメント(意見公募)を行っている。離婚後も双方の親に親権を認める「共同親権」が盛り込まれたことで注目されたが、養育費や離婚後の親子の面会交流など、試案には他にも重要な改正項目が示されている。今年は家族を巡る制度の「転機の年」となりそうだ。
子育ては両親の責務
部会が公表した中間試案では、子供の身の回りの世話をしたり子育ての重要事項を決めたりする「親権」について、現行の単独親権を維持する案とともに、離婚後も双方の親に認める「共同親権」を設ける案も併記。これ以外にも、幅広く現行制度の改正案が提示された。
注目されるのは、婚姻関係の有無に関わらず、子育てを「両親の責務」と明記した点だ。一見、当然のように思えるが、現在の民法に明確な規定がなく、子供と別居している親が離婚後の子育てに関わらない「口実」となっているとの指摘もあった。
子育てを両親の責務と明記したことが、今回の改正案の理念面での「骨格」だとすれば、実務面で骨格となるのが、養育費と面会交流に関する制度の改正案だ。
厚生労働省が平成28年に行った調査によると、別居する親が子供と同居する親に支払う養育費について、支払いを受けている母子家庭は24・3%に過ぎない。
このため改正案では、支払いを確実にできるよう、離婚した双方が合意していれば、養育費の支払いが滞った場合でも別居親の給与などを差し押さえる権利を同居親側に与えることを提案。合意がなくても、裁判なしに一定額の養育費請求権を与える制度を新設する案も盛り込んだ。
複数案で意見募る
一方、別居親にとって切実な問題なのが、子供との面会交流だ。厚労省の調査では、別居親と面会交流を実施している母子家庭は3割弱。父子家庭でも5割弱にとどまる。
面会を巡るトラブルへの懸念が背景にあるが、試案では、離婚調停中でも裁判所の観察下で面会交流を認める手続きを創設する案も示されている。
ほかにも、養育費や面会交流の取り決めがなければ離婚ができない新たな仕組みを導入する案も、取り決めなしに離婚できる現行案と併記。さまざまな項目で複数案を提示し、意見を広く募る形を取っている。
法務省関係者は「子育てが両親の責務であると明記し、養育費と面会交流の問題が前進すれば、離婚後の子育てに関する問題解決が一定程度、進展する可能性がある」と指摘する。
パブリックコメントの期間は今年2月17日まで。
(共同親権を与野党担当者に聞く)選択肢の拡大が重要 維新政調会長 音喜多駿氏
出典:令和4年12月9日 日本経済新聞
(共同親権を与野党担当者に聞く)選択肢の拡大が重要 維新政調会長 音喜多駿氏 [#nd650860]
法制審議会は共同親権の形式を原則的に認める、例外的に認める、個別の事案ごとに判断する――と併記した。いまはまだ整理した段階にある。どの選択肢に進んでいくかが大切になる。議論を見守りたい。
日本維新の会は選挙公約に共同親権の導入を盛り込んだ。共同親権が望ましい場合は選択できるようにすべきであるというスタンスをとる。選択肢を増やすことが重要だ。
答申を踏まえて党内論議を続けるが、いずれにしても単独親権しか選択肢がないという日本の現行制度は望ましいものではない。
ドメスティックバイオレンス(DV)などが原因で夫婦が別れた場合、共同親権がDVから逃れることの足かせになる場合もある。並行してDVに対する施策や法整備の拡充を徹底しないといけない。
共同親権にするか否かについて司法の判断が必要となる場合、夫婦双方の意見を聞いたとしても、DVの兆候などを見逃す可能性もある。
司法が適切に状況を判断する能力をいかに高めるか。人材面や機能面での家庭裁判所の強化が不可欠になる。
(共同親権を与野党担当者に聞く)子どもの声受け止め 公明法務部会長 大口善徳氏
出典:令和4年12月9日 日本経済新聞
(共同親権を与野党担当者に聞く)子どもの声受け止め 公明法務部会長 大口善徳氏
親権の問題は国民に大きな影響を与える可能性がある。法制審議会が中間試案で「共同親権」を認めるなど複数案を提示し、パブリックコメントで国民の意見を聞く姿勢は評価したい。
共同親権の容認は親が子どもに対する養育の責務を自覚し養育費の確保につながるという意見がある。一方でひとり親からは離婚の理由になった児童虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の継続につながるという心配が根強い。
私自身、弁護士として配偶者から暴力を受けた人や、逆に子どもに会えずに苦しむ親の代理人になった。大切なのは子どもの声を受け止めることだ。それが子どもの最善の利益を確保する法改正につながる。
中間試案で養育費の不払いや面会交流といった子どもの養育に関連する課題への対応も提示されているのは重要だ。公明党は子どもの最善の利益の実現を目指して養育費の不払い対策を提言してきた。
共同親権をめぐる議論が社会の分断につながるのはよくないと感じる。合意を形成していく努力が必要となる。党としても議論して一定の方向を出していきたい。
離婚後の子の利益、どう確保?=「共同親権」で意見公募―法務省
出典:令和4年12月7日 事実通信
離婚後の子の利益、どう確保?=「共同親権」で意見公募―法務省
離婚後の親権の在り方を巡り、法務省は6日、法制審議会(法相の諮問機関)の部会がまとめた中間試案に対する意見公募(パブリックコメント)を始めた。父母双方が持つ「共同親権」の導入と、どちらか一方が持つ現行の「単独親権」の維持を併記。賛否が対立する中、「子どもの利益」をどう確保するかが焦点だ。来年2月17日まで受け付ける。
現行民法は、婚姻中は父母の共同親権、離婚後は一方のみの単独親権と規定している。
単独親権を巡っては、養育費の未払いや面会交流の妨げにつながっているとの指摘がある。欧米各国では共同親権が一般的だ。
その一方で、離婚後も「DV(家庭内暴力)や虐待が続く恐れがある」として、単独親権の維持を求める意見も根強い。
中間試案は11月に決定。親権について方向性は示さず、共同親権と単独親権の両案を併記した。
その上で、共同親権を導入する場合の選択肢として、(1)原則は共同で一定の要件を満たせば例外として単独も認める(2)原則は単独で一定の要件を満たせば例外として共同も認める(3)個別事案に即して共同か単独か決める―の3案を示した。
中間試案にはまた、夫婦の話し合いによる「協議離婚」の際、養育費や面会交流の取り決めを義務付ける案なども盛り込まれた。
離婚後の子どもの養育制度見直し 6日からパブリックコメント
出典:令和4年12月2日 NHK
離婚後の子どもの養育制度の見直しに向けて、国の法制審議会が、父と母双方を親権者とする「共同親権」を導入する案と、一方のみの「単独親権」を維持する案を併記する中間試案をまとめたことを受けて、法務省は今月6日から、国民に広く意見を募るパブリックコメントを始めます。
国の法制審議会の部会が先月まとめた中間試案では、第1に「子どもの最善の利益を考慮しなければならない」と明記しています。
そのうえで、子どもの身の回りの世話や財産管理をする権限であり、義務でもある「親権」の扱いについては、親が離婚したあと、
▽父母双方を親権者とする「共同親権」を導入する案と、
▽いずれか一方のみの、今の「単独親権」を維持する案が、併記されました。
そのうえで、「共同親権」を導入する場合は、
▽「共同親権」を原則とし、例外的に「単独親権」を認める案と、
▽「単独親権」を原則とし、例外的に「共同親権」を認める案
などが示されました。
一方、今回の試案では、配偶者からの暴力や親による虐待がある事案には、適切に対応できる仕組みを検討するとしています。
このほか、父母の協議が整わないまま離婚や別居状態になった場合に、養育費の不払いが想定されることなどから、一定額の養育費を支払う義務が発生する「法定養育費制度」を新設する案も明記されました。
法務省は今月6日から来年2月17日まで、国民に広く意見を募るパブリックコメントを行い、集まった意見を参考に、さらに法制審議会で答申に向けた議論が行われます。
離婚後 “子どもにとっての最善を” 中間試案
親が離婚したあと、子どもをどう育てていくのか。
法制審議会の部会では、これまで1年半以上かけて議論が行われ、中間試案をまとめました。
大前提となる考え方は、「子どもにとって最善の利益となる」ことです。
このため、
▽父と母には、子どもを養育する責務があり、その最善の利益を考えないといけないこと、
▽子どもが示した意見を、年齢や発達の程度に応じて考慮することなどが明記されました。
さらに、すべての項目について、今後、具体的な規律を決めるにあたっては、配偶者からの暴力や子どもへの虐待があるケースに、適切に対応できるようなものにするとしています。
そのうえで、具体的な論点については複数の考え方を示しました。
離婚後の「親権」については、
▽現在の法律を見直し、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を導入する案と、
▽法律は変えずに、現在の「単独親権」を維持する案が、
併記されました。
「共同親権」を導入した場合の考え方としても、大きく3つの選択肢をあげています。
▽1. 父母の「共同親権」を原則として例外的に「単独親権」を認める案と、
▽2. 原則は父母どちらかの「単独親権」とし、一定の要件を満たす場合にかぎり双方を親権者とする案、
そして、
▽3. 原則を決めずに個別のケースに応じて、父母が話し合いなどで決めていくという案です。
いずれの場合も、「共同親権」「単独親権」のどちらにするかは、双方の話し合いで決め、決まらない場合は家庭裁判所が判断するとしています。
また、
▽別れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」や、
▽子どものための「養育費」についても、
法律を見直すかどうか、複数の案が示されました。
現在の法律では、協議離婚の場合、これらを事前に取り決めることとしていますが、義務とまではなっていません。
中間試案では、父親と母親の間で明確な取り決めがないことで、子どもに不利益にならないよう、
▽1. 法律を見直し、原則として、事前に取り決めをしなければ離婚できないようにする案と、
▽2. 法律は今のまま、取り決めを進めるための別の方法を検討する案の、
両方が示されました。
このほか、事前の協議が整わないまま離婚や別居状態になった場合に、養育費の不払いが想定されることなどから、
▽一定額の養育費を支払う義務が発生する「法定養育費制度」を新設する案も盛り込まれました。
法制審議会の部会は、パブリックコメントで寄せられた意見も参考に、具体的にどういう制度にしていくのか、引き続き検討していくことにしています。
共同親権、与野党担当者に聞く
出典:令和4年12月1日 日本経済新聞
子どもに最善の利益を/男女格差あわせて考慮
法相の諮問機関である法制審議会が離婚後の親権のあり方の中間試案をまとめた。父母双方に「共同親権」を認める案を併記した。各党の法務分野の政策担当者に聞いた。
■ 子どもに最善の利益を 自民・法務部会長宮崎政久氏
法制審議会が「共同親権」を認める制度案と、片方だけが親権を持つ現行の「単独親権」を維持する案とにまとめたのは評価している。1つに集約できるほど国民の意見は統一されていない。
自民党の中で共同親権導入を訴える意見が多いことは十分理解している。離婚後も父母双方に関係があるとドメスティックバイオレンス(DV)などが続くとして現行のような制度を維持してほしいという声もある。
私は双方の立場に立つ代理人弁護士として複数の案件を担当した。両方の気持ちが分かるからこそ、この件はフラットにやる。
法務部会である議員が「国民の声を真摯に聞くべきで、パブリックコメント(意見公募)の制度があるなら使うべきだ」と言った。その通りだ。
国民の声を聞いた上で最後は1つの案にまとめることはできる。主義主張や世界観、信条は内心の問題でまとめることはできない。あくまで法制上の措置を集約させる。
重要なのは子どもにとり最善の利益をどうすれば一番確保できるかという発想だ。
父母が離婚後も日常的な身の回りの世話、養育費の支払いなど子を養育する責務を持つことに変わりはない。その責務を果たすための制度をどのようにつくったらいいのかを考える。
法制審の案のなかの「具体的な要件を定めず個別ケースごとに単独か共同かを選択可能にする」やり方は実務の判断が難しい側面がある。離婚時は夫婦の関係が悪化しており協議が成立しない場合が多い。
■ 男女格差あわせて考慮 立民・ネクスト法相牧山弘恵氏
法制審議会は国民の関心が非常に高い離婚後の親権の問題について、提示案を1つに絞らず論点整理の段階でパブリックコメントを募ることにした。
早い段階で国民に選択肢を共有するのは、いずれなされる政治決断を国民感情に近いものにすることにつながる。
親権は離婚後の親子関係に大きな影響を与える。子どもの利益を最優先して考えることが大原則だ。その上で選択を子どもの責任にしてはならない。
子どもは両親が離婚したときの年齢や親の再婚相手などによって、父と母のどちらと住みたいかが変わる。どちらとも一緒に暮らしたくない場合もある。
弁護士として米国で勤めていた。共同親権を認める米国の制度は一緒に住む権利と、進路や治療方針など子どもに関する重要事項を決める権利にわかれる。
父親と母親の間を行き来したりお迎えに父親の再婚相手が来たり、さまざまなケースがあった。
日本は諸外国と比べ家事の分担や女性の所得など男女の違いがある。主要な海外で共同親権を認めているから日本でも導入してみればいいという安易な問題ではなく、ジェンダーギャップ指数などをあわせて見て検討した方がいい。
立憲民主党は共同親権へ賛成派、慎重派の双方から意見を聞いてきた。党内でも賛否は割れており、中間試案も踏まえさらに議論を重ねたい。
国政選挙の公約策定のような時間の制限を受けるような環境とは切り離して、丁寧に方向性を出したい。
「共同親権」どう考える 賛否両派に聞く
出典:令和4年11月24日 時事通信
離婚後の親権の在り方を巡り、法制審議会(法相の諮問機関)家族法制部会が、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を導入する案と、現行の「単独親権」を維持する案を併記した中間試案をまとめた。
前者はさらに、共同親権を原則とする案と、一定の要件を満たせば例外として共同親権を認める案に分かれる。「子の利益」の観点から親権制度はどうあるべきか。近く始まる意見公募(パブリックコメント)を前に、共同親権の賛否両派に話を聞いた。
◇「原則共同親権・監護」実現を=柴山昌彦氏―超党派共同養育支援議連会長、自民党衆院議員
中間試案に、私たちが求める「原則共同親権・共同監護」という選択肢が入ったことは評価する。世界でも単独親権制度の国は極めてまれだ。「子どもの権利条約」では子が親の保護を求める権利が保障されている。
少なくとも家族が幸せに暮らしている時、子どもはパパもママも好き。子が親との関係を保ち、子に対する責務を両親が果たす婚姻中の正常な形を、離婚時に片方の親が断ち切られる単独親権制度が子の利益に即しているとは思えない。それがあるべき姿であれば、世界でもっと単独親権の国が増えていると思う。
別居親との面会交流ができずに子どもが悲しい思いをする、同居親との間で起きる子の福祉を損なう行為に対して子の異変やSOSを別居親が認識できないなど、単独親権が弊害になるケースが出てきている。
子どもと没交渉なのに養育費だけ支払わされているお父さんから「自分は現金自動預払機(ATM)か」との声も聞く。養育費が喜んで支払われるような子どもとの交流も、自然な形で極力認められるべきだ。
子の養育を継続的にしていた人が離婚時の親権獲得で優位になる。だから子を連れ去って既成事実として親権を獲得するという事案を誘発する。共同親権なら、親権獲得目的で連れ去るインセンティブがなくなる。
共同親権ではDV(家庭内暴力)が継続すると懸念する声もある。夫婦間の問題と親子間の問題が常に連動するわけではないと考えるが、子の福祉に沿わないDVや虐待があるケースを共同親権の例外とすることに、私は異を唱えない。
(DVが)認定されるプロセスのいとまがない場合など、正当な理由があって子どもを連れて避難することまで否定しない。ただ、親権喪失や親権停止の制度は今もある。やむにやまれず出て行った人はどれくらいの比率なのか、実態調査を踏まえた上で議論しなければいけない。
(子どもの日常の世話や教育をする「監護権」を両親が持つことで物事の決定に支障が出るとの指摘に)共同監護を原則としても、あらゆることまで別居親の同意が必要なわけではない。離婚時に養育費や面会交流、その他の子どもに関する基本事項の決定について話し合うことが一番だ。監護者指定で合意できず、共同監護となった場合は裁判所の負担が増えるため、地方自治体やNPO、カウンセラーの活躍の場を広げてはどうか。
試案取りまとめの過程で自民党法務部会が圧力をかけたとの指摘があるが、政府提出法案でも与党の同意がなければ閣議決定されない。法制審のプロセスの中で与党とキャッチボールしながら進めることを圧力だと言うのは、日本の統治機構に対する誤解だ。
◇共同親権導入は時期尚早=赤石千衣子氏―しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長、法制審委員
中間試案は書きぶりが共同親権に寄っていると感じる。委員に現場を知っている人が少なく、当事者の実態が伝わっていない。協議離婚した人の実態が議論されないまま、拙速に案を出した。さまざまなケースを慎重に考える必要があり、民法をいじるのは時期尚早だ。
「共同養育的な関わり」の推進は賛成だ。私もそのように子どもを育ててきて、子どもは自由に父親と会っていた。同居親以外の関わりがあることで、子どものセーフティーネットは増える。
だが、離婚後に子の重要事項を共同決定することを法制化するのは反対だ。離婚後に協力して子育てできている人に法改正は必要ない。コミュニケーションを全く取れない場合、子どもにすさまじい不利益が生じる。
共同監護で事前に話し合いを要する場合、別居親から日常的に情報提供を求められたり、進学先などが決まらなくなったりする恐れがある。経済的に脆弱(ぜいじゃく)なひとり親が、(意見が対立し)家庭裁判所決定となるたびに仕事を休み、弁護士費用を払うことなどできない。今でもパンク状態の家裁が対応できるのか。
(選択的に共同親権とする案の)「選択的」というのは誤解を生みかねない。意見が合わなければ家裁に持ち込まれ、調停や審判で決定されてしまう。
(DV=家庭内暴力や虐待のケースを例外的に単独親権とする案に関し)DV被害を受けている渦中に証拠を集められる人はほとんどいない。裁判所がアセスメント(評価)できると思えない。
2011年の民法改正以来、家裁は面会交流原則実施論一色となった。調停では、夫から煮えたぎった鍋を投げつけられる暴力を受けた人でさえDVは軽視され、面会交流するよう求められている。調停経験者を対象に行った調査では、家裁が中立ではないという声が多数あった。今度は「DVの証拠がないなら共同親権にしなさい、それが普通だ」と調停で言われる恐れがある。
「子の連れ去り」とはDVや虐待からの緊急避難だ。生活基盤を手放して突然逃げるのはよほどのことで、逃げざるを得なかったからだ。
もう一つ想定されるのは、別居親が全く無関心で連絡が取れないケースで、数としてはこちらの方が多い。協議離婚で連絡先も居場所も分からないケースでどう共同決定するかという議論も全然されていない。
共同親権になっても面会交流の推進や養育費確保の保証はない。それどころか制度の立て付け次第では扶養控除や手当がなくなり、余計生活苦になるかもしれない。民法改正では人の行動は変わらない。子どもと親のサポートや社会保障の仕組み、家裁の体制を強化するのが先ではないか。
「イクメン」時代、離婚後も父母両方で養育を 共同親権に賛成の識者
出典:令和4年11月16日 朝日新聞
「イクメン」時代、離婚後も父母両方で養育を 共同親権に賛成の識者
二宮周平・立命館大名誉教授(家族法)
離婚後の子どもの親権を父母の双方が持つ「共同親権」を導入すべきか、父母のどちらか一方に決める今の「単独親権」を維持すべきか――。法務大臣が意見を求めた専門家会議は、激論の末、両論を併記する中間試案をまとめた。共同親権の導入に賛成する二宮周平・立命館大名誉教授(家族法)に話を聞いた。
――中間試案についての見解は。
「共同親権を導入する案に賛成します。ある調査によると、離婚後も親子交流を続けている父母は25%程度います。ただ、合意が長続きする保障はなく、親権者が交流をやめるといえば、非親権者に抵抗する手段はありません。家裁で争って親権者を変更することはできますが、かえって対立が深まり、話し合いが難しくなります」
「選択制になっている韓国や台湾では、従来通り単独親権になることが多く、共同親権を選ぶのは2~3割の夫婦に限られます。離婚後も養育費を払い、頑張って子育てをしている父母を支える制度は必要です」
――共同親権になると、どんな変化がありますか。
※以下、紙面を参照ください。
離婚後の共同親権で3案提示 単独親権案も併記、法制審
出典:令和4年11月15日 日本経済新聞
中間試案、方向性定めず
法相の諮問機関である法制審議会は15日、離婚後の親権のあり方に関する中間試案をまとめた。父母双方に「共同親権」を認める3つの制度案を示しつつ、片方だけが親権を持つ現行の「単独親権」を維持する案も併記した。共同親権の導入を巡る賛否が割れている状況を考慮し、方向性を定めず複数案を提示するにとどめた。
親権は子供の世話や財産管理に関する民法上の権利・義務とされる。現行法は婚姻中であれば父母がともに親権を持つ「共同親権」で、離婚した場合はどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」になると規定する。
法制審は離婚後に共同親権を認める場合の制度として①原則は共同親権で一定の要件を満たせば例外として単独親権も認める②原則は単独親権で一定の要件を満たせば例外として共同親権も認める③具体的な要件を定めず個別ケースごとに単独か共同かを選択可能にする――の3案を記した。
現在の単独親権の法規定を維持する案も載せた。12月から2023年2月をめどに中間試案のパブリックコメント(意見公募)をかける。
共同親権を導入するには答申をまとめたうえで民法を改正する必要がある。法務省の担当者は「答申の時期は見通せていない。法改正を含め具体的な時期を示すことは困難だ」と語った。
法制審は21年から家族法制部会で共同親権を導入する是非を議論してきた。親権を持たない側が子供に会えない不満を持ったり、養育費を払わなかったりする問題が出ていた背景があった。
欧州連合(EU)の欧州議会は国際結婚が破綻した日本人配偶者が子供を連れ去る事例が相次いでいると主張し、20年に共同親権を認める法整備を求める決議を採択した。
共同親権は賛否が割れる。家族法制部会委員を務める「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」の武田典久代表は現在の単独親権制度では離婚後に金銭面などの責任を持たなくなりがちな親がいると指摘する。
「共同親権にすれば直ちに解決するわけではないが、離婚後の親の意識を変えることにはつながる」と強調する。
慎重派は離婚後も父母双方に関係があると虐待やドメスティックバイオレンス(DV)が続くと危惧する。
シングルマザーサポート団体全国協議会が6~7月に実施したひとり親を対象とするアンケート調査では8割が共同親権制度が導入されても「選択しない」「どちらかというと選択しない」と回答した。
離婚した理由として「子供への悪影響」「精神的虐待」を挙げた人はいずれも37%に上った。
同協議会の代表で家族法制部会委員を務める赤石千衣子氏は「共同親権にかじを切れば子供が危うい状況に置かれる」と訴える。赤石氏ら一部委員は11月15日に「限定的で拙速な議論が進められていることを憂慮する」との意見書を法制審に提出した。
法制審はもともと8月末に中間試案をまとめる予定だった。当初案は共同親権の導入について原則認めるか一定の要件下で認めるかの2案に単独親権維持案を併記した内容だった。
自民党の法務部会で共同親権導入の推進派から党内意見の反映などを求める主張が続出したため先送りした。個別ケースごとに共同親権か単独親権かを判断する案を追加する修正や検討経緯の説明を経て11月10日の部会で了承を得た。
厚生労働省によると日本の離婚件数は20年におよそ19万3000組で、うち11万1000組程度は未成年の子供がいる夫婦だった。家族のあり方にかかわるだけに国民的な合意を得て進めるのが望ましい。
中間試案は養育費不払いの問題を踏まえ一定額の養育費を払う義務を課す「法定養育費制度」を創設する案も盛り込んだ。親子が定期的に会う面会交流の実施を巡っては子供の意思や発達状況などの判断基準を明確にすることを提起した。
立命館大の二宮周平名誉教授は「共同親権を認めるには離婚後の養育について情報提供する講座の受講を父母に義務付け、面会交流や養育費など父母間の合意形成を促す体制が必要だ」と訴える。
海外の主要国は共同親権が一般的だ。法務省によると米国や英国、オーストラリア、韓国などが導入している。イタリアやフランスは共同親権を原則としつつ、虐待リスクなど子供の利益に反すると裁判所が判断すれば単独親権を認める。
「子の利益」論点整理できるか 離婚後親権の中間試案
出典:令和4年11月15日 産経新聞
法相の諮問機関「法制審議会」の家族法制部会が15日、公表した中間試案は、離婚後の親権に関し、共同親権と単独親権の単純な「二者択一」ではなく、例外規定を設けて細かく選択肢を提示する形となった。意見集約が難しかったことの裏返しともいえるが、法務省はパブリックコメント(意見公募)で国民の意見を広く募り、さらなる議論に生かす考えだ。
共同親権の導入を巡っては、平成23年の民法改正時に衆参両院の法務委員会の付帯決議で「可能性を含めた検討」が明記されたことなどを受けて、令和3年2月に法相が法制審に諮問していた。
部会では、共同親権であっても従来通りの単独親権であっても「子供の利益に資するべきだ」という点は委員間で一致していた。ただ、実際にどんな仕組みが最も「子の利益」につながるかという点については、議論百出した。
ある委員は、共同親権は子供からみれば、普段はそばにいない「もう一人の親」に相談する権利になりえるとし、肯定的な見方を示した。別の委員も、離婚後に別居する子供から受験について電話で相談を受け、これをきっかけに元配偶者と話し合いの機会を持ったことで適切な助言ができたとの体験を明かし、原則的に共同親権とすることで、こうしたケースが増えることを期待した。
ただ、離婚した両親の意思疎通が円滑でない場合、子供の進路などの重要事項が、かえって期限内に決まらないなどの混乱も予想される。このため中間試案では、共同親権はあくまで「例外」とし、原則的に単独親権とする案も併記された。
また、ドメスティックバイオレンス(DV)の渦中にある場合などでは、共同親権だと「真の合意ができない可能性があり、一切認めるべきではない」という意見も出た。このため、現行の単独親権のみしか認めないとする案も残された。
今回の中間試案では、共同親権を認めた場合でも、身の回りの世話をする「監護者」については父母のいずれか一方を指定する仕組みも提案された。
法務省関係者は、今回の中間試案について「あくまでパブリックコメントを募るための案だ」と強調する。神学論争に陥ることなく「子の利益」を軸に論点をどう整理し、「両論併記」を脱することができるかが、法案化のカギとなりそうだ。(荒船清太)
[離婚後の「共同親権」導入、「単独親権」維持と両案併記 法制審
出典:令和4年11月15日 朝日新聞
離婚後の「共同親権」導入、「単独親権」維持と両案併記 法制審
離婚後の子どもの親権について法制審議会(法相の諮問会議)の部会は15日、父母双方が持つ「共同親権」の導入と、どちらか一方に限る現行の「単独親権」の維持を併記した中間試案をまとめた。賛否が激しく対立して1案には絞れず、法務省は年内にもパブリックコメントを実施して国民の意見を募る。
親権には、日常的な身の回りの世話(監護)などをする「身上(しんじょう)監護権」と、子の財産を管理し、契約行為を代理する「財産管理権」があるとされる。現行の民法では、婚姻中は父母双方が親権を持つが、離婚後は一方に決める必要がある。
中間試案では、法改正して共同親権を導入する案と、現行の単独親権を維持する案を併記した。
そのうえで共同親権を導入する場合は、①共同親権を原則とし、一定の要件を満たす場合に限って例外的に単独親権を認める②単独親権を原則とし、例外的に共同親権を認める③原則・例外を設けず、個別事案に即してどちらかにする――の3案を示した。
共同親権にした場合、親権のうちの身上監護権を担う「監護者」を定めるかも焦点になる。中間試案では、必ず父母の一方に定める案と、監護者は定めずに双方が監護することも可能にする案を併記した。
中間試案は、離婚後の養育費の支払いや、別居する親子の面会交流をめぐる新たな制度案も示した。
養育費や面会交流の取り決めをしなければ原則離婚できない▽養育費の請求権が自動的に発生する▽親子交流の実施を判断する要素(子の生活状況、安全面など)の明確化――といった複数の案が盛り込まれた。
見直しの背景には、夫婦3組のうち1組が離婚するといわれ、親が離婚した未成年の子が毎年約20万人に上るなか、離婚後も父母双方が子の養育に責任を持つべきだとの考えがある。
一方、共同親権に対しては「関係が継続することで家庭内暴力や虐待が続く」などとして反対する声も強く、法制審部会は1案に絞れなかった。15日の部会でも、一部の委員が「議論が拙速」として中間試案の取りまとめに「強い懸念」を表明する意見書を出した。
政治の関心も高く、8月の自民党法務部会では共同親権を求める立場から「中間試案の内容が分かりにくい」との指摘が出て、同月末に予定していた取りまとめが先送りされていた。その後、骨格は維持したまま若干の修正がなされた。(田内康介)
離婚後の共同親権、法制審部会が中間試案 単独親権の維持も併記
出典:令和4年11月15日 毎日新聞
離婚後の共同親権、法制審部会が中間試案 単独親権の維持も併記
家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は15日、離婚した父母の双方が親権を持つ「離婚後の共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正の中間試案を取りまとめた。現行制度の単独親権を維持する案も併記した。部会は、12月開始予定のパブリックコメント(意見公募)の結果を踏まえ、詰めの議論に移る。
民法上の親権は、未成年の子に対して親が持つ権利と義務を指し、子の身の回りの世話をする「身上監護」と、子の財産を管理し子に代わって法律行為をする「財産管理・法定代理」からなる。現行制度は、婚姻中は共同親権、離婚後はどちらか一方の親による単独親権と定める。
今回の試案はまず制度の枠組みとして、離婚後に共同親権を選択することについて、原則とする▽例外とする▽個別事案に即して決める――の3パターンを提示。その上で共同親権を行使する範囲に関し、婚姻中と同様に子に関する全事項について共同で行使する▽父母のいずれか一方を「監護者」と定め、親権のうち身上監護に関する事項については単独で決める――といった選択肢を提案した。
一方で、父母が激しく対立したり家庭内暴力(DV)や虐待で力関係に差があったりするケースでは、離婚後の共同親権は難しいとの意見も踏まえ、部会は、現行通り単独親権しか認めない案も併記した。
養育の取り決め義務付け案も
試案は親権以外のテーマについても見直し案を示した。日本では、子への養育費の支払いや別居親と子の面会のルールを決めないまま父母が離婚に至るケースが多く、一人親家庭の貧困や親子の断絶を招いているとの指摘がある。
このため試案は、父母の話し合いだけで決める「協議離婚」をする際に、離婚後の子の養育について学ぶ講座を受けることや、子の養育に関して取り決めをすることを義務付ける案も提示。養育費の額を決められなかった場合に同居親側に一定額の養育費の請求権が発生する「法定養育費制度」や、家裁が別居親と子の暫定的な交流を命じられる手続きの創設も盛り込んだ。
部会は2021年3月に議論を開始。今年8月に中間試案を取りまとめる予定だったが、部会内外から「案が分かりづらい」と指摘があり、先送りしていた。【山本将克】
離婚後の親権で法制審が中間試案…「共同親権」選べる案と「単独親権」維持する案を併記
出典:令和4年11月15日 読売新聞
離婚後の親権で法制審が中間試案…「共同親権」選べる案と「単独親権」維持する案を併記
離婚後の親権のあり方などを議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は15日、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」が選べる案と、どちらか一方が親権を持つ現行民法の「単独親権」を維持する案を併記した中間試案をまとめた。12月から2か月程度のパブリックコメント(意見公募)を行う。法制審は国民の意見を踏まえて早期の答申を目指す。
現行民法は、婚姻中は父母が共同で親権を持つが、離婚後は片方が親権を持つ「単独親権」を規定している。「単独親権」は離婚時の親権争いや、子どもの連れ去りなどのトラブルの原因とも指摘される。欧米諸国では共同親権が一般的だ。
一方で離婚後も家庭内暴力(DV)や虐待が続く恐れがあるなどの理由で、単独親権を支持する声もある。
中間試案では、共同親権を導入する場合、〈1〉共同親権が原則だが、父母間の合意などを条件に例外として単独親権も認める〈2〉単独親権が原則だが、例外で共同親権を認める――の2案を示した。原則や例外を定めず、個別事案に即して柔軟な選択を可能にする考え方もあると追記した。
共同親権を認める場合、子どもの世話をする「監護者」について、〈1〉必ず父母の一方を指定する〈2〉父母の一方を監護者と定めるかどうかは協議で決める――との案を併記した。離婚後の財産分与を請求できる期間を現行の2年から「3年」と「5年」に延長する案も示した。
中間試案は当初、8月にまとめる予定だったが、自民党内から共同親権に関する内容が「分かりにくい」などと反発があり、先送りされていた。
離婚後の共同親権案を提示 「単独」維持併記、法制審
出典:令和4年11月15日 東京新聞
離婚後の子どもの養育について検討する法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は15日、制度見直しの中間試案を取りまとめた。親権に関し、父母双方の「共同親権」を選べる案、現行民法のままどちらか一方の「単独親権」だけを維持する案など、10ほどの選択肢を併記した。
当初は8月末に取りまとめ予定だったが、自民党法務部会で強硬に共同親権導入を求める一部議員らが反発、先送りされた。15日の試案は修正を小幅にとどめ、当初案を基本的に維持した。
12月初旬にもパブリックコメント(意見公募)を実施。今後の議論次第では、離婚後の親子関係が大きく変わる。
離婚後「共同親権」も選択肢 中間試案、12月から意見公募―法制審
出典:令和4年11月15日 時事通信
離婚後「共同親権」も選択肢 中間試案、12月から意見公募―法制審
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は15日、離婚後も父母の双方に親権を認める「共同親権」導入を選択肢の一つとした中間試案をまとめた。12月から意見公募(パブリックコメント)を実施する予定。答申に反映させる。
現行民法は、父母の婚姻中は共同で親権を持つが、離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」を規定している。
中間試案は、共同親権を導入する案と、単独親権を維持する案を併記。さらに、共同親権を導入する場合は(1)共同親権を原則とする(2)父母間の合意など一定の要件を満たせば例外として共同親権を認める―などの案を提示した。
戦後民法の親権制度に欠陥
出典:令和4年11月2日 日本経済新聞
ITコンサルタント 松村直人
9月27日の本欄に「離婚後(実質的には別居後)の単独親権」を巡る問題が掲載された。これと密接に関係する「婚姻中共同親権の制度欠陥」について説明したい。
そもそも私たち国民はどの程度「婚姻中共同親権」を意識しているだろうか。民法818条3項は「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う」と定めており、婚姻中は父母が共同で子育ての意思決定をする必要がある。しかし、父母の考え方が異なる場合の規定が無い。円満な夫婦でも受験やワクチン接種などで考えが異なる場合、意思決定が不能になるのだ。この解消手段の1つが「子の連れ去り」という乱暴な実力行使であり、家庭裁判所が「監護者の指定」手続きにより「別居後単独親権」を事実上作り出している。
このような意思決定のデッドロックを避けるため、企業は通常1対1の出資比率を避ける。また共同親権を採用している各国は、父母の意見が対立した際の調整規定を設けている。具体的には裁判所がどちらかの親に決定権を与えるか、裁判所がその内容を決定するか、いずれかの方法だ。つまり、日本の婚姻中共同親権は対等な父母の最終意思決定方法を欠くという重大な欠陥を抱えている。
実は、父母の意見が不一致の場合の調整規定が無い問題は、戦後1947年に民法が改正された当時から指摘されていた。ただ当時は父親が意思決定する時代だったため、立法者は課題を認識しながらも何の手当てもしなかった。その後も民法学者が繰り返し指摘してきたものの、放置されてきた。
博報堂生活総合研究所の「家族30年変化」調査によれば、家庭の総合的決定権を持つのは、1988年に夫72%、夫婦同等16%、妻10%だったが、2018年には夫39%、夫婦同等31%、妻30%に変わっている。過去30年で家庭内の意思決定は夫優位から夫婦対等に大きく変容した。そして家庭の重要な役割として子育てがあり、その意思決定方法を規定するのが親権制度である。父母対等な現代家庭を支えるには、意見調整機能を備えた真の共同親権が必要だ。
私はこの共同親権の意見調整機能不備の立法不作為を問う国家賠償請求訴訟を起こしており、12月に控訴審判決が予定されている。
急げ「実子連れ去り」問題解決を
出典:令和4年10月21日 産経新聞
コラム 正論
不覚にも最近初めて知ったのだが、国内で親による「実子連れ去り」事件が多発しているという。
わが目疑う実子の「誘拐」
ご存じでない読者には、にわかに信じられないであろう。
※以下、紙面を参照ください。
離婚しても子育ては半分ずつ 共同親権が当たり前のアメリカから見る単独親権の違和感
出典:令和4年10月19日 The Asahi GLOBE+
離婚しても子育ては半分ずつ 共同親権が当たり前のアメリカから見る単独親権の違和感
離婚後の子供の共同親権問題。日本ではこの夏、賛否が激しく対立する中、議論が物別れに終わりました。
離婚後の共同親権の導入を議論してきた法制審議会(法務大臣の諮問機関)は、中間試案の取りまとめを見送り、パブリックコメントで広く意見を募るはずだった予定自体も延期となりました。
結婚している間、夫と妻は協力し合い、子育てにいそしみます。特に意識することなく共同親権のもと、子供の成長に向き合っていきます。
日本の場合、離婚後は父母のどちらか一方しか親権を持つことができず、現行の法律では単独親権となります。もちろん、日本でも面会交流の取り決めをして、月に1度であったり、週末を一緒に過ごしたり、ということはあるかと思いますが、わたしの周囲の一般的なシリコンバレーのファミリーの場合、離婚後は「親権、まっぷたつの共同親権」の場合がほとんどです。
アメリカでは子供にとって最善の利益になるように離婚後の取り決めがされます。そもそも、日本のように「父親か母親のどちらかの選択」という概念がなく、離婚したからといって「片方の親が、子育ての蚊帳の外に置かれる」という風潮もなく、父親も母親も親権を望むので、よっぽどのことがない限り、単独親権にはなりません。
つまり、子供は両親の家を行き来して、平等に同じ時間だけ過ごし、両親は離婚後も2人で子育てを継続していきます。
小泉純一郎元首相が、離婚後に小泉氏が長男と次男を、元妻が三男を引き取り、長年交流がなかったことが報道された際には、周囲のアメリカ人から「そんな人が首相でいいの?」と聞かれたことがあります。小泉家には小泉家の事情があったのだとは思いますが、アメリカ人からすると理解し難いようでした。
共同親権 という意味の英語「Joint custody」には、一緒に住む権利の 「Joint physical custody」と 学校や習い事をどうするか、病気やけがの治療方針をどうするかなどを決定する権利の「Joint legal custody」 があります。
アメリカでは離婚後の子供の親権は各州によって法律が異なるのと、各家庭のそれぞれの事情により異なってきますが、離婚はすべて裁判所を通し、財産分与、養育費、子供に会う権利など細かい点まで協議、調停、裁判などのプロセスを経て合意に至った後に、ようやく離婚成立となります。
一度合意されると、日本によくありがちな一方の親が離婚相手に精神的苦痛を感じわだかまりがある、または、相手の再婚相手が気に入らない、などの感情論で子供との面会を拒否することはできません。
ちなみに、日本人の妻/夫がアメリカ人の配偶者の合意なく、離婚後に子供を連れて日本に帰ると、ハーグ条約により「誘拐扱い」になります。
合意までの過程の中で、それぞれの親が子供と過ごす基本的なスケジュールが決められます。ちょっと限定的な例えとなりますが、わたしの周囲のシリコンバレーのテック企業などで働く共働きカップルが離婚する場合、ほぼ共同親権で合意されます。両親ともに虐待、ギャンブル、アルコール中毒などの特別な問題がない場合です。
例えば、周囲によくあるのが水曜日の朝までパパの家、水曜の学校の後のピックアップはママ側が担当し、週末は隔週でそれぞれの親と過ごすパターン。3カ月弱ある夏休みなどの際は、3週間ずつ交代にしたり、11月のサンクスギビング(感謝祭)はママの家で過ごすのであれば、クリスマスはパパ側で過ごす、といった感じです。
子供は二つの家を行き来し、歯ブラシも二つ、おもちゃも二つ、洋服も2カ所に分けて(もしくはその都度持参して)、自分の部屋も二つという生活を送っています。
子供の誕生日会を離婚後も2人がそろってホストしていることも多いですし、子供のサッカーゲームを観戦しているシーンに遭遇するときもあります。
私の13歳の娘などは、住む場所は1カ所なのに、部屋の整理整頓がいまいちで、学校の用意も当日の朝ギリギリ、忘れ物もあります。場所が2カ所だと次の日や、次の次の日の習い事の用意など、先に先にと考えなければならず、大変だろうなあ、と想像したりします。子供が小さいうちは、それは必然的に親の仕事となります。
アメリカのカマラ・ハリス副大統領は、夫のエムホフ氏の前の結婚での子供2人に初めて会ったのは彼らがまだ10代の時だったそうですが、結婚後にステップマム(義理のお母さん)となったハリス氏は、Mom(ママ)とKamala(カマラ)を合わせて「モマラ(Momala)」と呼ばれているそうです。彼らも成長期にかなりの時間をハリス氏とも、実の母親とも過ごしたのではないかと思います。
日本の場合、今の若い夫婦が離婚した場合はもしかしたらそうでもないのかもしれませんが、私の世代では両親が離婚して、父親には(または、母親には)それ以来一度も会っていない、という知り合いが何人かいます。また、親側も、「別れた子供は今20歳になっているけど、10年以上会ってない」という知り合いもいます。
「DV(家庭内暴力)や虐待から子どもの安全を守れなくなる」など、共同親権に反対の意見は理解できます。加えて、親の一人がアルコールや薬物、ギャンブル依存などの問題を抱えていることもありえるでしょう。日本でさまざまな声が上がっており、反対理由もさまざまです。
アメリカではDVなどがあった場合は、監視下の元、第三者がいる状態で子供との面会が行われることが多いようです。
共同親権であれば、「すべてがスムーズでバラ色でいいことづくし」というわけではありません。両家を行き来する子供の精神的な負担や、親のストレスも、もちろんそれなりにあります。
離婚した元夫が再婚し、再婚相手の連れ子と性格が合わない、その子供の友達がきたら仲間はずれにされて居心地が悪い、コロナ時のときでは感染予防に関する意識のレベルが違うので相手の家に行かせるのが心配、お互い子供と過ごしたい休暇のスケジュールが合わない、家庭内ルールが二つの家庭で異なり子供が混乱する、など、それはそれは、各家庭それぞれお悩み、課題は山のようにあります。
「パパのところには行きたくない」「ママよりパパの家がいい」。子どもの意向をどこまで尊重するかも親にとっては悩ましいところです。
子供が大きくなり、生活環境に変化が応じた場合、お互いの合意によって親権の決定を後から変更することも可能です。
わたしの夫の両親は離婚していますが、それぞれのパートナーを連れて私たちの結婚式のときには日本にやって来たのには、わたしの日本人の両親はちょっとびっくりしていました。しかし、これもアメリカでは非常に一般的です。
子供にとっての二重拠点生活。課題が多く、複雑な生活スタイルになったとしても、父親(や母親)に1年にたった1度会うのではなく、両方の存在と愛情を身近に感じながら子供たちは大きくなっていきます。
シリコンバレーでお互い顔も見たくないほどドロドロにこじれた離婚の後(もしくは離婚調停中)でも、浮気をされて怒り心頭に発していたとしても、いったん合意したあとは、「大人」になって子供のためにスケジュールを調整し、連絡をとりあっているファミリーを見ていると、日本の今回の共同親権の導入の議論自体が先送りになったのには、正直、違和感があります。
離婚しても、別々に暮らすようになっても、他に家族ができたとしても、家族であることには違いないですから。
グリーンバーグ美穂
Miho Greenberg。神戸出身。ユダヤ系アメリカ人の夫、12才の女の子の3人暮らし。1905年に設立された北カリフォルニア・ジャパンソサエティーの COO。日米間の相互理解を深め、特に子供の「ジャパン・ファン」人口を増やす、という目標に向けて邁進中。現職の前は、 サンフランシスコにあるマーケティング企業で、世代別のライフスタイル調査などを担当。ボストンでは、MITメディアラボ勤務。趣味は、仕事と子育て。他はアウトドア、ピラティス、料理などなど。
「実子誘拐ビジネス」とは?共同親権問題、マスコミが報じない弁護士業界のリアル
出典:令和4年10月12日 SAKISIRU
「実子誘拐ビジネス」とは?共同親権問題、マスコミが報じない弁護士業界のリアル
法務省法制審で提起している“共同親権”が「骨抜き」「名ばかり」だとして、民間法制審を立ち上げて自民党が2つの案を俎上に載せる異例の展開となっている。これはどういうことなのか。法務省案の問題点、そして親子の離別を「ビジネス化」してきた一部弁護士の実態など、共同親権問題をとりまく様々な問題について、民間案の作成に協力した上野晃弁護士にインタビューした。
※以下、原文を参照ください。
共同親権、分担養育の仕組みを
出典:令和4年9月27日 日本経済新聞
臨床心理士・公認心理師 宮崎保成
9月2日の本欄に掲載された投稿「離婚後の『共同親権』導入を」を読んだ。親であっても我が子に会えない、成長に関われず見守ることもできないことがどれほどつらいか。現行法では離婚後に父母のどちらか一方が親権者になるが、離婚後も共同親権となり、我が子と交流できることを期待するのは親として当然であろう。
ただ、離婚後共同親権になれば子どもと交流できるようになるのだろうか。ここで考えてほしいのは、現行法でも婚姻中は共同親権ということである。離婚まで父母が別居をして、子どもがどちらか一方の親と同居していても、法的には共同親権である。しかし法的に共同親権でも、別居親は子どもと十分交流できるとは言い難い。
同居親が子どもと別居親との交流に寛容であれば、親権の有無に関係なく交流ができるが、そうでない場合、親権の有無に関係なく裁判所に面会交流の調停や審判を申し立て、合意や決定がされるまで我が子に全く会えないことも珍しくない。そして裁判所の面会交流に関する決定(頻度や交流時間)は、別居状態であっても離婚後であっても差異はない。つまり裁判所の面会交流に関する決定に親権の有無は関係ないのである。
今は「離婚後単独親権」とされるが、実質的には「別居後単独親権」になっている。だから子どもと別居すると、共同親権であっても実際に行使できる親権はほとんどない。仮に今後、離婚後共同親権になったとして、それが婚姻中別居状態と同じような共同親権だとしたら、子どもとの交流を含めて実質的な改善は期待できない。
ではどうすべきか。子どもの情報(居住地や学校の様子など)を知る権利の規定、面会交流の基準となるガイドラインの作成、子どもの日常の世話に責任を持つ監護権については米ケンタッキー州のような共同監護制度(裁判官は原則、父母の平等な育児時間が子どもにとって最善と推定)の導入といったことを検討すべきだ。
海外の研究では離婚後も別居親が少なくとも35%の育児時間を分担すると、子どもの健康度や成績が良いとの結果も出ている。漠然と離婚後共同親権に期待するのではなく、実質的な具体的改善がある法改正が望まれる。
親権を考える 離婚後のあり方 識者に聞く
出典:令和4年9月23日 中日新聞
離婚後の子どもの養育を考えた本紙の連載「親権を考える」(先月十八、十九日)には、多くの反響が寄せられた。目立ったのは、離婚後の親権を父母のどちらかに限る「単独親権」のままでいいか、両方の親が持つ「共同親権」を導入すべきかについての意見だ。読者の声を紹介するとともに、親権制度を法的な観点から解説している木村草太・東京都立大教授と、離婚後の親子の交流支援の重要性を訴える小田切紀子・東京国際大教授の話を伝える。 (小林由比、長田真由美)
※以下、紙面を参照ください。
論点 離婚後の共同親権
出典:令和4年9月21日 毎日新聞
離婚後の共同親権の導入をめぐり、賛否が激しく対立している。法制審議会(法相の諮問機関)の部会では現行の単独親権維持と共同親権導入の両案併記の形で、8月中に中間試案を取りまとめ、パブリックコメントにかける予定だったが、自民党保守派の反発で先送りになった。3人の識者にさまざまな視点を提示してもらった。
※以下、紙面を参照ください。
「共同親権」の試案先送り 離婚後の養育巡り法制審部会
出典:令和4年8月31日 日本経済新聞
離婚後の子どもの養育について検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会は30日、予定していた中間試案の取りまとめを延期した。父母双方の親権保持を可能にする「共同親権」を導入する民法改正を巡り自民党の議論で意見が割れ、再調整が必要になった。
法制審の家族法制部会は2021年3月から離婚後の「共同親権」の導入に向け検討を重ねてきた。現行法は離婚すると父母のどちらかしか親権を持てない。
※以下、紙面を参照ください。
柴山昌彦共同養育支援議員連盟会長は、8月31日に投稿されたFacebookで、「自民党では、子供の利益の観点から原則としては共同親権制度を採用するよう訴えてきましたが、法務省の取りまとめ案は単独親権維持と両論併記になっていて方向性が示されず、その後のパブリックコメントの様子を見て方針決定するという生煮えのものであること、そして監護のあり方なども含め極めて複雑でわかりにくいものであることが問題とされ、承認を保留すべきという意見が大勢となっていたのです。」と紹介されています。
離婚後共同親権、法制審の中間試案先送り 自民部会了承せず
出典:令和4年8月26日 時事通信
離婚後も父母の双方に親権を認める「共同親権」をめぐり、法制審議会(法相の諮問機関)の中間試案の決定が先送りされる見通しとなった。26日の自民党法務部会でさらなる議論が必要と判断され、了承が得られなかったため。当初は30日の法制審部会で決定後、意見公募(パブリックコメント)を行う予定だった。
法務部会では、法務省側の説明に対し出席者から「部会での意見を聞かないで中間試案を決めるなら、何のために部会をやっているのか」との反発が続出。終了後、熊田裕通部会長代理は「親権についてはさまざまな立場があり、丁寧に議論を進める必要がある」と述べ、再度部会を開く考えを示した。
あびる優で注目される「連れ去り」は家族法制見直しでなくなるか 「共同親権導入」を訴える自民党議員に聞いた
出典:令和4年8月23日 デイリー新潮
あびる優で注目される「連れ去り」は家族法制見直しでなくなるか 「共同親権導入」を訴える自民党議員に聞いた
「子供を連れ去られた」「DVを受けていた」。週刊誌の“代理戦争”にまで発展したタレント・あびる優と元夫との親権争い。双方に言い分があるようだが、忘れてはならないのは父母の争いで片方の親との仲を引き裂かれてしまう子供である。日本でこのような夫婦間トラブルが多発する“元凶”と言われているのが離婚後の「単独親権制度」だ。いま親権制度の見直しが、法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で審議されている。自民党内でも法務部会の中にプロジェクトチーム(PT)が発足し議論が活発化。「共同親権・共同監護は譲れない」と語る自民党議員二人に話を聞いた。
***
子供の利益を最優先に考えるべき
「『共同親権よりもまず養育費だ』という声も確かにあります。この問題について調べてみると、10人いれば10人それぞれのケースがあって話がまとまりにくいのです。だからこそ、私たちは原理原則論で行くべきだというスタンスで、『共同親権・共同監護』で民法改正を進めるべきという提言書をまとめたところです。法律は家族を幸せにするためのものであり、家族を引き裂いてはいけない。子供の利益を最優先に考えるべきだという考えが根底にあります」
こう語るのは、前自民党法務部会長の山田美樹衆議院議員だ。
日本の民法では、離婚した場合はどちらか一方かが親権を持つ「単独親権制度」が採られている。あびるのケースでも離婚後に一度、親権が元夫側に渡ったものの、あびるが親権者変更を申し立てる争いに発展した。そもそも離婚後も共同で親権を持つ制度であれば、このような争いが起きづらくなるという考え方が増え始めてきているのだ。
自身も離婚経験がある谷川とむ衆議院議員もこう訴える。
「日本では協議離婚が約9割です。つまり、口約束で子供の養育方針が決められてしまっている。だから、事後的に養育費が支払われないなどの問題が出てきてしまうのです。あらかじめ離婚後も『共同親権・共同監護』と決めたうえで、離婚時に『共同養育計画』を作成し、養育費は月々いくら、親子交流を月2回などと申し合わせる仕組みを作るべき。我々の案では『離婚後養育講座』を受講することも盛り込んであります」
民間法制審も「共同親権導入」を提言
諸外国で単独親権制度を採り入れているのは、日本、インド、トルコくらいである。山田氏は「グローバルスタンダートにならうべきだ」とも訴える。
「国際社会では、国際結婚した日本人による離婚後の子の連れ去りが起きていると、長らく日本は批判を浴びてきました。先日、凶弾に倒れた安倍晋三先生も外交に力を入れてきたからこそ、この問題に対して前向きでした。PT内でも、『慰安婦問題などと違ってこの問題だけは反論できない』という声も出ています」
自民党PTでは、こうした議論を経て「離婚後共同親権(監護権を含む)制度を導入すべき」などの提案を柱とする5項目の提言をまとめ、6月21日に古川禎久法務大臣(当時)に申し入れを行った。
この問題をめぐっては民間サイドでも動いている。日本テレビの人気番組「行列のできる相談所」でおなじみの北村晴男弁護士(66)が部会長を務める「民間法制審議会家族法制部会」が4月に結成され、共同親権導入を求める独自試案を5月末に高市早苗・自民党政調会長(当時)に提出した。自民党PTの提言書も民間法制審の提言も参考に取り入れた上で作成されたという。
骨抜き案
だが、このまま「共同親権・共同監護」を盛り込んだ法案作成へと進んでいくかと思いきや、相反する動きも出ている。法制審が7月にまとめた「中間試案のたたき台」が、自民党の提言書とはまったく違う内容のものだったのだ。
たたき台では、「乙案」として「単独親権」を残す案も記載されている。共同親権を採り入れる「甲案」においても、親権を選択制にする案などと記載。さらに、親権と監護者を切り離して、親権は双方にあれど監護者は単独とするなどの案が、α案からγ案といったかたちで盛り込まれている。実質的に単独親権制度と変わらない“骨抜き案”になっているのだ。山田氏はこう首を傾げる。
「審議会というのは、法制審に限らずいろいろな考え方の識者を集めて開かれていますのでこういう形にはなってしまったのだと思います。法制審のたたき台案のなかには、父母の離婚時に父母の協議のみで一方を子の単独親権者に認めたりすることもできてしまう案もあります。婚姻中の親権剥奪事由とは異なる事由で本人の意思に反して裁判所が親権を剥奪してしまう案もある。そうではなくて、原則原理で『共同親権・共同監護』というのが私たちの考えです」
法改正で「連れ去り」は防止できるのか
法制審では中間試案を取りまとめた後、パブリックコメントを募集し、年内にも答申案を決定する。その内容が自民党案と違う場合はどうなるのか。
「原理原則は変えないというのが私たちの方針です。法制審案がもし骨抜きになってしまったとしても、それが与党を通ることはありえません。」(山田氏)
もし自民党が提言するような法案に改正され、「共同親権・共同監護」が当たり前の社会になると「連れ去り」はなくなるのだろうか。谷川はこう力説する。
「連れ去られたとしても、親権も監護権もこちら側にあると主張できるようになれば、話し合いが避けられなくなると思います。もちろん、これからもDVで命からがら逃げ出したような人たちは今後もケアし続けないとなりません。けれど、それは違う法律でちゃんと対応していけば良いのです」
夫婦間ですれ違いが生じ、やむなく別れを選択するのは致し方ないことであろう。だが、子供にとっては父も母も一人しかいない。離婚の狭間で子供が苦しむことがない世の中が実現するよう、一刻も早い制度改正が望まれる。
デイリー新潮編集部
親権を考える(下)共同か単独か 子どもの利益を第一に
出典:令和4年8月19日 中日新聞
子どもの育ちの視点からも、離婚後の子どもの養育の在り方について、慎重な議論をする必要があるのではないか―。医師や心理士、保健師らでつくる日本乳幼児精神保健学会は六月末、こうした声明を出した。法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、父母の双方が親権を持つ「共同親権」の導入が議論されていることに、危機感を持ったからだ。
共同親権になれば、「離婚後も父母が共同で子育てができる」と導入を推す意見がある。別居親と子どもの面会交流や養育費の支払いもスムーズに行えることを期待する声も上がる。
共同親権で子の安全・安心守れるか
一方で、「子どもの安全・安心を守れるのか」との懸念は根強い。同学会は声明で「家庭内暴力(DV)や虐待が継続したり、父母間の葛藤や紛争がこじれて慢性化したりして、同居親が危険やストレスから子育ての余裕を失い、養育の質が低下しないか」と訴える。
同学会の理事で児童精神科医の黒崎充勇みつはやさんによると、虐待を受けた子どもは一般的に、不安感が強く、抑うつ状態に陥るなど、その後の対人関係にも影を落とす。脳の発達に影響することも分かっている。
※以下、紙面を参照ください。
親権を考える(下)共同か単独か 子どもの利益を第一に
出典:令和4年8月19日 中日新聞
離婚後、子どもの親権は父母の双方が持つべきか、どちらか一方に限るべきか-。法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、議論が進められている。そもそも親権とは何だろう。親権がなければ子育てはできないのか。現状を二回に分けて紹介する。(長田真由美)
調停で面会交流可能に
中国地方に住む男性(39)の家には週一回、離れて暮らす小学生の長女と長男が遊びに来る。一緒にゲームをしたり、ご飯を食べたり。親権を持つ元妻も含めて四人で出かけることもある。「珍しいかもしれないが、これが僕たち家族の在り方です」
元妻が子ども二人を連れて家を出たのは二〇一七年末。夫婦間の価値観の違いが積み重なり、小さなけんかが増えていたが、まさか出て行くとは思わなかった。悔しさや怒りもあったが、「子どもに会いたい気持ちが強く、妻と争いたくなかった」と振り返る。
「子の問題と夫婦の問題は別」
離婚調停中、面会交流を申し立て、数カ月たってようやく認められた。最初は月一回一時間だけだった面会の時間は次第に延びた。男性は「離婚しても親として子どもへの責任はある。子どもの問題と夫婦の問題は切り分けて考えるべきだと思う」と話す。
※以下、紙面を参照ください。
協議離婚「養育」決めて 民法改正で義務化、法制審部会が検討 「ハードル上がる」慎重論も
出典:令和4年7月20日 毎日新聞
協議離婚「養育」決めて 民法改正で義務化、法制審部会が検討 「ハードル上がる」慎重論
家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は19日、民法改正の中間試案取りまとめに向け、父母の話し合いのみで成立する「協議離婚」に一定の条件を設ける制度案を議論した。離婚を検討している父母に、離婚後の子の養育について取り決めることを義務付ける内容。協議離婚のハードルを上げることになり、導入に慎重な意見も示された。
日本では夫婦の離婚は協議離婚が主流で、離婚件数全体のおよそ9割を占める。ただ、協議離婚には裁判所など公的機関が関わらないため、離婚後の養育費や面会交流の具体的内容を定めないまま離婚に踏み切る父母もいる。このことが、養育費の未払いや親子交流の断絶の要因になっているとの指摘があった。
※続きは、紙面を参照ください。
離婚後「共同親権」案、中間試案に盛り込む方針…海外では一般的
出典:令和4年7月20日 読売新聞
離婚後「共同親権」案、中間試案に盛り込む方針…海外では一般的
離婚後の親権や養育費のあり方を見直す法制審議会(法相の諮問機関)の部会は19日、民法などの改正案を巡って、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」を選べる案を、中間試案に盛り込む方針を決めた。共同親権への反対意見を踏まえ、現行の「単独親権」を維持する案も併記する。部会は8月末に中間試案を決定した上で、パブリックコメント(意見公募)を行い、早期の答申を目指す。
現在は離婚後、父母の一方が親権を持つ。親権がない場合は子育てに関与しにくく、親権争いが生じる原因とされる。年間の離婚件数は、近年は20万組前後で推移する。
米国などの主要国を含む24か国対象の法務省調査では、単独親権のみを採用しているのは、日本のほかにインドとトルコだけだった。海外では、共同親権が一般的だ。離婚後も両親が子育てに関与できるようにすべきだとして、共同親権導入を求める声が出ていた。
共同親権を導入しても父母の関係が悪ければ、協力した意思決定は困難で、DV(家庭内暴力)や虐待を危惧して単独親権の維持を求める声もある。このため、部会は、親権について両論併記することとし、親子の実情に応じて、共同か単独かを選択できる案を示した。
親権者とは別に、子供の身の回りの世話をする「監護者」の規定を置くことも検討する。養育費の取り決めを離婚の要件とすることや、支払いを拒否する相手方の給与差し押さえが容易になる方策なども議論されている。
共同親権選択制、単独維持を併記 法制審、離婚後の養育議論本格化
出典:令和4年7月19日 東京新聞
共同親権選択制、単独維持を併記 法制審、離婚後の養育議論本格化
離婚後の子どもの養育について検討する法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は19日、親権制度見直し案のたたき台を示した。父母双方の「共同親権」を選ぶことができる案、現行民法のままどちらか一方の「単独親権」だけを維持する案などを併記した。この日の意見を踏まえ、8月末に中間試案を示す方針。
父母がどちらも子育てに責任を持つべきだとして共同親権の導入を求める声がある一方、ドメスティックバイオレンス(DV)を受け、元配偶者との関わりを避けたいといった理由から反対意見も根強い。議論の行方次第では、離婚後の親子関係の在り方が大きく変わる。(共同通信)
法制審、離婚後の共同親権で論点 選択制など複数案提示
出典:令和4年7月19日 日本経済新聞
離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は19日、親権制度見直しのたたき台を示した。父母双方の「共同親権」を選択できる案や、従来通り「単独親権」のみを維持する案など複数案を提示した。
民法は婚姻中の父母が共同で親権を持つと認める半面、離婚後はどちらかだけが親権者となる単独親権を採用する。米国や英国、ドイツ、フランスなど先進国の多くは離婚後の共同親権を取り入れている。
離婚後も父母双方が子の養育に責任も持つべきだといった意見を受け、法制審は2021年3月に家族法制部会を立ち上げた。8月末までに中間試案にまとめ、パブリックコメント(意見募集)にかける。
たたき台では共同親権を認める際に子を日常的に世話する「監護者」について2案を示した。父母の一方を監護者に決めるか、監護者の設定は父母の協議で選択するかの2つを並べた。
共同親権を認める法改正をする場合、現行法との整合性も論点になる。2案のうちの1つは、父母双方を親権者にすることを原則にし、例外として「一定の要件を満たす場合に限り、父母の一方を親権者とすることができる」と定めた。もう1案は逆に単独親権を原則とし、共同親権を例外にした。
共同親権を巡っては離婚後にドメスティックバイオレンス(DV)や虐待が続くことへの警戒感も根強い。単独親権のみを定める現行法の維持も案に入れた。
離婚後の養育費と親子の交流についても盛り込んだ。現行法ではそれぞれに関して事前に取り決めがなくても離婚ができる。法制審は事前に取り決めをしなければ原則として離婚不可とするか、取り決めを促すための支援策を別途検討するかの2案を設けた。
古川禎久法相は19日の記者会見で「子の最善の利益を確保することが最も大事な観点だ」と指摘した。
「共同親権」導入の是非 中間試案では複数案併記へ 離婚後の父母双方が子どもの親権持つ案について法制審で賛否両論
出典:令和4年7月19日 TBS NEWS DIG
「共同親権」導入の是非 中間試案では複数案併記へ 離婚後の父母双方が子どもの親権持つ案について法制審で賛否両論
離婚後の父親と母親がともに子どもの親権を持つ「共同親権」について、法務省の審議会が来月まとめる中間試案では導入する案としない案が併記される見通しとなりました。
現在の民法では離婚後の子どもの親権者は父親か母親、どちらか1人とする「単独親権」が定められていますが、欧米では、ともに親権をもつ「共同親権」が認められています。
この導入を検討している法務省の法制審議会の部会は、きょう、来月末にまとめる予定の中間試案の詰めの検討を行いました。
この中では離婚後、▼原則、共同親権とする案、▼原則、単独親権としつつ共同親権も認める案、▼これまで通り単独親権とする案の3つの案が併記される方向となりました。
部会では「離婚後も両方の親が子育てに責任を持つべき」として、共同親権を求める意見がある一方、DVや子どもへの虐待を防ぐため導入に反対する声もでています。
離婚後の「共同親権」、賛否対立し大激論 「単独親権」維持も併記
出典:令和4年7月19日 朝日新聞
離婚後の「共同親権」、賛否対立し大激論 「単独親権」維持も併記
離婚後の子どもの親権は父母の双方が持つべきか、どちらか一方に限定すべきか――。法制審議会(法相の諮問機関)の部会は19日、「共同親権」の導入と、現行の「単独親権」の維持を併記する形で論点整理をした。8月末にまとめる中間試案のたたき台という位置づけで、中間試案ができればパブリックコメントで国民の意見を募る。
親権には、大きく分けて、未成年の子の身の回りの世話(監護)と教育をする「身上(しんじょう)監護権」と、子の財産を管理して契約行為などを代理する「財産管理権」があるとされる。
今の民法では、父母が婚姻中は双方が親権を持つが、離婚後は一方に決めなければならない。欧米の多くや韓国は、制度設計の違いはあるが離婚後の共同親権を可能にしており、国内でも「単独親権は子の奪い合いを招く」「離婚後も双方が養育に責任を持つべきだ」との指摘が出ていた。
法制審の部会は今回の論点整理で、基本的な規律として「父母双方が子を養育する責務を負う」「子の最善の利益を考慮しなければならない」と明確にした。
※以下、紙面を参照ください。
離婚後の共同親権を提示 単独親権維持も、来月に中間試案―法制審
出典:令和4年7月19日 時事通信
離婚後の共同親権を提示 単独親権維持も、来月に中間試案―法制審
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は19日の会合で、離婚後も父母の双方に親権を認める「共同親権」の導入と、現行民法の「単独親権」を維持する案を併記した中間試案のたたき台を提示した。8月末の次回会合で決定し、意見公募(パブリックコメント)を行う。
現行法上は、婚姻中の父母は共同で親権を行使するが、離婚後はどちらか一方のみが親権者になる「単独親権」制をとっている。
しかし、厚生労働省の人口動態統計によると、2020年に婚姻した夫婦約52万組に対し、離婚した夫婦は約19万組。3組に1組が離婚しており、単独親権制が養育費の未払いや面会交流が円滑にできないといった問題の要因になっていると指摘されている。
また、欧米諸国では共同親権が一般的なため、国際結婚が破綻した際の日本人の親による「子ども連れ去り」が国際問題化している。
「子どもの連れ去りは未成年者略取罪」 警察庁が明言、共同養育支援議連で 警察の現場対応、円滑化に期待
出典:令和4年2月5日 SAKISIRU
「子どもの連れ去りは未成年者略取罪」 警察庁が明言、共同養育支援議連で 警察の現場対応、円滑化に期待
牧野 佐千子 ジャーナリスト
親の離婚後の子どもの養育に関する問題の解消に取り組む超党派の共同養育支援議員連盟(柴山昌彦会長、三谷英弘事務局長)の総会が3日、東京・永田町の衆議院第2議員会館で開かれ、20名以上の議員が参加した。法務省、警察庁、最高裁、内閣府、厚労省、総務省、文科省、外務省の担当者が出席し、各省庁での取り組みを報告した。(これまでの議連については、アゴラ拙稿「共同養育・共同親権に向けて、超党派で動きが活発に」参照)
総会は非公開で行われたが、柴山会長は終了後、報道陣への説明で、「一方の親の子どもの連れ去りについて、これまで『法に基づき処理』の一辺倒だった警察庁が『正当な理由のない限り未成年者略取罪に当たる』と明言し、それを現場に徹底すると答えた」と会の成果を語った。
「連れ去り」現場の警察官が対応しやすく
日本は両親の離婚の際に、子どもの親権がどちらか一方の親のみに決められる単独親権制で、親権の獲得を有利に進めようと、一方の親の同意なく子どもを連れ去り別居する行為が横行している。これまでは、こうした「連れ去り」の行為については、刑法で有罪とした例は公刊物の中では見当たらないと最高裁は回答していた。ところが、連れ去られた側の親が連れ去られた子どもを「連れ戻す」場合には未成年者略取罪として逮捕される例も多く、アンバランスな状態が続いてきた。
「連れ去り」行為には、子どもも知らない第三者が介入して、まさに誘拐のように突然連れ去られる例などもあり問題となっているが、現場の警察署員もこれまでに判例もなく、「助けたくても手が出せない状況もあった」という声も届いていた。
しかし今回、警察庁が「未成年者略取罪に当たる」と踏み込んだことで、「連れ去り」に対する現場での警察の対応がしやすくなり、抑止力が働くようになるのではと期待が寄せられる。
(柴山氏のTwitterでも議連の報告がされている↓)
2月3日の共同養育支援議員連盟総会で政府と協議。片親による子の連れ去りについて警察庁はこれまで「法に基づき処理」一辺倒だったが、昨日ようやく、同居からの連れ去りか別居からの連れ戻しかを問わず、正当な理由がない限り未成年者略取誘拐罪にあたると明言。これを現場に徹底するとした。(続く)
日仏当局の協議も開催へ
議連ではほかにも、DV防止法の改正に伴い、「精神的DVの要件を明確にする必要がある」ことと「加害者とされた者の手続きの保障の必要性」の確認が度々なされたという。これについては、親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)が、子どもを連れ去り、長期に及び子どもと引き離す行為も「精神的DV」と定義することを要望している。
また、子どもの連れ去り問題の日本政府の対応はEUからの非難決議など、国際社会からも批判を受けてきた。
(関連アゴラ拙稿「EUが日本非難!『子ども連れ去り』を止める法改正を」)
先般、フランスの大使館員の子どもが「連れ去り」にあったことや、マクロン大統領からの要望があったことを踏まえ、外務省は近日中に日仏当局間で協議することになったと明かした。
法務省の法制審議会の家族法制部会(関連拙稿:「共同親権」導入も議論:離婚後の養育をめぐる課題解消に向け、上川法相が法制審に諮問)の会議が11回目まで終了しているが、同省の担当者は、次回から2巡目の検討に入り、今年中に中間とりまとめを行い、その後最終答申に入るといったスケジュールを表明したという。柴山会長は「意欲を示してもらったのは前進だと思う」と述べた。
柴山会長は、議連の働きかけに手ごたえを感じている様子で、「議連として今後、申し入れなど積極的に行っていく」と意欲を示していた。
ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ
出典:令和4年1月15日 SAKISIRU
ミツカン父子引き離し事件、「子どもを連れ去った者勝ち」の日本は、子供の権利条約違反だ
牧野千佐子 ジャーナリスト
ミツカン創業家の「娘婿」中埜大輔さんが、「ミツカン社とその創業家によって、組織ぐるみで生まれたばかりの長男と引き離されたことは、国際法違反の児童虐待である」として、同社の会長・副会長夫妻を相手に損害賠償請求訴訟を起こしている。13日には東京地裁でその第1回口頭弁論が開かれ、その後大輔さん(被告との混乱防止のため以下「大輔さん」)と代理人の河合弘之弁護士が記者会見を行った。
「親子引き離し」信じがたい“手口”
訴状などによると、ミツカングループは日本のほか、アメリカ、イギリスなど世界各地に支店や生産拠点をもつ大企業。江戸後期の1804年、初代中野又左衛門が創業して以来、中埜一族の「一子相伝」による支配的な経営がなされている。
同社の株式や同家の財産は、その「一子相伝」の中埜家の当主と次代の当主が保有しており、中埜家の当主が代々、ミツカンの代表者となってきた。そして、中埜家による経営・支配を次代以降の血族に引き継いでいくことを”至上命題” としているという。
大輔さんとミツカンの跡取りである妻・Sさん(会長・副会長夫妻の娘)は、2012年に知人を介して知り合い、2013年5月に婚姻届けを提出。大輔さんは外資系金融機関の仕事をしていたが、Sさんが跡取りであることから、“婿入り婚” をして、ミツカンに入社した。2014年6月には、大輔さんは長男を妊娠中のSさんと渡英、ミツカン英国支店での勤務となった。
同年、Sさんは無事に長男を出産。ところが生後4日、ロンドンに来た会長・副会長夫妻は、大輔さんの目の前に養子縁組の書類を広げ、産まれたばかりの長男を夫妻の養子にするよう迫ってきたという。大輔さんは「まだ(赤ちゃんの)名前も決まっていないのに、一晩考えさせてください」と答えた。それが夫妻の逆鱗に触れたのだという。
その時は、会長夫妻は大輔さんに対し、「養子縁組は税金対策のためであって、親子を引き離すための書類ではない」と言っていたが、裏ではその前から弁護士らと「親権を奪え」と合議していたのだという(録音データあり)。「子どもをだまし取ろうとしていたのが明らか」と大輔さんは憤る。
そこから大輔さんは、当時のロンドンの自宅から追い出され、大阪に配転させられるなど、社内の人事権も使った異常なまでの嫌がらせによって、親子・夫婦関係をともに引き裂かれた。会見では「息子と生き別れて3年、どこにいるのか、生きているかどうかもわからない」と明かした。
単独親権制の日本と共同親権制の英国
日本は、1994年に「子どもの権利条約」を批准しており、その第9条には「親と引き離されない権利」として、 子どもには、親と引き離されない権利があり、子どもにとって良い状況の場合は引き離されることも認められるものの、その場合は、親と会ったり連絡したりすることができると明記されている。
2017年、大輔さんは日本の家庭裁判所に、イギリスにいる息子との面会交流を申し立てたが、「半年に1回1時間、第三者の監視付きで」会うことができるとの判断が下された。単独親権制の日本の家庭裁判所では、非親権者である別居親の子供との面会は「月1回、3~4時間程度」が相場である。
離婚しても両親ともに子供の親権が持てる共同親権制のイギリスでも、同じ条件で裁判所に面会交流の申し立てを行った。すると、日本とイギリスの距離も考慮され「年に7回以上、宿泊を伴って会うことができる。テレビ電話を使って交流ができる。子供の学校のイベントなどにも参加できる」といった判断が下された。担当したイギリスの弁護士は、「もし仮に(大輔さんが)イギリスに移住すれば、隔週で週末に会える。バカンスの半分は一緒に過ごせる。子どもにとって両親はともに大事な存在だからです」と話していたという。
大輔さんは、「日本は子どもの権利を粗末にしている状況であると言わざるを得ない。先に連れ去った側が子どもを人質のように扱い、裁判などで交渉の材料に使うような状況。我が国は子どもの権利条約を守っていない状況であると言わざるを得ない」と嘆く。
イギリスでは、この「ミツカン父子引き離し事件」について大手タイムズ紙が報道するなどしており、フランス人の夫との間の子供を連れ去った日本人母にフランス当局が逮捕状が出した事件と同様(詳しくはこちら)、「子供の連れ去り」問題に対策を講じない日本に対して厳しい視線が注がれている。
大輔さんの裁判では、被告である会長・副会長側は「子供の引き離しは故意ではない。配転は正当な人事権の行使である」と主張している。
ミツカンの公式サイトには、初代又左衛門の「八か条の言置(いいおき)」が掲示されている。「夫婦は仲睦まじくせよ」「他人や召使いには無慈悲なことはけっしてしてはならぬ」…。初代又左衛門は、現・会長、副会長による夫婦・親子引き離しの所業を見れば、果たしてどう思うだろうか。
ミツカン社に聞いてみた
当事件についてミツカン社の担当窓口に聞いてみた。以下、一問一答。
Q:中野大輔さんの父子引き離しについて、社内ではどの程度共有されているのでしょう?また社としての見解はいかがでしょう?
A:その件につきましては、こちらからお答えすることはありません。
Q:ミツカンはポン酢など、「家族団らん」のイメージで売り出している商品が多いので、「親子引き離し」のイメージはまずいのでは?社内で(ブランドイメージの)対策はされていますか?
A:こちらからお答えすることはありません。
Q:係争中の案件だからということですよね。
A:そうですね。ただ、こういったご意見があったということにつきましては社内で共有させていただきます。
Q:お互いにとって良い結果になるように望んでいますので、頑張ってください、と言ったらおかしいですけど、頑張ってください。
A:ありがとうございます。
文字にしてしまうと冷たい対応にとられてしまうかもしれないが、
共同親権 日本に圧力 子連れ去り 外交問題化
出典:令和3年12月16日 読売新聞
日本人との国際結婚などの破綻に伴い、子どもを不当に連れ去られたと訴える外国人が後を絶たない。子どもを一方の親に会わせない状態は、欧米主要国などで犯罪行為とみなされる。日本に法改正を求める外交問題にも発展している。(国際部 佐藤友紀)
※以下、記事参照
仏当局、日本人女性に逮捕状 フランス人の夫が「子供の連れ去り」訴え
出典:令和3年12月1日 BBC
仏当局、日本人女性に逮捕状 フランス人の夫が「子供の連れ去り」訴え
フランスの司法当局は、子供2人をフランス人の父親から引き離したとされる日本人の妻に対し、親による誘拐などの容疑で国際逮捕状を発行した。AFP通信が30日に報じた。
この事案は、結婚生活が破綻した場合の共同親権という概念がない日本において、「親による誘拐」をめぐる議論を再燃させた。
フランス人のヴァンサン・フィショ氏は、日本人の妻が3年前に2人の子供を連れて東京の自宅から姿を消して以来、子供に会えていないと訴えている。
フィショ氏は今年夏に東京オリンピックが開催される中、3週間のハンガーストライキを行い国際的注目を集めた。
日本の法律には、結婚生活が破綻した場合に夫婦が親権を共有することについての規定がない。
日本の当局は、一方の親が、もう一方の親と子供の接触を妨害しても見て見ぬふりしていると批判されている。人権団体の推計によると、日本では毎年約15万人の18歳未満の子供たちが親と強制的に引き離されているという。
フランス当局の逮捕状は、フィショ氏の妻が未成年者を危険にさらしたともしている。
フィショ氏の妻の弁護人はAFP通信に対し、「離婚手続きが進行中であり、法廷外で争うつもりはない」と述べた。
(英語記事 France issues warrant over Japan 'parental kidnap')
仏・日本人妻に逮捕状「子供連れ去った疑い」
出典:令和3年12月1日 TBSNEWS
フランス・パリの裁判所は、フランス人男性との結婚生活が破綻した日本人の妻が子供2人を男性に会わせないのは未成年者略取の疑いがあるとして、妻の逮捕状を出しました。
東京に住むフランス人ヴァンサン・フィショさんは、日本人の妻との結婚生活が破綻し、妻が息子と娘を連れ去ったため、子供と3年以上会えていないと訴えています。フィショさんはおととし告訴、パリの裁判所は11月30日までに、未成年者略取容疑などで妻の逮捕状を出しました。2人は現在、日本で離婚手続き中だということです。
ヴァンサン・フィショさん
「未成年者略取容疑で逮捕状が出ている母親に、裁判官が親権を与えるようなことがあれば、おかしいと思います」
一方、妻の弁護士はAFP通信の取材に対し、「法廷外で争うつもりはない」と話したということです。
仏当局が日本人女性に逮捕状 フランス人の夫が子の「連れ去り」訴え
出典:令和3年12月1日 朝日新聞DIGITL
仏当局が日本人女性に逮捕状 フランス人の夫が子の「連れ去り」訴え
記事PDF
フランス人の夫に子どもを会わせていないとして、フランスの司法当局が妻の日本人女性に対し、子どもを連れ去った疑いがあるなどとして逮捕状を出したことがわかった。30日、AFP通信が報じた。
同通信によると、夫は日本に暮らすバンサン・フィショさん(39)で、2019年に仏当局に告訴していた。この夏には、東京五輪が開催されるのにあわせ、3週間のハンガーストライキを決行。6歳と4歳の子どもへの面会を求めている。逮捕状の発行で、女性がフランスに入国すれば、逮捕される恐れがある。
AFP通信によると、フィショさんは女性が日本で逮捕されることを望んでいるわけではなく、日本の裁判所の離婚手続きで親権を決める際、逮捕状が妻に出ていることを考慮してもらうことを期待しているという。
離婚後の子どもの養育をめぐっては、欧米では父母の双方が親権を持つ「共同親権」が主流だが、日本で父母のどちらかしか親権を持てない「単独親権」だ。国際結婚が破綻(はたん)して子どもを日本に連れ帰ることで、子どもを連れ去ったとして犯罪とみなされるケースも起きている。(パリ=疋田多揚)
仏裁判所が日本人女性に逮捕状…国際結婚が破綻、子供の面会許さない「連れ去り」容疑
出典:令和3年11月30日 読売新聞
仏裁判所が日本人女性に逮捕状…国際結婚が破綻、子供の面会許さない「連れ去り」容疑
【パリ=山田真也】AFP通信は30日、フランスの裁判所が、日本に住んでいる仏男性と日本人の妻との結婚生活が破綻した後、妻が子供2人を連れ去って男性に面会させないのは略取容疑などにあたるとして、逮捕状を出したと報じた。
仏男性は子供と会えない状況が続いているといい、2019年にフランスで刑事告訴していた。両親は離婚に向けた手続きを進めているという。
日本では、父母双方が離婚後に親権を持つ「共同親権」が認められていない。日本人が国際結婚の破綻に伴い、相手の子供との面会を拒否することが、欧米などでは「連れ去り」として問題視されるケースがある。
日本人女性に逮捕状 「子連れ去り」容疑―仏
出典:令和3年11月30日 時事通信
【パリ時事】フランスの司法当局は、日本に住むフランス人のバンサン・フィショさん(39)の妻が、夫婦関係破綻後に子供を連れ去ってフィショさんに会わせないのは未成年略取容疑などに当たるとして、日本人の妻に逮捕状を出した。AFP通信が30日、報じた。
AFPによると、フィショさんは息子(6)と娘(4)と3年以上会っておらず、連絡も取れない状況だという。フィショさんは2019年、パリで刑事告訴。20年末に捜査が開始された。
妻の弁護士はAFPに対し、「離婚手続きが進行中であり、法廷外で争うつもりはない」と説明。逮捕状に関するコメントは避けた。
仏当局、日本女性に逮捕状 両国籍の子連れ去り容疑
出典:令和3年11月30日 東京新聞
仏当局、日本女性に逮捕状 両国籍の子連れ去り容疑」
記事PDF
パリの裁判所は30日までに、東京在住のフランス人男性(39)と日本人の妻の結婚生活破綻後、妻が子どもたちを連れ去って男性に会わせないのは略取容疑などに当たるとして、妻の逮捕状を出した。関係者が明らかにした。日本人の片方の親が子を連れ去り、欧州連合(EU)市民の親に会わせないケースの多発は日欧間の主要外交問題だが、逮捕状発付は異例。
事件は男性が2019年に告訴。連れ去られた長男(6)と長女(4)は日仏両国籍を持つため、フランス当局に捜査権限があるという。男性は警視庁にも立件するよう求めたが、妻が子どもを連れて別居するのは普通のことだとして退けられた。
仏当局、日本女性に逮捕状 両国籍の子連れ去り容疑
出典:令和3年11月30日 共同通信
パリの裁判所は30日までに、東京在住のフランス人男性(39)と日本人の妻の結婚生活破綻後、妻が子どもたちを連れ去って男性に会わせないのは略取容疑などに当たるとして、妻の逮捕状を出した。関係者が明らかにした。日本人の片方の親が子を連れ去り、欧州連合(EU)市民の親に会わせないケースの多発は日欧間の主要外交問題だが、逮捕状発付は異例。
事件は男性が2019年に告訴。連れ去られた長男(6)と長女(4)は日仏両国籍を持つため、フランス当局に捜査権限があるという。男性は警視庁にも立件するよう求めたが、妻が子どもを連れて別居するのは普通のことだとして退けられた。
離婚後の共同親権、静岡県内賛否 法制審、8月中間試案
出典:令和4年7月13日 静岡新聞
離婚後の父母の双方に親権を認める「共同親権」を導入する案などを盛り込んだ家族法制の見直しに関する中間試案を、法相の諮問機関である法制審議会の家族法制部会が8月にも取りまとめる。静岡県内では親権を失った別居親を中心に共同親権の実現を求める動きが活発化しており、推進派、反対派の双方が「正念場」と法制化の行方を注視している。
「親として、子に関わりたい」。県東部の別居親の50代男性は思いを吐露した。家庭裁判所の審判で定期的な面会交流の約束をしたが、子どもと2年以上会えていない。
2020年に全国の別居親らと「単独親権制により人権侵害を受けている」として国に損害賠償を求める集団訴訟を東京地裁に起こした県東部の40代男性は、新型コロナウイルスの感染拡大で面会が制限されるなど影響を感じていて、「法的な枠組みを変えないと、親なのに部外者扱いのまま」と話す。
静岡県内には別居親の活動組織として「静岡親子の会」「浜松親子の会」があり、計40人が参加する。地方から声を上げる全国運動と連動し、県や市町の議会に国への意見書提出を求める活動に取り組む。「面会交流支援に必要な法整備」や「共同養育の実現」などを盛り込んだ意見書案は昨年9月までに、県議会や静岡市議会など八つの議会で採択された。
一方、単独親権者であるひとり親の支援団体からは「中間試案は共同親権ありきで、当事者の実態を踏まえていない」との指摘がある。静岡市の支援団体「シングルペアレント101」は「離婚で両親の対立から免れた子どもたちが、共同親権導入によって再び渦中に引き戻され、葛藤にさらされる」と懸念を示す。
家族法制部会の中間試案は、共同親権を原則とする案と、現行民法の単独親権を維持する案の両論併記になる見通しだ。共同親権について部会は①父母双方が合意した場合②裁判所が子の利益に必要と判断した場合―などで認めるケースを想定する。中間試案の取りまとめ後、パブリックコメント(意見公募)を経て答申案を決定する。
<メモ>厚生労働省の人口動態統計によると、2020年に婚姻した夫婦は52万組あり、離婚した夫婦は19万組と、約3組に1組が離婚している。日本は民法で婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権制度を採る。
フランス当局が日本人妻に逮捕状発行で注目の”連れ去り”離婚訴訟 敗訴の夫側は
出典:令和4年7月7日 デイリー新潮
フランス当局が日本人妻に逮捕状発行で注目の”連れ去り”離婚訴訟 敗訴の夫側は
夫側の母国であるフランス司法当局が「実子を誘拐した」として日本人妻に逮捕状を出したことで注目を集めた離婚訴訟の判決公判が7月7日、東京家庭裁判所で開かれた。裁判所は妻側が訴えていたDVについては認定しなかったが、親権を妻に定める従来通りの判決を言い渡した。(ライター・上條まゆみ)
***
フランス大使館職員も傍聴
「主文。原告と被告とを離婚する。原告と被告の間の長男および長女の親権者をいずれも母である原告と定める」
東京家庭裁判所141号法廷。裁判長の判決言い渡しを、被告の在日フランス人のヴィンセント・フィショさんはみじろぎせず聞いていた。傍聴には、被告側の支援者やフランス大使館職員も駆けつけた。一方、妻側は弁護士も含めて欠席した。
ヴィンセントさんは昨年の東京五輪期間中に国立競技場前で「連れ去り被害」を訴え、3週間のハンガーストライキを敢行したことで注目を浴びた。4年前、離婚問題について話し合いをしている最中、妻が黙って二人の子供を連れ去ってしまったというのがヴィンセントさん側の訴えだ。
一方、妻側は夫によるDVから逃れるために仕方なく取った避難行動であったと主張。妻側が離婚を求めて起こした訴訟で、親権が争われていた。判決では親権は妻に定められたが、妻側が主張していたDVについては認められなかった。
昨年11月、フランス司法当局が日本人妻に対して「未成年者拉致の罪」(未成年者略取及び誘拐)と「未成年者を危険にさらした罪」で逮捕状を発行したことでもより大きな注目を集めた今回の判決公判。判決後に司法記者クラブで開かれた会見には、「ル・フィガロ」「ル・モンド」などのフランス主要メディアも駆けつけた。
「子供たちも負けたのです」
会見でヴィンセントさんは判決への不満をこう訴えた。
「裁判で負けたのは私だけではない。私の子供たちも負けたのです。子供たちは父親なしで生きていかなければならない。なぜ裁判所は、私がDVをしていないとしながらも『連れ去り』を見逃すのでしょうか。フランス政府が要請し、インターポール(国際刑事警察機構)から逮捕状も出ている妻に親権を認めるのか。納得できません。控訴して戦います」
会見に同席した上野晃弁護士はこう述べた。
「今日、夫のDVはなかったと認められた。つまり、妻は理由もなく子供を連れ去ったことになる。にもかかわらず、子供の連れ去りについての評価はスルーされたのです。今、法制審議会で親権問題が議論されている中に、子供の連れ去り問題も入っています。裁判所がこの問題にまったく頓着しない判決を出したことに、私たちは大いに失望しています」
離婚トラブルの温床と言われる「単独親権」
離婚後のトラブルが絶えない温床になっているのが、日本の親権制度である。現状、日本は父母のどちらかが親権を持つ「単独親権」。世界の先進国のほとんどは、離婚後も子供の親権を父母がもつ「共同親権」。日本でもこの「共同親権」を導入すべきだという声が高まっている。
親権というと、いかにも親の「権利」のようだが、親が果たすべき責任とも言える。離婚後も子どもが両親から経済的、精神的支援を受けながら育つことが子供の最善の利益につながるという考え方が「共同親権」を求める声の背景にある。1994年に日本も批准している「国連子どもの権利条約」には、「子供が父母と引き離されないことを確保する」と示されている。
一方、共同親権になってしまうと、離婚をするほど仲の悪い両親の間に挟まれた子供が不利益を被る、あるいはDV親との縁が切れず子供が危険にさらされるという意見もある。故に、断固として共同親権に反対する声は大きい。
法制審議会で進む議論
現在、法務省内の法制審議会家族法制部会において、父母の離婚後等の親権者に関する規律等についての議論が進んでおり、今夏に中間試案が公表される予定だ。部会資料によれば、中間試案では「共同親権」という文言は採用されているものの、選択的共同親権の採用や単独での監護権を認めており、「骨抜き」になる可能性が高い。そうなると、これまでと同様、別居親との親子断絶や監護権を有利とするための子どもの連れ去りは防げない。
そこで立ち上がったのが、国内外の研究者や弁護士らでつくる民間団体だ。テレビ等でも活躍する北村晴男弁護士が部会長を務める。「法制審の案は、婚姻中の家族のあり方まで変更する恐れがある」として、独自に取りまとめた中間試案を自民党の高市早苗政調会長に提出した。団体側は、法制審の部会が発表する試案と団体側の試案を与党内で比較・審査したうえで、欧米諸国や韓国、台湾などが採用している離婚後の「共同親権・共同監護」制度を創設するよう求めた。
離婚後の単独親権、それを発端とする子どもの連れ去りについては、諸外国からも強く非難されている。2020年にはEU議会が日本に対し「子の連れ去りに関する国際的なルールを遵守していないように見受けられる」と非難決議を表明している。
=========
上條まゆみ(かみじょう・まゆみ) ライター。東京都生まれ。大学卒業後、会社員を経てライターとして活動。教育・保育・女性のライフスタイル等、幅広いテーマでインタビューやルポを手がける。近年は、結婚・離婚・再婚・子育て等、家族の問題にフォーカス。現代ビジネスで『子どものいる離婚』、サイゾーウーマンで『2回目だからこそのしあわせ~わたしたちの再婚物語』を連載中。
「子どもの連れ去り」訴えたフランス人夫に親権認めず 東京家庭裁判所判決 妻に逮捕状など国際問題に
出典:令和4年7月7日 TBS NEWS DIG
「子どもの連れ去り」訴えたフランス人夫に親権認めず 東京家庭裁判所判決 妻に逮捕状など国際問題に
日本人の妻が別居の際に無断で子どもを連れて出て行ったのは「子どもの連れ去りだ」としてフランス人の夫が訴え国際的に問題になっていた夫婦の離婚訴訟で東京家庭裁判所は子どもの親権を日本人の妻に認める判決を言い渡しました。
この裁判は、日本人の妻が都内に住むフランス人の夫に対する離婚と、その後の子どもの親権などを東京家庭裁判所に訴えていたものです。妻側は「夫による妻へのDVや子どもへの厳しいしつけがあった」「妻が一貫して育児を行ってきた」として2人の子どもの親権を主張しDVなどを否定する夫側と争っていました。
東京家庭裁判所はきょう午後の判決で、妻が訴えていたDVについて主張については「暴行された事実は認められない」としたものの、「子どもたちの発育は順調で、妻の監護状況に特段の問題は見られない」という裁判所の調査官の意見をもとに子ども2人の親権者を妻とする判決を言い渡しました。一方で調査で子どもが夫に対して否定的な感情を示さなかったことから「妻が夫と子らとの面会交流を妨げていることは問題である」とも指摘。しかし離婚後も父親と母親が親権をもつ共同親権の制度が認められていない日本では「面会交流は今後2人が協議や調停などを通じて実現していくべき」としました。夫は妻が子どもを連れて家を出ていったことについて「一方的な連れ去りで一度も会うことができず連絡も取れていない」と訴えていました。
未成年者略取にあたるとした夫の告訴をうけ、フランス司法当局は去年、妻の逮捕状を出したほか、AFP通信によりますと去年7月、オリンピックで来日したフランスのマクロン大統領が日本政府に問題提起をするなどしていました。
日本では離婚後どちらか片方の親が親権をもつ「単独親権」が定められていますがフランスなど欧米では共同親権が主流です。また子どもを片方の親が、もう一方の同意なく連れ去ることを認めないケースも多いため、日本人との国際結婚が破綻した際「日本人の配偶者に子どもを連れ去られた」という訴えが後を絶たず、外交問題となっています。
子連れ別居日本人妻に親権 仏男性が争い、東京家裁
出典:令和4年7月7日 産経新聞
日本人の妻が子2人を連れて家を出て、子と面会させないと抗議してきたフランス人のバンサン・フィショーさん(40)=東京都内在住=が、妻と親権などを争った訴訟の判決で、東京家裁は7日、妻に親権があると判断した。一方で妻が面会交流を妨げていることは問題だと指摘した。妻が訴訟を起こし、離婚も認めた。フィショーさん側は控訴するとしている。
この問題を通じ、日本人と欧州連合(EU)市民の国際結婚が破綻し、日本人の親が子に面会させないケースがクローズアップされ、外交問題になっている。日本は海外主要国と異なり、離婚後に両親双方が親権を持つ「共同親権」を認めていない。小河原寧裁判長はこの現状を踏まえ、2人が協議などをして子の福祉を慎重に模索するよう求めた。
判決などによると、2人は平成21年に結婚し都内で生活。30年8月、妻が子を連れて出て別居が始まった。フィショーさんは子を連れ去られたと訴え、パリの裁判所は昨年10月、逮捕状を発付し、妻は国際指名手配を受けている。
子連れ別居の日本人妻に親権、東京家裁 国際結婚破綻で
出典:令和4年7月7日 日本経済新聞
別居している日本人の妻が連れて出た子2人に面会させないとして、フランス人の夫、バンサン・フィショーさん(40)=東京都内在住=と妻が親権などを争った訴訟の判決で、東京家裁は7日、妻に親権があると判断した。
妻が離婚を求めて提訴した。家裁は離婚も認めたが、一方で、妻が面会交流を妨げていることは問題だと指摘した。夫側は判決後、控訴すると明らかにした。
判決などによると、2人は2009年に結婚し都内で生活。18年8月、妻が子を連れて出て別居が始まった。夫は子を連れ去られたと訴え、パリの裁判所は21年10月、逮捕状を発付し、妻は国際指名手配を受けている。
夫側は、妻が親権者になれば国際的な批判が免れないなどと訴えたが、判決は妻の監護状況に問題はなく「不適格ではない」と結論付けた。夫に暴行されたとの妻側の主張は認めなかった。
日本人と欧州連合(EU)市民の国際結婚が破綻し、日本人の親が子に面会させないケースは国際問題化している。日本は海外主要国と異なり、離婚後に両親双方が親権を持つ「共同親権」を認めておらず、法制審議会(法相の諮問機関)で共同親権導入の是非を含めた議論が始まっている。
小河原寧裁判長はこうした現状を踏まえ、2人が協議などをして子の福祉を慎重に模索するよう求めた。〔共同〕
離婚後の「共同親権」導入は是か非か、歓迎論と慎重論が交錯
出典:令和4年6月26日 FNNプライムオンライン
家族法制の見直しについて議論している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会に対し、法務省が6月21日「離婚した父母双方を親権者にできる『共同親権』の導入」案を提示した。日本では現在、離婚すると父母のどちらかに親権を与える単独親権の一択しかなく、熾烈な親権争いが繰り広げられる原因となっていた。
議論の結果は、8月にも民法改正の駐韓試案として取りまとめられる見通し。
こうした動きを受け、フジテレビ系『日曜報道 THE PRIME』(日曜午前7時30分)では、6月26日、有識者たちが「離婚後の共同親権」の是非について議論した。
ジャーナリストの櫻井よしこ氏は、「子どもの幸せ、健全な養育、成長を考えると絶対に共同親権にしなければいけない」と強調した。
弁護士の本田正男氏は、家庭内暴力(DV)や児童虐待がある家庭では、共同親権制度を採用した場合、被害の継続や拡大が危惧されることを念頭に、「反対というか、きちんと考えたほうがいい。個別的に考える必要がある」と述べ、離婚後の共同親権の導入に慎重な姿勢を示した。
タレントで羽衣国際大学現代社会学部教授のにしゃんた氏は、多くの国、とりわけ先進国では共同親権制度を採用していることを踏まえ、「当然、共同親権があるべき姿でもっとも理想的な形だ」と断じた。
離婚後の共同養育を支援している、しばはし聡子氏は離婚する夫婦が「共同親権」と「単独親権」を選択できる制度の導入を主張した。
以下、番組での主なやりとり。
松山俊行キャスター(フジテレビ政治部長・解説委員):
6月21日に法務省が法制審議会の部会に離婚後の共同親権導入などを盛り込んだ中間試案のたたき台を提示した。共同親権を導入すべきだと考えるか。
櫻井よしこ氏(ジャーナリスト、国家基本問題研究所理事長):
子どもの幸せ、健全な養育、成長を考えると絶対に共同親権にしなければいけない。問題点があれば、個々の問題として解決することが大事なのであり、父母がともに子どもに愛情を注ぎ、注意をし、養育し、励まし、時には叱り、そして子どもの成長を一緒に見届けるという意味での共同親権は本当に大事だ。
松山キャスター:
本田さんは共同親権に反対する署名活動もしている。なぜ反対するのか。
本田正男氏(弁護士):
反対というか、きちんと考えた方がよいと思っている。3点申し上げる。一点は家族の形は様々で共同親権になったらこうなるというような算数の問題を解くように簡単に答えが出るわけではない。非常に個別的に考える必要がある。2点目は、裁判所のインフラが非常に脆弱だ。日本の裁判所は米国のように非常に細かくは全くできない。丁寧にやれば裁判所に負荷がかかりすぎてしまい、できない。3点目だが、子どもは生まれた時は親なしでは生存できず、親のほうが子どもを自由に操作できるような感覚になり、勘違いしてしまう。どうしても子どもにプレッシャーを与えすぎてしまう感じになってしまう。もう少し子どもの意向が汲めるような状態を出さなければいけない。
しばはし聡子氏(共同養育サポートりむすび代表):
数々の懸念事項あるとは思う。離婚しても子どもにとり親が二人であるというすごく当たり前のことを浸透させるという意味でも共同親権が選択できる制度を導入するべきだ。ただ、両方選択できるというときに逆に親権を巡って争う構造になることが懸念される。
にしゃんた氏(タレント、羽衣国際大学現代社会学部教授):
当然、共同親権があるべき姿であり、もっとも理想的な形だ。現状は「三方良し」になっていない。親権を持つ片親だけが喜び、往々にして子どもと親権のない親が泣き寝入りしている。「両親良し、子どももよし」、あるいは、「子ども良し、親も良し、社会も良し」までもっていく必要があり、今回良いチャンスが巡ってきているのではないか。
櫻井氏:
裁判官、司法の方が、裁判官を増やすことにずっと反対してきたという実態があり、裁判官の数が足りない現実がある。裁判官が足りない現実に合わせて子どものことを、家庭のことを今の歪な単独親権の形にしておくのは、本末転倒で子どものことを考えていない議論だ。
松山キャスター:
共同親権を考える上でDVの問題がある。DVが本当にあったのか、あるいは、DVがあったと主張した場合の子どもの親権をどう考えるか。
しばはし氏:
身体的暴力は割と白黒が分かりやすい。多分一番ここで問題になっているのがモラハラと言われる精神的なDVだ。それは夫婦間ではすごく尺度が違い、指標がない。DVをされたと訴える母親、DVはしていないという父親というのはよくある。どちらが嘘をついているわけでもなく、それぞれが違う物語だというところがある。モラハラはDVだから子どもを合わせないほうがいいと決めてしまうのはちょっと行きすぎだ。一方で、実際に本当に精神的なDVを受けて相手と関わるのが難しい方については、第三者の支援を入れるなりして、子どもをきちんと面会させるという部分は切り分けて考えていく必要がある。
松山キャスター:
DVが実際にあったかどうかを認定できる制度が日本に整っているかかという問題がある。
櫻井氏:
男が子どもを連れさられて、妻からDV夫だと言われる。本人はもうびっくりする。DVした記憶はない。暴力的にもない、言葉の上でもやった記憶はないのにDV夫だと言われ、子どもを連れさられて、離婚になり、親権を取られて、十何年も子どもに会えていない。最高裁まで争ったケースだ。あなた(山田氏)は妻の側に立った弁護士の一人だ。最高裁まで行って夫のDVは認められなかった。DVをされたという申告だけで日本ではDV夫、DV妻だ。DVは絶対許してはならないことは確かだ。DVをした夫や妻はきちんと罰せられるべきだ。DVは本当にあったのかということについて欧米などではすぐに警察を入れる。DV助けてくださいと言えば、すぐに来て現場で当事者の話を聞いたり、近所の話を聞いたりして事実認定をする。DVがあれば夫を家から放逐するとか、妻や子どもに接触させないなどの罰がある。日本では片親がいない間にもう一人の片親が子どもを連れて逃げ、DVがあったと申し立てるケースがある。DVが本当にあったかについて客観的な第三者が調査する仕組みを確立していかなければフェアではない。
本田氏:
もちろん殴るなどは論外だが、子どもにプレッシャーを与えてしまうことがある。精神的な部分で目に見えない。言葉により目に見えないとしても、さまざまなトラウマを抱えている人はいっぱいいる。私の依頼者の中で40歳になっても50歳になっても親子関係の葛藤に苦しんでる人は大勢いる。DVというと典型的な殴る蹴るだけではない。もう少し幅広く精神的なダメージを与えるような有害な状況が家庭の中にある場合があるというところを見てもらいたい。
松山キャスター:
共同親権か単独親権かを選べるようにするという考えも出てきてた。
櫻井氏:
共同親権を基本にするというところをはっきりさせたほうがいい。片方の親が性犯罪をしたとか、DVをしているとか、どうしても許せない状況がある場合は、もう片方の親に任せるという意味の単独親権があっていいとは思う。けれども、法体系としては共同親権を基本とするところに軸足を置かないと。法務省の提案にも一応、共同親権という言葉は入っているが、これはものすごく狭い範囲の共同親権だ。学校をどこにするか、何か大きな病気をした時の治療法をどうするか。共同親権は父母両方が子どもに関わり、時間を共に過ごし、子どもの顔を見ながら、子どもの声を聞きながら、子どもの心理を推測しながら、本当にそこに大人の親としての愛情や配慮を注いでいくということが共同親権だ。どこの学校にするか、大病したからどうするか、宗教をどこにするか、キリスト教にするか、仏教にするのかを決めるときに共同親権と言っているが、それはごく一部のことだ。法制審の華族制度部会の委員にはすごくリベラルな人権派と言われる人たちがいて、その人たちが主導してシングルマザーだけを応援するというような傾向がなきにしもあらずだ。シングルマザーの応援はとても大事だと思うが、もっと視野を広げて、子どもの幸せ、子どもの健全な育成を考えたところに、わが国の法律は立脚しないといけない。その意味では、共同親権か一部単独親権かではなく、「原則共同親権」だ。しかし、どうしても親に問題があるときは、これは単独親権だね、という工夫がなされるような法制度にしないといけない。
本田氏:
結局調整のところで揉めてしまう。例えば、学校の話があったが、横浜市の隣にあるA小学校とB小学校のどちらに入るかでもめている。相手方代理人は「裁判所で決着すればいいのではないか」と言う。そんなこと言ったら4月になってしまう。本来は二人が調整できることが大前提だが、イコールの関係がないとただもめるだけだ。そのもめる家庭の嵐の雨風を浴びるのは子どもだ。離婚で裁判になるのなんて1%ほどだが、結局我々(弁護士)のところに来るようなのはものすごい嵐が吹いているような状態なので、むしろそういう状態から切り離されている方が子どもにとっては幸せなのではないか。
しばはし氏:
実際、裁判所を通して離婚調停などを行っていくと別居前よりも関係が悪化する事例がよくある。どちらが親権をとるかもそうだが、離婚は破綻主義ではなく有責主義となると、相手が悪いから離婚すると。書面で相手の批判をしていく。そうなると別居前よりもより関係が悪くなって離婚後にとても共同養育できるような関係にならないというケースもある。むしろ大事なことは、親権をどちらにするか選択することよりも、別居後にすぐに子どもと会える環境をまず制度として作ること。離婚後も共同養育できる関係性をつくっていくために例えば裁判所にカウンセリングの制度を設けるなど、そういう環境をつくっていくことの方が大事だ。
議論沸騰「共同親権問題」 あの「行列」の顔「北村晴男弁護士」が本気で取り組むワケ
出典:令和4年6月22日 デイリー新潮
議論沸騰「共同親権問題」 あの「行列」の顔「北村晴男弁護士」が本気で取り組むワケ
共同親権――離婚後も両親が子供の親権を持ち、それぞれが子を見守り、監護すること。先進国の多くで採用されている制度だが、日本は、離婚すると親権はどちらか一方にしか認めない「単独親権制」を採用している。これにより、共同親権を採用する国の人と日本人が国際結婚して子供をもうけ、離婚する場合、日本人親が突然子供を連れて帰国し、残された親が「誘拐罪」で日本人親を告訴するケースが後を絶たない。こういう子の連れ去り行為は国際的には誘拐罪に他ならず、日本は「拉致国家」との強い非難を受けている。
そのため、「共同親権の導入を」と、国際的な圧力が高まるなか、日本でも導入すべきか議論する動きが出ている。しかし――。
異例中の異例
制度改正の議論を行っているのは、法務省の諮問機関、法制審議会の「家族法制部会」。昨年3月にスタートし、今夏、中間試案が発表される見込みだが、この試案を巡って動いたのが、日本テレビの人気番組「行列のできる相談所」でもおなじみの、北村晴男弁護士(66)、そして彼が率いる「民間法制審議会家族法制部会」という団体だった。この団体が先月31日、法務省の部会版とは異なる、独自の試案を作成し、自民党に提出。比較して議論を進めるよう高市早苗政務調査会長に提言した。
法務省担当記者が言う。
「法務省の法制審があり、審議を進めているにも関わらず、それとは別に、民間団体が独自の法制審を立ち上げ、提言を行うなんて、異例中の異例です。しかもあの人気弁護士の北村先生が旗振り役なので話題になりました」
なぜ「行列」のあの人が動いたのか。北村弁護士ご本人に、直接話を伺った。
――共同親権問題に取り組むようになったきっかけは。
「長いこと弁護士業務をするなかで、何度も、単独親権制の問題点を痛感させられてきました。例えば、妻の浮気など圧倒的に妻の責任で離婚に至るケースで、妻が子を連れて別居してしまう。その後、離婚の協議に入るわけですが、夫は私に、『先生、妻の浮気が原因ですから、当然、子供の親権はとれますよね?』と言う」
日本はこんな法律でいいの?
「でも、日本は単独親権制で、その上、裁判所には『小さな子供には母親が必要』という認識があり、監護実績を重視するという判断基準もあるため、父親が親権を取るのは、ほとんど不可能。『それでもお願いします』と言われるものの、結局親権を取れずに、月に1度、数時間程度の面会交流を確約してもらうために、相場よりも高い養育費を払うことになるわけです。おまけに、犯罪者でもないのに、第三者による監視付き面会とせざるを得ないことも多い。これにより、親権を奪われた側の祖父母は孫と全く会えなくなる。諸外国の共同親権制度では、両親や祖父母は子の成長をずっと見守る事が出来、子供も多くの大人に見守られ、愛情をたっぷりと注がれながら成長することが出来る。法律家として、仕事はするけど、そもそも、日本はこんな法律でいいの? という疑問が、ずっと頭にありました。単独親権制は、親子関係を破壊し、子供、親権を奪われた親、祖父母など多くの人の幸せを奪う、とんでもない悪法です。
そんな中、今年に入って、ある弁護士さんがうちの事務所にいらして、この方が共同親権の実現を目指して一生懸命やっておられる方で、『是非とも応援してほしい』と言われ、微力ながら、力になれればと思った次第です」
夫婦喧嘩でも……
――法務省の法制審が公開しようとしている試案の、どの点が問題なのでしょうか。
「まず、一番の問題は、父親と母親が合意したら共同親権を認める、という点です。『子供を元配偶者に合わせたくない』という親は合意しませんから、この制度ではこれまで同様、不幸な子供、不幸な親、絶望する祖父母を生み出し続けることになります。原則共同親権とする制度にしないと全く意味がない。そして二つ目は、監護権と親権を切り離したうえで、監護は単独で行います、というところ。監護、つまり、一緒に住んで見守る権利は一方にしか与えられない。そして、子供がどこに住むかを決める居所指定権も、監護権に付与する、と。こうなってしまうと、これは、今問題になっている“子の連れ去り”を合法化するための巧妙な仕掛けです。しかもですよ、その監護権を、婚姻中にもどちらか片方に付与することができるように議論を進めている節がある。夫婦喧嘩をし、かっとなったどちらかが訴えると、監護権を片方にのみ設定できるわけで、現行法よりもさらに早く親子関係を破壊する可能性が高い」
子供の幸せに責任を
――北村先生たちが提案している試案について教えてください。
「まず、離婚後も原則共同親権とします。未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、子供を父母がそれぞれどういう割合で監護するかなどについて具体的に定めた計画、『共同監護計画』の提出を義務付けよう、というのが基本です。離婚する二人の事情は様々ですから、多様な場面に対応可能なガイドラインも作成します。当然ながら、DV被害者を守るための制度設計も重要ですからそれについても十分に検討しています。
さらに、我々が提案しているのは、離婚するのであれば、子供の心理について講座を設けるので勉強してください、と。例えば、片親疎外症候群というのですが、一泊二日で父親の元に行き、母親のところに帰って来たとします。そして子供が『楽しかったよ』と報告したときに、母親が顔を曇らせると、大好きな父親を嫌いにならなければいけない心理状況に追い込まれることになる。その結果本当に父親を毛嫌いするようになるケースもある。そうした複雑な心理環境に子供を追い込むのは子の虐待に等しい。そういうことをきちんと勉強して、共同監護をしましょう、ということです。親の都合で離婚するわけですから、それによる子供への精神的負担を出来る限り軽減し、子供の幸せに最大限責任をもちましょうよ、と。共同親権を導入している先進国の制度を参考に、作成しました。どちらの案が、子供の幸せ、親の幸せに結びつくかは火を見るより明らかだと私は思っています」
二つの試案は、法改正にどのような影響を及ぼすか――。
デイリー新潮編集部
自民プロジェクトチームが共同親権提言 「家族の分断ないように」
出典:令和4年6月22日 中日新聞
自民プロジェクトチームが共同親権提言 「家族の分断ないように」
民法の家族法制のあり方を検討してきた自民党のプロジェクトチーム(PT)は二十一日、夫婦の離婚後、一方のみに認める親権制度を改め、双方が親権を持つ「共同親権」導入の提言書を古川禎久法相に提出した。「家族の分断」を生じさせない法制を求めるとした。
※以下、記事を参照ください。
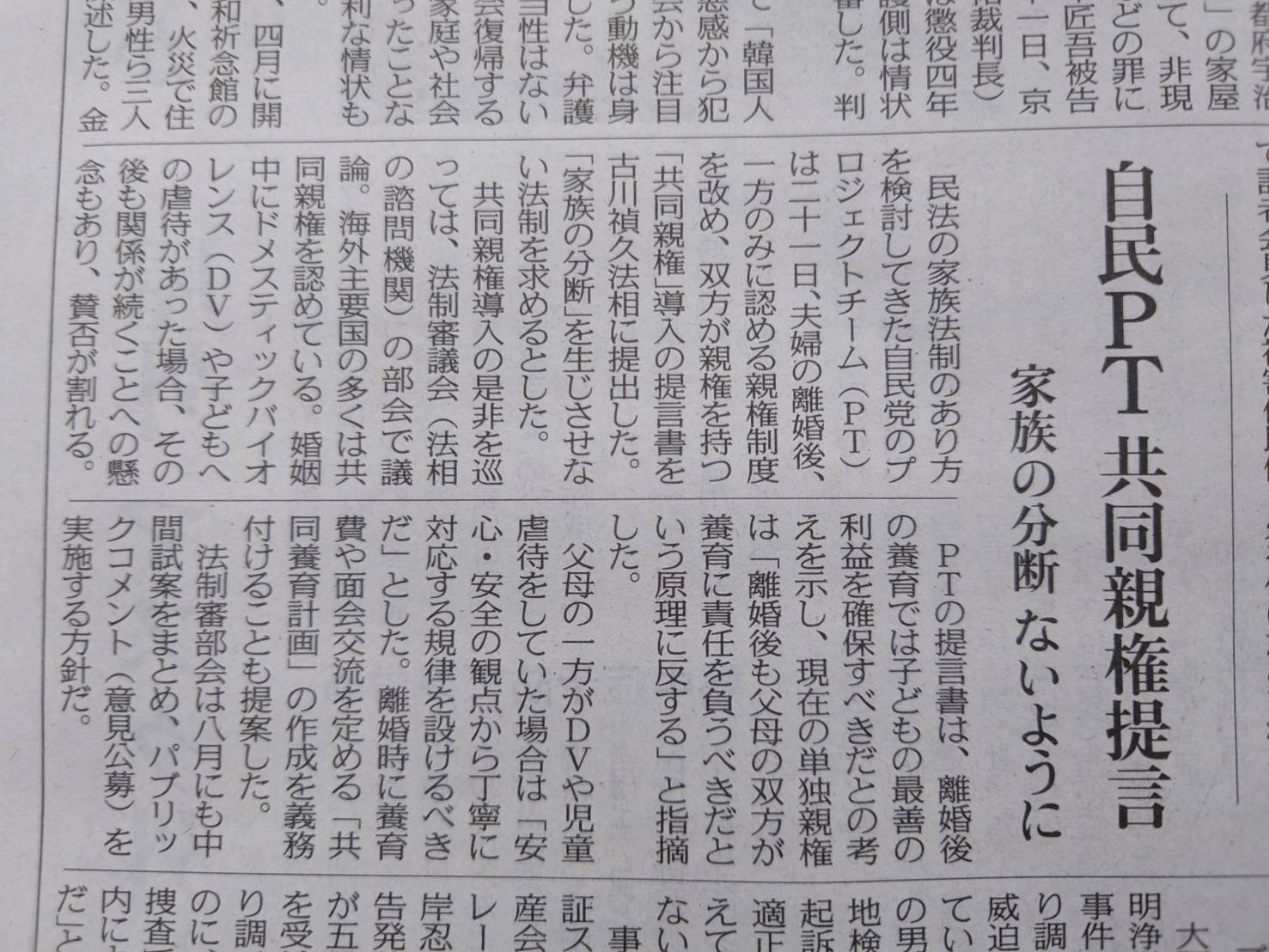
離婚後の「共同親権」導入へ試案 法制審、8月末にも
出典:令和4年6月22日 時事通信
家族法制の見直しについて議論している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は、離婚後も父母の双方に親権を認める「共同親権」導入などを盛り込んだ中間試案を8月末にも取りまとめる。中間試案は、共同親権を原則とするか、現行民法の「単独親権」を維持するかの両論併記となる見通しだ。
民法は、父母の婚姻中は共同で親権を持つが、離婚する場合はどちらか一方を親権者と定める「単独親権」制度を規定している。
厚生労働省の人口動態統計によると、2020年に婚姻した夫婦約52万組に対し、離婚した夫婦は約19万組。約3組に1組が離婚に至っている状況があり、離婚後の養育費未払いが社会問題となっている。また、共同親権が一般的な欧米諸国と日本の親権制度の違いから、国際結婚が破綻した日本人の親による「子ども連れ去り」問題も指摘されている。
こうした近年の家族の状況を受け、法制審部会では、共同親権を認める際は(1)父母双方が合意した場合(2)裁判所が子の利益のため必要があると判断した場合―などを想定。離婚後に日常の世話や教育の仕方について決める「監護権」を持つ「監護者」については、父母双方が共同で監護者となる選択肢も検討する。法制審は中間試案の取りまとめ後、意見公募(パブリックコメント)を経て答申案を決定する。
共同親権をめぐっては、自民党法務部会も21日、制度導入を求める提言書を古川禎久法相に提出した。離婚後の養育費負担や面会交流などについて定める「共同養育計画」の作成などを義務付けることも提起した。
離婚後の共同親権を提言 自民・法務部会 「子の最善の利益確保」
出典:令和4年6月21日 毎日新聞
離婚後の共同親権を提言 自民・法務部会「子の最善の利益確保」
自民党法務部会は21日、父母の離婚に伴う子の養育を巡る法制度の見直しについて、提言書を古川禎久法相に提出した。「離婚後の共同親権を導入すべきだ」としている。
同部会の「家族法制のあり方検討PT(プロジェクトチーム)」がまとめた提言書は、父母が離婚した後の子の養育について「子の最善の利益を確保するため、子を真ん中に置いた議論をしなければならない」と記載。離婚後の単独親権を定めた現行民法に触れ「原則として、父母がそれぞれ引き続き子に対して親としての責務を果たすため、離婚後共同親権制度を導入すべきだ」としている。
また、父母が離婚する場合に、子の養育費の負担や親子の交流について取り決める「共同養育計画」の作成を課すべきだと提案。一方で、家庭内暴力(DV)や児童虐待がある家庭を念頭に、子の安全や安心を確保する観点から「丁寧に対応する規律を設けるべきだ」としている。
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は現在、離婚後の親権のあり方を含めた家族法制の見直しを議論している。【山本将克】
共同親権の制度 導入すべき” 自民の作業チームが法相に提言
出典:令和4年6月21日 NHK
“共同親権の制度 導入すべき” 自民の作業チームが法相に提言
離婚後の子どもの養育の在り方などをめぐり、自民党の作業チームは、原則として、父親と母親が引き続き責務を果たすため、双方が親権を持つ「共同親権」の制度を導入すべきだなどとした提言をまとめ、古川法務大臣に提出しました。
親が離婚したあとの養育費の不払いや親権の在り方など、子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会は制度の見直しに向けた議論を行っています。
こうした中、自民党の法務部会の作業チームは子どもの養育の在り方などをめぐって提言をまとめ、21日、古川法務大臣に提出しました。
この中では、離婚した場合、原則として父親と母親が引き続き子どもに対し責務を果たすため、双方が親権を持つ「共同親権」の制度を導入すべきだとしています。
また、離婚する場合、父親と母親が子どもの養育を適切に行うため「監護割合」や養育費などについて定める「共同養育計画」の作成など、必要な事項について一定の責務を課すべきだとしています。
さらに「共同親権」の制度の導入に伴い、父親と母親の一方がDV=ドメスティック・バイオレンスや児童虐待を働いているなど、原則どおりに適用すると不都合が生じ得るケースについて、安心・安全の観点から丁寧に対応する規律を設けるべきだなどとしています。
自民が古川法相に離婚後の共同親権・共同監護を提言
出典:令和4年6月21日 産経新聞
自民党の山田美樹法務部会長は21日、法務省で古川禎久法相と面会し、同部会の「家族法制のあり方検討プロジェクトチーム」がまとめた父母が離婚した後の子供の養育に関する提言を手渡した。提言は「子の最善の利益を確保する」として、離婚後の父母が共に親権や子供の身の回りの世話や教育をする「監護権」を持つ「共同親権・共同監護」制度を導入するよう求めた。ドメスティックバイオレンス(DV)や児童虐待がある場合に対応した規律を設けることも訴えた。
同席者によると、古川氏は「子供の最善の利益を追求することは共通した思いだ」と応じた。
離婚後の“共同親権”に向け制度設計へ 現在は父母いずれかの“単独親権”
出典:令和4年6月21日 日本経済新聞
離婚後の“共同親権”に向け制度設計へ 現在は父母いずれかの“単独親権”
法務省は離婚した父母の双方が親権を持ち続けることを可能にする法改正を法制審議会(法相の諮問機関)に提案する。法制審が8月をメドにまとめる中間試案に盛り込む見通しだ。現行法の維持などと合わせた選択肢のひとつとして記す。
民法は婚姻中の父母が共同で親権を持つと認める半面、離婚後はどちらかだけが親権者となる単独親権を定める。法制審は2021年3月に家族法制部会を立ち上げ、離婚後の共同親権の採用を巡り議論してきた。
法務省と法制審の部会は中間試案に向け、父母の合意や裁判所の判断といった共同親権を採用する条件などを協議する。単独親権を原則として維持する案も含め、複数の選択肢を併記する方向だ。
日常の子どもの世話を決める「監護権」の範囲も検討事項にする。法務省は部会がまとめた試案を意見募集(パブリックコメント)にかける。
離婚後の共同親権の導入は部会の委員の間でも賛否が割れる。
病気の治療など子どもにとって重要な事項は父母双方が親権に基づいて熟慮することが適当とみる声がある。一方で同居する親が単独で決めた方が判断が安定するとの意見もある。
離婚後の「共同親権」日本での導入は? 現在の民法では父母いずれかの「単独親権」 それぞれの「課題」と「今後の議論」
出典:令和4年6月20日 TBS
離婚後の「共同親権」日本での導入は? 現在の民法では父母いずれかの「単独親権」 それぞれの「課題」と「今後の議論」
近年「3組に1組が離婚する」という言葉もある中、離婚した後「子どもをどう育てていくのか」が重要視されます。現在の民法では父母いずれかの「単独親権」で、「母に親権」が渡るケースが9割以上です。離婚後の父親と母親が、子どもの親権を共同で持つ「共同親権」を日本でも導入するかについて、法務省の専門家会議が具体的な制度の議論を進めていることが分かりました。親権をめぐる課題や今後の議論について見ていきます。
■ 子どもの「共同親権」導入なるか? 日本の民法は「単独親権」
ホラン千秋キャスター: 「共同親権」について考えます。今後、日本でも導入されるんでしょうか?
離婚した後に2人で共同親権を持って育てていこうというものです。
まず、婚姻届を出したカップルを見ていきましょう。
2020年婚姻届を提出したのは52万5507組。
そして、離婚届を提出したのは、19万3253組となるわけです。(厚労省 人口動態統計2020年)
近年「3組に1組が離婚する」という言葉もあるわけですが、離婚した後、お子さんをどう育てていくのかというところが重要視されるわけですよね。
その上で、現状、日本は単独親権ですので、離婚の場合、どちらが親権を持つのかということが議論に上がります。
親権とは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限・義務のことなわけです。
では、改めて日本の現状というのを見ていきましょう。
現在の民法では、単独親権のみが認められています。ですので、お父さん・お母さんが離婚した場合、そのどちらかが親権を持つ単独親権ということになるわけなんですよね。
では、お父さん・お母さんそれぞれ親権を持つ件数というのはどれくらい違うのかというのを見てみると
父に親権…1635件、
母に親権…1万6908件
(2020年度司法統計より)
圧倒的に母親に親権が渡ることの方が多いわけなんです。
この現状を見てみまして海外と比べましても「共同親権」ということを考えていく必要があるのではないかということで議論が行われています。
法務省の専門家会議が行っている議論なんですが、離婚した後も、どちらかだけに親権が渡るのではなく2人協力して育てていきましょう、というものが共同親権なわけなんですが、法務省の法制審議会の部会は「子どもの貧困や虐待を防ぐ上で離婚した後も双方が最後まで責任を持つべき」だとして、「共同親権」について検討しているわけなんです。
■ 「単独親権」「共同親権」それぞれの課題
ホランキャスター:
では、日本が今認めている「単独親権」、そして導入が考えられている「共同親権」、それぞれの課題というものを見ていきましょう。
萩谷麻衣子弁護士によると「子どもにとっての幸せを考え議論をしていくことは必要」ということです。
【単独親権の課題】
・子どもとの関わりが少ないため、養育費がきちんと支払われない
ちなみに母子家庭で養育費を受け取っている家庭は24%ということですので、その数字というものも課題になっているのかもしれません。
逆に
・養育費を支払っていても子どもとの面会・交流が極端に少ない など
養育費を支払っていても、払っていなくても課題があるというのが「単独親権」のようです。
【共同親権の課題】
感情的に対立して離婚に至るということが多く、子どものためとはいえ、割り切って簡単に協力できるものではない(教育・大きな病気の治療など意見が対立しやすい)
「共同親権」というものを導入したとしても、何らかの支援制度が必要なのではないかと話しています。
井上貴博キャスター: DVなどの問題もありますし、もう本当ケースバイケースで一概に言うことはできませんが、夫婦が離婚したとしても子どもの親であることは変わりませんので、選択肢が増えるというのは、進めていただきたいなとは感じます。
スポーツ心理学者(博士) 田中ウルヴェ京さん: 私もそう思います。選択肢が増えるということはつまり、その議論が増えるということなので、議論をしないと何が課題で、どちらにメリット・デメリット、両方メリット・デメリットあるねみたいな話をすることが大事ですから、共同親権の話が出ることはとても賛成です。 一方で、課題はそのご夫婦によって違うということがまず大前提ですけれど、もう一つ、大前提は子どもという「宝」。資本という言い方もできるかもしれませんが、子どもは社会にとってのとても大事な宝ですから、どのように社会が育んでいくかということが前提で話し合われることが大事だなと思います。 つまり、ご夫婦のどちらかに責任を持つべきという言い方よりは、子どもを育てるということは実は大人の人間的成長にも、とても大切なもので、誰かの子どもだとして、みんなで、どのように子どもを育んでいくかという中での共同親権なんだという俯瞰的な見方をすることで、また違った解決策が出てくるということもあろうかと思います。
井上キャスター: 家族単位だけではなくて社会全体というか、それを綺麗ごとではなくて全体として社会として国としてどういうふうに子ども育んでいけばよいでしょうか。
スポーツ心理学者 田中さん:
例えば、離婚は駄目だとか、結婚は良いことだではなくて、社会で子どもを育てるとはどういうことかということから話し合われていくこともすごく大事だと思います。
■ 夏にも中間的な案の取りまとめ
ホランキャスター: 法務省での部会で行われている議論も、共同親権だけにしましょうということではなくて、様々な形というのが話し合われています。 今まで通り単独親権の方がいいんじゃないかというような議論であったり、共同親権を原則にするという話、それから双方を組み合わせるのはどうだろうかなど話し合われているということなんですね。
そして、共同親権を導入した場合、お父さん・お母さん、2人に親権がありますので
日常的に子どもの面倒を見るのはどちらになるのか、それを監護者と呼ぶということですが、その監護者をどう決めていくのかも議論されているそうです。
そして夏にも中間的な案の取りまとめを行い、国民の意見も募集するということだそうです。
井上キャスター: この共同親権はもちろんのことですけど、先ほど広い話でいうと、例えば養育費についても、周りでも実際に受け取れない人がいて、でもそれをしっかりと養育費を支払わなければならないという仕組み作りも少し日本は遅れている。そういうところも含めて議論を進めていただきたいなと思います。
スポーツ心理学者 田中さん: 大きな議論から細かい課題の解決ということは必要です。例えば、養育費も今は男性が、ではなく女性が養育費を支払うことも当然あるわけで、社会進出の仕方も変わってきましたし、細かいことをこれからしっかり決めなきゃいけないんですよね。
井上キャスター: ウルヴェさん自身は国際結婚されてますので、そこの考え方はかなりフレキシブルですか? スポーツ心理学者 田中さん: 元々、日本人だったので本当にびっくりすることは、例えばフランスでは婚姻届を出していないカップルもたくさんいらっしゃいますし、例えばお1人のお子さんを3組ぐらいのカップルが、それぞれが一緒に育てるみたいな体系になったりもしています。大切なことは、お子さんにとって何が幸せかって、彼女たち・彼らたちが決められなかったりもするので、どのようにあると良いかってことを大人がいろいろなところから解決を考えていくってのが大事かと思います。
井上キャスター: 日本はまだまだ「家族はこうあるべきだ」というのが強い気はします。
離婚後の“共同親権”に向け制度設計へ 現在は父母いずれかの“単独親権”
出典:令和4年6月20日 TBS
離婚後の“共同親権”に向け制度設計へ 現在は父母いずれかの“単独親権”
離婚後の父親と母親が、子どもの親権を共同で持つ「共同親権」を日本でも導入するかについて、法務省の専門家会議が具体的な制度の議論を進めていることが分かりました。専門家会議は、この夏にも中間試案をまとめる方針です。 現在の民法では離婚後の子どもの親権者は父親か母親、どちらかになる「単独親権」になっています。 これに対し、有識者からなる法務省の法制審議会の部会では「子どもの貧困や虐待を防ぐ上で離婚したあとも、双方が最後まで責任を持つべき」という議論があり、「共同親権」について検討がされてきました。 関係者によりますと、部会の議論では・現状のまま単独親権とするのか、・共同親権を原則とするのか、・両者を組み合わせるのかの議論が行われています。 その上で、共同親権を導入した場合、例えば、離婚で父親と母親が別居した際には、どちらかを日常的に子どもの面倒をみる「監護者」とする制度をつくるのか、などが議論されています。 部会はこの夏にも中間試案をとりまとめ、国民から意見を公募する方針です。
離婚後の共同親権を提案へ 法務省、法制審部会に 8月にも試案討議
出典:令和4年6月20日 毎日新聞
離婚後の共同親権を提案へ 法務省、法制審部会に 8月にも試案
法務省は、家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案する方針を固めた。現行民法は離婚後の単独親権を定めており、部会は民法改正の中間試案を8月をめどに取りまとめる。その上で意見を公募するパブリックコメントを実施し、詰めの議論に入る。
民法は、婚姻中の父母の共同親権を定める一方、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権を採用する。日本では近年、年間20万組前後、おおよそ3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。
一方で、女性の社会進出や男性の育児参加が進み、「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声があり、離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに子と家を出る「子の連れ去り」も頻発している。国際的には、離婚後の共同親権が主流となっている。
関係者によると、同省が提案する内容は、父母双方が子に関わり続けることが「子の最善の利益にかなう」ケースを念頭に、父母が話し合いや裁判所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。具体的には、子の進路や病気の治療方針について父母双方が共同親権に基づき、子のために熟慮して決定するような仕組みが想定される。このような共同親権を原則とする案と、単独親権を原則とする案が示される模様だ。
また、離婚した父母は多くの場合は別居し、一方の親が子と同居して暮らすことが多い。このため、離婚後の共同親権を選んだ場合に、子の日常の世話について決める「監護権」を持つ親である「監護者」を置く制度も議論されるという。共同親権と監護権の役割分担をどうするかは今後の焦点になりそうだ。
さらに、離婚しても子が普段は同居親と生活し、休暇中は別居親と過ごすといった良好な親子関係もあるため、共同親権を前提に、両者が監護者になる「離婚後の共同監護」も選択肢として示される見通し。
一方、家庭内暴力(DV)や激しいいがみ合いが続く父母が共同親権を選ぶと、子に関わる重要な決定ができなくなるとの懸念もある。家族を巡る価値観は多様であることを踏まえ、単独親権のみの現行制度を維持する案も議論されるという。【山本将克】
「共同親権」参院選を前に静かなる“ヤマ場”、自民党が民間試案を討議
出典:令和4年6月6日 SAKISIRU
「共同親権」参院選を前に静かなる“ヤマ場”、自民党が民間試案を討議
法務省法制審案と合わせ異例の検討、カギとなるDV対策は?
SAKISIRU編集部
親が離婚した後の子育てについて、G7で唯一、単独親権制度しか認めていない日本で、国際的なルールに合わせた共同親権・共同養育を認めるべきか、参院選を前に政策的なヤマ場が生まれつつある。
■「法務省 vs. 民間」2つの法制審
日本では片親が子どもを一方的に連れ去る事案が後を絶たない。日本は2013年に「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)に批准した後も、親権制度がこの国際的なルールに適応する形で変更されておらず、日本人の配偶者による連れ去り事案が相次いだ欧州では、EU議会が日本に対し「子の連れ去りに関する国際的なルールを遵守していないように見受けられる」と決議している。
国際的な圧力もかかってきたことで近年、日本側も制度改正を検討し始め、法務省の諮問機関、法制審議会の家族法制部会が昨年3月から検討を進めてきた。しかし、同部会の委員には、共同親権導入に抵抗する左派の人権派有識者もいるためか、現行の親権制度の見直し案は国際基準から程遠い「骨抜き」になりつつある。
審議中の資料などから浮かび上がってくるのは、共同親権は形式的には認めるものの、監護権は引き続き片親のみに認めるとする案に固まりつつあり、共同親権推進派からは「家族制度が崩壊する」などの懸念が示されている。
これに対し、推進派は、弁護士・大学教授などがつくる民間法制審議会の家族法制部会が別の制度案を提起し、法務省案に対抗する構えに打って出た。5月31日には同部会長で、テレビ番組でも知られる北村晴男弁護士らが記者会見。独自の「中間試案」を発表し、自民党の高市政調会長にも提出した。
民間側の試案では、
1.全ての欧米諸国、台湾や韓国も採用する離婚後『共同親権・共同監護』制度の創設
2.婚姻中の家族の在り方を規定する現行の民法体系と整合性のとれた制度の創設
3.父母が配偶者暴力(DV)や児童虐待を行っている場合など、特殊な事例にも対応した制度の創設
4.ハーグ条約(国際的な子の連れ去りを禁止する条約)不履行国と国際的に非難される原因となっている国内法の改正
がポイントに挙げている。(1)や(4)が示すように国際基準に則った内容になっているのが特徴だ。
■ 実効性あるDV対策、自民は異例の対応
一方で、日本で共同親権導入が進まなかった大きな要因としてはDV(配偶者暴力)だ。例えば、離婚後共同親権に反対する市民の会は「加害者は子どもと会う権利や機会を利用し、支配を続けようとする」(公式サイト)などと主張し、根強く抵抗している、
このDV問題をどうするか。(3)で提起しているDVなどの問題事案への対応について、試案の詳細版では、両親が離婚する際に「共同監護計画」の作成と公正証書化を義務付けた上で、「離婚後の面会交流、養育費に関する規律」を要求。
父母の一方が、配偶者暴力防止法の規定に基づく保護命令を裁判所に申し立てたときは、裁判所は、当該父母に対し、婦人相談所等が提供する父母間の連絡調整及び子の受渡し支援サービスの利用を命ずる規律を設ける。
などと提起している。関係者は「民間法制審案は、DVの申し立てがあれば配偶者との接触は禁止するが、親子の交流は継続しなければならない規定になっている」と説明する。
DV問題に関連して、これまで一部の親が相手と子どもの面会を拒絶したいがために、実態がないDVを主張するケースもあったが、この民間法制審案を導入した場合は、手続きに第三者が入ることで、関係者は「子どもをもう一方の親と会わせない理由としてDVは使えなくなる。本当にDVを受けていた人にはメリットがある一方で、嘘のDVを申し立てていた人には、デメリットばかり増えることになる」と実効性を期待している。
民間法制審の中間試案の影響力は小さくない。試案を受け取った自民党サイドは、法務省の法制審案と比較検討して今後の立法化を進めるという異例の対応をする方針を示している。
党政調会法務部会(部会長:山田美樹衆院議員)は7日、民間法制審の試案を俎上に載せて討議した。参院選での政策論議や、秋の臨時国会以後に新たな展開があるのか注目される。
家族解体へ進む法改正
出典:令和4年6月6日 産経新聞
世間の目がウクライナ侵略戦争に、片や国会議員の関心が参院選に集中する中、法務省で家族をバラバラにする法改正が進んでいる。法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会(以下法制審)がこの夏にまとめる予定の「父母の離婚に伴う子の養育の在り方」に関する中間試案のことである。
法制審には、認定NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子理事長らをはじめ、いわゆる人権派の人物が名を連ね、シングルマザーの立場に肩入れするあまり、一方の親を排除して子供の独占を促進するかのような議論がなされていた。
家族の在り方を変える法改正を一方的な意見に基づいて進めることは社会の基盤である家族の形をゆがめるものだ。私は昨年8月20日、上川陽子法相(当時)を訪ね、幅広い考え方を基に家族法制を定めるよう要望した。上川氏は「ご心配なく」と、断固とした自負を見せた。
※以下、紙面を参照ください。
離婚後も「共同監護を」民間団体が独自試案とりまとめ
出典:令和4年5月31日 産経新聞
法務省法制審議会家族法制部会が今夏にも発表する見込みの共同親権に関する中間試案を巡り、国内外の研究者や弁護士らでつくる民間団体が31日、「法制審の案は、婚姻中の家族の在り方まで変更する恐れがある」として、独自に取りまとめた中間試案を自民党の高市早苗政調会長に提出した。
団体側は、法制審の部会が発表する試案と団体側の試案を与党内で比較・審査した上で、欧米諸国や韓国、台湾などが採用している離婚後の「共同親権・共同監護」制度を創設するよう求めている。
試案の提出後、東京都内で会見した部会長の北村晴男弁護士は、法制審で議論されている、離婚後に一方の親のみを子供の監護者とする案について「国際的に批判されている、一方の親による子供の連れ去りを追認するものだ」と批判。「今も子供の成長を見守れない親がたくさんいる。その思いに応える制度設計をすべきだ」と訴えた。
髙橋史朗68 – 国連が勧告した日本の「実子連れ去り」家族の絆を取り戻す法改正の緊急課題
出典:令和4年5月19日 モラロジー道徳教育財団
髙橋史朗68 – 国連が勧告した日本の「実子連れ去り」家族の絆を取り戻す法改正の緊急課題
髙橋史朗 モラロジー道徳教育財団 道徳科学研究所教授
●欧州議会本会議対日非難決議「日本は子供の拉致国家」
櫻井よしこ「『家族』壊す保守政治家」(産経新聞令和3年7月6日付)によれば、毎年15万から16万人の子供が片方の親に連れ去られたり、片方の親から切り離される悲劇が起きているという。令和2年7月、欧州本会議は「日本は子供の拉致国家」であるとして、次のような日本における子供の連れ去りに関する非難決議を圧倒的多数で可決した。
「日本が子供の連れ去り案件に対し国際規約を遵守していないと遺憾を示すとともに、ハーグ条約の下で子供の送還が効果的に執行されるように国内法制度を改正するよう促す。……日本当局に対し、共同親権の可能性に向けた国内法令改正を促す」
父親も育児に積極的に参画し共同して監護する「家庭における男女共同参画」が推進されている中で、離婚という夫婦間の事情で親権(母親が9割以上取得している)を一方の親から奪い、一方の親を子育てから排除する社会制度や慣行は、男女のどちらか一方を不利にする状況をもたらし、男女共同参画の趣旨に反する。
また、養育費の義務化のみをことさらに主張して「共同養育」を軽視し、共同親権に反対する主張を一部の女性団体などがしているが、これは「男性は仕事だけしてお金だけ出せばよい」という、男女共同参画の理念に反する差別意識が背景にある。
このような歪んだ「逆差別」意識を解消していく必要がある。男性をATMのように扱う主張は明らかな人権侵害であり、このような考え方が男性差別であるという認識を社会に広く浸透させる必要があろう。
日本大学の先崎彰容教授は、「リベラルVS保守の立場を超えて、あまりにも単純な男女観、父母観から抜け出さねばならない」「男女平等とは何か」「家族とは何か」こそが問われていると次のように訴えているが、核心を突いた指摘といえる。
第一に、子供たちは母親を愛するのと同様に、父親を愛する権利をもっている。ところが、私たちは母親が女性というだけの理由で、養育するのを「常識」にしている。だがこれは究極の男女不平等ではないか。
また、男女の機会均等や不平等をめぐる議論は、圧倒的に「女性の権利が奪われている」という図式でなされる。それが逆転した男女差別が、この「単独親権」なのである。夫=男性=親権不適格者という「図式」だけでは解決が不可能になったのだ。リベラルな立場の人たちは究極の男女平等を追求するために、ぜひとも父母双方に子供と交流する機会を!と訴えてほしい。
第二に、夫が男というだけで養育の権利を奪われ、「家族」が解体してしまうことが問題である。家庭裁判所の現場でも、未だに「単独親権」、つまり母親の権利だけが重視されている。裁判官までもが女性=親権を持つべきだという男女観、無意識の「常識」に取り込まれている。
(産経新聞、令和元年9月16日付「正論」、「司法は『家族』を取り戻せるか」)
●左派団体に不都合な国連勧告を無視
「こども基本法」が浮上した背景には、過去5回、国連の児童の権利委員会(CRC)から日本政府に出された国連勧告がある。日本の左派NGOや日教組、日本弁護士連合会などが強調している国連勧告の中に、彼らにとって都合の悪い勧告が含まれている。児童相談所を中心とした「社会的養護」利権にかかわる問題である。
まず、この問題に関する2019年3月の国連勧告(日本の第4、5回合併定期報告書に関する総括所見)を抜粋しよう。
<家族環境>
「家族を支援し、強化すること」「子供の遺棄および施設措置を予防する」「親との個人的関係および直接の交流を維持する子供の権利が定期的に行使できることを保障する」
<家庭環境を奪われた子供たち>
⑴ 多数の子供たちが家族から引きはがされているとの報告があり、その引きはがしは司法令状のないままですることができ、しかも児童相談所に最大2ヶ月収容されることになること
⑵ 多数の子供たちが、不適切な水準にあり、児童虐待の事案が報告されており、しかも外部による監督と評価の機構がない施設に依然として収容されていること
⑶ 児童相談所がより多くの児童を受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブを有する疑惑があること
⑷ 施設措置された子供たちが、その生みの親との接触を維持する権利をはく奪されていること(以下、略)
<子供の代替的養護に関する指針(国連総会決議)に対する強い要求>
⑴ 子供が家族から引きはがされるべきか否かの決定に際して、義務的司法審査を導入し、子供の引きはがしについて明確な基準を設定し、そして子供たちを親から引き離すのは、それを保護するため必要で子供の最善の利益にかなっている時に、子供とその親を聴聞したあと、最後の手段としてのみなされるのを保障すること
⑵ 子供の速やかな脱施設化および里親機関の設置を保障すること
⑶ 児童相談所において子供たちを一時保護するやり方を廃止すること(以下、略)
このような国連勧告が出された背景には、「児童被害を撲滅する会」など、児童相談所に家族を破壊された被害団体が国連の同委員会に2回提出したレポートが影響を与えたものと思われる。左派団体は国連勧告を自分たちの主張を正当化するために利用し、このような児童相談所の家族破壊に関する国連児童の権利委員会の事実認定と勧告が出ると、児童相談所の拡大・強化を支持する日教組や日弁連などは、従来の国連に対する態度を、手のひらを返したように無視する戦術を展開している。
児童の権利条約第18条には、「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法廷保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する」と明記されている。
●家族破壊による「子供の商品化」
児童相談所は、軽微な冤罪「虐待」事案を口実に家族から切り離した子供たちを、児童養護施設などの「社会的養護」施設に流し込むが、虐待死のような凶悪事案は一向に根絶されない。児童養護施設に強制入所された子供たちには、児童虐待防止法第12条によって面会禁止処分が加えられることもあり、子供は家族から断絶され「人工孤児」となる。
これにより、社会的養護を提供する児童養護施設などの利益集団が、家族から切り離された子供たちを使って経済的利益をむさぼっているのである。一方、子供たちは、児童養護施設職員による性的暴行に晒されている。「子供の最善の利益」の保障が求められている児童養護施設が利権のとりことなって、家族破壊による「子供の商品化」に拍車がかかっているのである。
もともと、児童福祉法の下で利権化した児童養護施設の業界は、戦争孤児が成人した後、空きベッドを埋めるため「子供よこせ」運動を展開していた。児童相談所はもともと敗戦直後に戦争孤児をケアするためにできた行政機関で、戦争孤児が成人するとともにその本来の機能を失った。しかし、その後も存続し、経済の高度成長期には不登校児など細々と扱っていたが、1980年代冒頭の臨調行革の中でリストラの嵐に翻弄された。
そこで、厚生省が「児童虐待」に着目し、これを児童相談所に担当させることにして、息を吹き返した。戦争孤児時代の児童福祉法第33条をそのまま使い、児童の権利条約第9条1項には以下のように書かれているにもかかわらず、この条項に違反して、軽微な冤罪の「虐待」事案で、家族から子供を引きはがし拉致を強行し、これによって全国で家族破壊が広がっている。
「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りではない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある」
●国連も指摘した「拉致ノルマ」という「社会的養護」利権
児童相談所の「一時保護所」では、子供たちを学校に通わせず、性的暴行、向精神薬投与など数々の人権侵害が横行し、そのため国連児童の権利委員会から前述したように閉鎖勧告が出されたのである。児童相談所の年間予算には「一時保護見込み数」(児相被害者は「拉致ノルマ」と呼んでいる)が組み込まれており、予算額を達成できるだけの数の児童を家族から引き離す経済的インセンティブ(人々の意思決定や行動を変化させるような要因)を持つことは国連児童権利委員会も指摘し、厚労省の専門官も同委員会の答弁で認めている。
児童相談所に「拉致」された後、多くの場合、子供たちは児童養護施設に送り込まれ、家族破壊が長期化し、子供が「家に帰りたい」と訴えても帰さない。その意味で、児童相談所は「社会的養護」利権への「取児口」(水岡不二雄・南出喜久治『児相利権:「子ども虐待防止」の名でなされる児童相談所の人権蹂躙と国民統制』八翔社、参照)の機能を果たしている。
それ故に、水岡不二雄一橋大名誉教授は、児童相談所は増設ではなく廃止し、刑法犯罪に類する凶悪虐待事案は警察に移管すべきだと言う。児童相談所から「一時保護」の権限を奪い、純粋な育児支援機関に衣替えしないと、子育てをする家族は、わが子が奪われるのが怖くて行政の子育てサービスを利用できなくなると水岡名誉教授は警告する。
数値比較で日本の「社会的養護」が遅れていると批判する人々は、日本の制度自体が著しく国際人権規範から立ち遅れている現実を決して見ようとはしない。この現実を厳しく批判した国連勧告を無視する背景には「社会的養護」利権への忖度があることは明白である。
●「懲戒権」削除の民法改正と「教育虐待」の浸透が教育荒廃に拍車をかける
自民党の24条改憲案には、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される」と明記されており、高市早苗政調会長が構想する「家族基本法」の制定こそ喫緊の課題といえる。実親養育中心主義を明確に規定し、児童相談所が家族に介入し、子供を連れ去り「親子の絆」を蹂躙している現状を改革しなければならない。
1月5日の新聞報道によれば、「親が子を戒めることを認める民法の『懲戒権』の規定の見直しを議論する法務大臣の諮問機関である法制審議会の担当部会は、同規定を削除し、体罰の禁止を明示する規定を盛り込む方針を固めた」という。この民法改正案は通常国会に提出され成立する見通しであるが、これによって親が子供をしつけることの法的根拠がなくなることになる。これまで民法の「懲戒権」は、児童相談所による野放図な子供の拉致や家族破壊の歯止めとして機能してきたが、「懲戒権」がなくなれば、少しでも子供に厳しいことを言うと、直ちに家族が切り離されて児童相談所に連れて行かれ、さらに児童養護施設に送り込まれてしまう現実的危険が生じる。
親による過剰な責や受験圧力などは「心理的虐待」と見做され、2020年に警察が児童虐待の疑いで児童相談所に通告した子供約1万千人のうち、約7万8千人を「心理的虐待」が占めている。こども庁・子ども基本法論議をリードしてきた早稲田大学の喜多明人名誉教授は、こうした家庭における「心理的虐待」と学校における精神的暴力を一つのつながりのある事象と捉え、「エデュケーショナル(教育的)ハラスメント」(略称・エデュハラ)として捉える新たな視点を提唱している。
こうした「教育虐待」という新たな視点から家庭と学校における指導や躾る権利(親権)に歯止めをかけ、子供の意見を尊重するという大義名分によって「反差別的取り扱い」として、法的措置を含めた対立を持ち込もうとしているのである。「子供の最善の利益」の名の下に、児童の権利条約が認めている父母の教育権や養育責任が否定されれば、教育荒廃にますます拍車がかかることは火を見るより明らかである。
最後に、5月17日の参議院法務委員会で嘉田由紀子議員(元滋賀県知事)が「離婚後の子供の養育の在り方」に関する法制審議会家族法部会が今夏に提出予定の中間試案は「親子関係を根底から覆す恐れがある」として、⑴性別による役割分担を固定化し、男女共同参画という時代のニーズに逆行、⑵EU議会の対日非難決議に見られるように国際的潮流に逆行、⑶児童の権利条約9条違反、⑷憲法第24条違反だと批判した。私も同趣旨の同試案の懸念事項を4月26日に提出しているが、紙面が尽きたので、これについては稿を改めたい。
(令和4年5月19日)
長谷川京子 離婚後に変わった2人の子どもの育児スタイル「シェアしていくっていう形で」
出典:令和4年5月18日 スポニチ
長谷川京子 離婚後に変わった2人の子どもの育児スタイル「シェアしていくっていう形で
女優の長谷川京子(43)が17日放送のフジテレビ系「セブンルール」(火曜後11・00)に出演。離婚後の2人の子どもの育児について赤裸々に語った。
長谷川は2008年、30歳の時にロックバンド「ポルノグラフィティ」のギタリスト、新藤晴一と結婚し、12歳の長男と9歳の長女をもうけるも、昨年10月、新藤と離婚。今年2月には23年間所属したレプロエンタテインメントとのマネジメント契約を終了し、フリーで活動している。
番組では、独立後の2カ月半に密着。持ち歩くかばんからはなぜかテレビのリモコンが。「子どもが家にいるので、無制限でテレビを見てしまうので、子どもが自発的にテレビを見ずに宿題をやるのがゴールなんですよ。子ども同士のケンカみたいなところで、例えば引き出しの棚に隠していっても、絶対に見つけるから、持っていくしかないですよね」と母の顔をのぞかせた。
これまでどんなに忙しくても大切にしてきた子どもたちとの時間。それも離婚で変わったそうで「パパとママで育てていきたいという意味では、1週間の中で(育児を)シェアしていくっていう形で今はやっています」と離婚後の育児スタイルを告白。「これも子どもがどんどん大きくなっていくので、親の言いなりにはもうならないから、“こうしたい”“ああしたい”っていう提案があったら、聞いていきたいと思う」とも明かした。
別居母親 事例3 引き離しの背後に義母がいる
出典:令和4年5月16日 note
上篠まゆみ
別居母親や親子の引き離しの取材をしていて感じるのは、配偶者から子どもを引き離す人の背後に、ほぼ必ず義母の存在があるということだ。とくに夫の場合、夫本人というより義母が扇動していることが多いような気がする。そして、子育てを取り仕切る。
家庭のなかで「母」という立場は、ある種の権力だ。その権力をもう一度、取り戻したいのか。息子の子ども(孫)のうえに母として君臨したいのか。
実際、取材のなかで息子とその子ども(孫)を抱え込んだ義母が、自分のことを「ママ」と呼ばせているという話も聞いたことがある。
マサコさんのケースも、義母が大きな役回りをつとめている。
別居に夫も了承したのに…
マサコさん(仮名・46歳)は、13歳の息子の母親だ。夫と別居しひとり暮らしを始めて6年、子どもは父親の元にいる。子どもの世話は、同居の義母がしている。
マサコさんが望んだ形ではない。マサコさんは、子どもと一緒に暮らしたかった。しかし、夫と義母にそれを阻止された。
夫と義母、子どもが住んでいる家と土地は、マサコさんも半分の名義を持っている。にもかかわらず、出入りを禁止されており、子どもとも月1回4時間と決められた枠の中でしか会えないでいる。
マサコさんは看護師で、夫は薬品会社の営業マン。友だちを通して知り合い、結婚した。共働きをしながら出産。慌ただしくも充実した日々だった。
家を建てるときに、ひとり暮らしをしていた義母を引き取り、同居を始めた。このあたりから、夫婦の歯車が狂い始めた。
「家庭は夫婦2人で築いていくものなのに、夫は常に義母ありきでものを言う。共働きだから家事も育児も2人で分担したいのに、私が夫に頼んだことを夫は義母に丸投げしてしまう。それは違うんじゃないかな、ということが増えてきて。しまいには、家の中で大事なことも私抜きで、夫と義母が話をして決めるようになってしまいました」
マサコさんも気が弱いほうではないから、はっきりと夫に改善を求めた。「あなたは誰と生活していきたいの」。しかし、夫も頑固で、「態度を変える気はない」と言う。
「このまま生活していくのはしんどいなと思い、私は別居を提案したんです。夫も了承したので、実際にアパートの部屋を借り、子どもを連れて出ていきました。子どもが学校を変わりたくないと言うので同じ校区内、住んでいた家から10分足らずのところ。夫婦仲と親子関係は別物ですから、別居をしても子どもと父親の関係を切るつもりはありませんでした」
引っ越しは、子どもの学校の夏休み中にした。当時、子どもは7歳。マサコさんは看護師という専門職で、十分な収入を得ている。この先、離婚をして母子2人暮らしになっても、充分に暮らしていけると考えていた。
ところが。
別居開始からわずか2日後、夫はマサコさんに無断で、子どもを学童から連れ帰ってしまった。母子2人暮らしはここで終わった。
義母が子どもを家の中に軟禁
「私が子どもを連れて家を出ていくとき、夫はごくふつうに『じゃあ!』と話していたので、まさか子どもを連れて行ってしまうなんて思いもしませんでした」
夫は子どもを義母に預け、義母は親戚の家に逃げ込み、マサコさんが手出しできないようにした。
子どもといきなり引き離されて、マサコさんはどうしたらいいかまったく分からなかった。
ただ、相手方が『弁護士!裁判所!』としか言わないので困り果て、何件かの弁護士事務所に相談したが、「連れ去られ案件は勝てる見込みがないから難しい」と言われ、なかなか引き受け手が見つからない。焦燥感に駆られて過ごした。
「夏休みが終わるころには家に戻ってきましたが、一日中、義母が子どもを家の中に軟禁して一歩も家から出さないんです。子どもに会いたくて家に行ったら、義母が『助けてーっ! ママに殺されるー!』と叫び、窓に近寄ってきた子どもを2階に追い立てました。子どもは耳を塞いでいました。更に、警察まで呼び、警察には、『私は関係ない!』と叫ぶ始末。呼ばれた警察もただ立っているだけの、家と土地の所有者である私に、何も出来ず…の膠着状態…」
想像するだけでやりきれない光景である。
以降、マサコさんは、子どもの気持ちを考え、家に近づかなくなった。
子どもに会わせないのは復讐?
その後、ようやく引き受けてくれる弁護士が見つかり、子どもの監護者指定と引渡しを求めて家庭裁判所に調停を申し立てた。相手も弁護士を立てて応戦してきた。が、そもそも話し合う気がない夫との調停は、2年ほどかかったが、不成立に終わってしまう。
「夫は、私が頭がおかしくなって家を出ていった、精神科に行って病気を治したら話を聞いてやる、と言うんです。もともと自分のテリトリー内にいる人は可愛がるけど、それ以外の人は徹底的に排除する気質のある人でした。自分の言うことを聞かず家を出ていった私は、夫にとって敵なんでしょうね。私から子どもを取り上げることで復讐をしているつもりなんだと思いますし、自分は正しいので、やって当たり前なのだと信じているのだと思います…」
マサコさんは、とにかく子どもに会いたかった。それまで一緒に暮らしていたのにいきなり会えなくなって、自分も辛いが、子どもはどんな思いだろう。切なさに叫び出しそうになった。それでも、いつか子どもを引き取って一緒に暮らせる日が来るかもしれないと思うと、仕事は辞められない。
精神的にズタズタな状態で仕事に行くのは、過酷ではあるが、逆に救いでもあった。
「仕事に集中している間は、子どもと会えない苦しさを忘れていられました」
マサコさんが子どもに会わせてほしいと頼んでも、夫は無視。面会交流調停を申し立てたが、のらりくらりと交わされるばかり。その間にも、子どもと会えない時間が積み重なっていく。
マサコさんにできるのは、学校や保育園の行事にこまめに参加して、子どもの顔を見ることだけだった。子どもは困惑した顔を見せた。
「夫や義母が、ママが来ても無視するようにと言っているのだな、と思いました」
4年後にようやく月1回の面会が可能に
4年もかかってようやく高等裁判所の判断がつき、マサコさんは月1回4時間、子どもと会えることになった。あまりにわずかな時間だが、会えないよりはずっといい。ちなみに離婚はしていない。
「2年半の間、学校行事のほかは家庭裁判所での試行面会をしたり、弁護士2名が付き添っての面会交流だったり…。だから、誰も第三者がいない場所で子どもと会うのは本当に久しぶりでした。どうなるかとドキドキしていたら、子どもは来るなり弾丸トーク。『ママ、あれがね』『ママ、これがね』って。私を好きで、私を信頼している、私の子どもが変わらずそこにいました」
面会交流をめぐる調停や裁判で、夫が出してくる書面には「子どもは母親に会いたくないと言っている」などと書かれていた。別居するまでの親子関係は良好だったから、そんなはずはないと思っても、やはり凹むし、深く傷付く…。
「子どもの気持ちがわからなくて疑心暗鬼になってしまい、正直、子どもを精神的に手放したら楽になるのかなと思ったこともありました。でも、子どもは私を信じてくれていた。これはもう、子どもとの関係を諦めずに頑張るしかないと思っています」
離婚後の共同親権、超党派議連が法相に要望 「親として当然の責務」
出典:令和4年4月22日 毎日新聞
離婚後の共同親権、超党派議連が法相に要望 「親として当然の責務」
父母の離婚後の子の養育を巡り、超党派の「共同養育支援議員連盟」(会長・柴山昌彦元文部科学相)は22日、離婚後の共同親権を認める制度の導入を求める提言書を古川禎久法相に提出した。
現行民法は、父母が離婚した場合、いずれかが親権者となる「単独親権」を採用する。法制審議会(法相の諮問機関)は現在、父母の離婚に伴う子の養育や親権のあり方について見直しの議論をしている。
議連は提言で、離婚後も父母双方が子の養育に関わって責任を果たすことは「親としての当然の責務で、国際的潮流だ」と指摘。離婚の原因にDV(家庭内暴力)があるような例外的な場合を除いて、離婚後も共同親権・共同養育を認める検討を進めるよう訴えている。
また、父母が離婚した子の健全な成長のためには、確実な養育費の支払いと安全・安心な親子交流の実施が「車の両輪のように不可欠」とし、両者のいずれかを優先するのではなく、足並みをそろえて検討を進めることも求めた。
古川法相は「何よりも子の利益の観点が一番大事。政府全体で取り組んでいく大きな課題だ」と述べた。【山本将克】
「共同親権の導入検討を」超党派議連が提言、連れ去り助言の弁護士敗訴判決も追い風
出典:令和4年4月14日 SAKISIRU
「共同親権の導入検討を」超党派議連が提言、連れ去り助言の弁護士敗訴判決も追い風
マスコミ各社黙殺の異様、当事者ネット発信活発化
SAKISIRU編集部
夫婦間の対立や離婚に際し、片方の親の同意なしに子どもの連れ去りが相次いでいる問題は、捜査機関や司法の対応に変化が生まれ、政治レベルでも親権制度の見直しに向けた機運が着実に強まっている。
超党派の国会議員有志でつくる「共同養育支援議員連盟」は12日、親子交流の推進や共同親権の導入などを求める緊急提言をまとめた。近く政府に提出する。
■離婚後の単独親権見直し提言
親権制度のあり方を巡っては、法務省の諮問機関、法制審議会の家族法制部会が昨年3月から検討を進めており、中間取りまとめが近く行われる見通しだ。議連も同部会と並行し、これまでに月1回のペースで総会を開催。今回の緊急提言はこのスケジュールを見越したもので、法制審に対しては「離婚後の共同養育が当然であることの認識の下、養育費の支払いと親子交流のいずれを優先するのではなく、両者足並みを揃えて少しでも早く検討を進め、 答申すること」と要望した。
さらに、3月下旬には親権のある男性が、子どもを連れ去った元妻を訴えた裁判で「異例の判決」が出たことにも言及。この民事訴訟では、元妻とともに訴えられた代理人弁護士に対しても違法な連れ出しを教唆したとして東京地裁が損害賠償を命じる判決が出ている。
これを受け、提言では以下のように共同親権制導入に向けた検討も要請した。
代理人弁護士の不法行為責任が認められた地裁判決も出るに至っていることも踏まえるならば、海外の制度を調査し、日本の諸制度と比較検討した上で、離婚後に単独親権制度しか認められない現行制度を早急に見直し、DV などの例外的な事象を除き、離婚後においても共同親権が認められる制度の導入についての検討を進めること
このほか「親子交流支援の実態調査や現行の支援事業の抜本的拡充に加え、親子交流を支援する民間の団体を所管する官庁を明確に定め、民間の親子交流支援機関の展開・充実に早急に取り組むこと」も必要だと主張している。
議連の2月の総会では、警察庁の担当者が同意のない片親の連れ去りについて「正当な理由のない限り未成年者略取罪に当たる」と明言したことが注目され(関連記事)、その後、正式な通達が全国の警察本部に周知された。
幹事長を務める牧原秀樹衆院議員は12日夜のツイッターで「新たな流れができつつあります」と手応えを述べた。
共同養育議員連盟にて決議書を採択。審議会における親子交流と養育費の並行議論の要請、共同親権導入の検討、親子交流促進支援が柱です。
親子断絶を唆した弁護士にも損害賠償命令が出た判決、未成年者略取誘拐罪に該当しうる警察の通知発出など新たな流れができつつあります。
維新の石井苗子参院議員は総会後、DVなどの「特別な配慮が必要な別離にも十二分な配慮を」という但し書きをしながらも、「悲しむ親子を減らすためにも、共同養育へと舵を切ることに躊躇してはいけません」と強調した。
共同親権に関する議連へ参加。
現在日本では単独親権しか認められておらず、離婚で引き裂かれる親子が多くいます。
悲しむ親子を減らすためにも、共同養育へと舵を切ることに躊躇してはいけません。
ただしDVで苦しむなど、特別な配慮が必要な別離にも十二分な配慮を。
選択的共同養育へ向けて。
議連会長の柴山昌彦元文科相は連れ去り被害者からの相談が続出し、心が痛むと綴った。ただ「政府への要請や立法が国会議員の仕事なので、この欄の記載などをご参考に是非弁護士に相談して下さい」と投稿し、当面の対策に役立ててもらう意向を示した。
(補足)多くの方から連日「子供が連れ去られましたがどうしたらいいでしょうか?」という個別相談を山ほどいただいています。深刻な案件ばかりで心が痛みますが、政府への要請や立法が国会議員の仕事なので、この欄の記載などをご参考に是非弁護士に相談して下さい。
■圧力にビビる報道、当事者はネットで抗戦
「面会交流調停をやっても、相手側が虚偽の主張であっても、子どもとは会えない」。数年前に2歳と5歳の子どもを元妻に連れ去られたという男性は現在の裁判所の対応や制度面の限界に憤る。他方、この問題が新聞やテレビ局などの記者クラブメディアでほとんど報道されず、世間の関心が高まらないために事態が進展しないことにも不信感を募らせている。
実際、昨年もある大手メディアの言論サイトで連れ去り被害者側のインタビュー記事が掲載直後に削除された「事件」があったが、事情通によれば編集部に対し、猛烈な圧力がかかったと言われる。
それでも当事者はゲリラ的にSNSで積極的に想いを伝え続けている。柴山氏や牧原氏らのツイッター投稿に対し、連れ去り被害者と見られるアカウントから取り組みへの謝意とともに「将来の日本を背負うこどもの為に1日でも早く助けて下さい」などの要望が相次いだ。彼らは時に共同親権反対派の左派系アカウントとの論戦も辞さない。
日本が「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)に批准して10年近く。それでも単独親権制度を継続し、同意なき連れ去りが止まないことから、EU議会が日本に対し「子の連れ去りに関する国際的なルールを遵守していないように見受けられる」と決議するなど国際的な圧力もかかっている。反対派は、法制審の議論での巻き返しを図っているが、参院選に向けて当事者の尊厳をかけた政治闘争はさらに続きそうだ。
「子供とって最適な形で」日本でも“共同親権”導入の是非検討…単独親権との違いと課題
出典:令和3年11月9日 FNNプライムオンライン
「子供とって最適な形で」日本でも“共同親権”導入の是非検討…単独親権との違いと課題
現在日本においても導入の是非が検討されている共同親権。
それは「子に対する親権を父母の双方が持っていること」又は「父母が共同し、合意に基づいて子に対し親権を行うこと」を指します。
一方、現在の日本で認められている単独親権は、離婚の際に父母のどちらかに親権を与える制度(民法819条1項)です。
日本の民法は時代の波に対応できていない
すでに共同親権制度は先進国のほとんどで採用されていますが、日本では、今のところ、離婚すると単独親権の一択しかなく、熾烈な親権争いが繰り広げられる原因となっています。
現在の民法はそもそも1896年(明治29年)に制定されたものであり、何度か改正はされたものの、いまだ女性が家事や育児をやるのは当然だという旧態依然の男女の役割分担の意識が強く反映されたままです。
つまり、少子化や共働き世帯の増加、父親の育児参加などの子供を取り巻く状況の変化や時代の波に対応しきれていないのです。
いまや、時代の風潮にあった法律の改正が必要であることは明らかであり、その大きな議題として、共同親権制度への移行が議論されているのです。
世界で認められている「共同親権制度」とは
ここで、共同親権について世界の情勢を見てみましょう。
法務省の調査によると、日本以外ではインド及びトルコが単独親権制度を採用していますが、その他多くの先進国は離婚後の共同親権も認めています。つまり先進国では、単独親権制度を採用しているのは日本くらいなのです。
運用は国ごとに差異があるものの、裁判所の判断等がない限り、原則として共同親権とする国(ドイツ、オーストラリア等)、父母の協議により単独親権とすることもできる国(カナダのブリティッシュコロンビア州、スペイン等)、父母のいずれもがそれぞれの親権を単独で行使できる国(イギリスのイングランド及びウェールズ、南アフリカ等)があります。
日本で繰り広げられる離婚時の「親権」をめぐる大変さ
単独親権を採用する日本では、夫と妻がともに親権を希望した場合は容易ではない道のりが待っています。
まず、日本では離婚時には必ず子供の親権を父母のどちらかに決めないと離婚することができません。したがって、父と母がともに親権を希望すると、“親権争い”をしなければなりません。
父母間の協議で話がつかない場合、裁判所に調停を申し立てることになりますが、調停も所詮は話し合いの場です。決着がつかない場合には、最終的に離婚訴訟までもつれこむことになります。お互いに相手が「親権者にふさわしくない」と言った激しい攻撃や相手からの攻撃に対する防御を繰り返した挙句、裁判所の判決により親権者が指定されることになります。
家庭裁判所の調査官が子供の養育環境を調査するため家庭訪問をしたり、関係各所に話を聞いたり、子供の意向を確認したりすることも必要となってきます。本格的に争った場合、1年以上の時間がかかることも珍しいことではありません。もちろん、弁護士を依頼した場合は少なからず弁護士費用もかかることになります。
また、判決が出て親権者がどちらかに決まったとしても、すべてがうまくいくわけではありません。訴訟で攻撃や防御を繰り返したことで、父母間の感情的な対立は非常に悪化しています。
親権を取った側は、子供の親権を争った相手には子供と面会交流させたくないと思いがちですし、子供と面会交流をさせてもらえない相手は、養育費なんて支払いたくないと思うことが多いです。
つまり、どちらが勝っても負けても、面会交流を実施してもらえなかったり、養育費を支払ってもらえないなど、お互いに禍根を残すことになってしまうのです。加えて、板挟みになった子供にも大きな精神的な負担がかかることは言うまでもありません。
共同親権の課題
2011年(平成23年)に民法が改正された際に、「親権は子供の利益のためのもの」であることが確認されました。
日本の法律で共同親権が採用された場合は、非親権者が子供の個人情報すら教えてもらえないといった現在の状況は大幅に改善されるでしょうし、父母ともに子供に対する責任感が生じてきやすいと思われます。
ただ、共同親権にも課題がないわけではありません。
おおよそ次の問題があるとされています。
1つ目は子供の教育方針です。父母の対立は根本的に緩和されず残存しています。そもそも離婚するくらいですからお互い相入れない意見を持っている可能性が高いため、子供をめぐる意思決定に時間がかかると思われます。特に、子供の教育方針について意見が対立した場合など、意思決定が遅れることで子供への悪影響も懸念されます。
2つ目はDVや児童虐待です。DVや児童虐待等の問題があった配偶者の場合、共同親権では離婚しても縁が切れず、関係が継続することになります。DVや児童虐待の問題の解決は難しく、共同親権制度を採用することで被害の継続・拡大が危惧されます。
3つ目は負担が子供にもかかることです。父母の共同親権のもと、子供が頻繁に父母の家を行き来するようになると、子供の負担が大きくなります。子供が父母の家のどちらが自分の家かわからなくなり、精神的な安心感を得られなくなることもあるでしょう。また父母間の家の移動に時間がかかるなど、子供の時間を奪うことにもなり、体力的にも精神的にも疲弊することが懸念されます。
今後、こうした課題を解決するためには、「子供の利益」という観点から、個別具体的に対応策を議論すべきだと思われます。共同親権を導入するか否かという法改正の是非のみならず、共同親権を採用したとして、どのように運営していくのかを行政機関の対応も含めて慎重に議論する必要があるでしょう。
2021年(令和3年)2月には上川陽子法相(当時)が法制審議会に諮問をしており、「共同親権を含む家族法制の見直し」については法制審が議論を開始しています。
日本で共同親権制度を導入するのか、導入するとしてどのような形で施行するのかについては、日本の家族制度のあり方自体を大きく変えることになります。共同親権制度を採用するのであれば、子供とって最適な形で実施することが望まれます。
特に、離婚原因がDVや児童虐待などであった場合は、被害を受けていた側は二度と接点を持ちたくないと考えるのは当然のことです。離婚後も積極的に自分の子供に関わっていきたいと「共同親権」を望む声もありますが、今後日本において共同親権制度を導入する際には、共同親権者として明らかにふさわしくないと客観的に判断されるような親については例外規定を設けることも慎重に検討する必要があるものと考えます。
後藤千絵
京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。荒木法律事務所を経て、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所設立。離婚・DV・慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流・相続問題など、家族の事案をもっとも得意とする。なかでも、離婚は女性を中心に、年間300件、のべ3,000人の相談に乗っている。
フェリーチェ法律事務所:https://felice-houritsu.jp/
DV不認定、面会指示も息子に会えず 小牧の男性「元妻が制度悪用」
出典:令和3年11月4日 中日新聞
DV不認定、面会指示も息子に会えず 小牧の男性「元妻が制度悪用」
記事PDF
ドメスティックバイオレンス(DV)被害者からの申請に基づき、元配偶者らへの住民票の写し交付などを自治体が制限できる「支援措置」。加害者が被害者を捜すのを防ぐ目的だが、裁判でDVが否定されても措置は解除されない。愛知県小牧市の自営業の男性(53)は、実の息子と十五年以上も会えておらず「制度が悪用されたらどうすることもできないのはおかしい」と訴える。 (水谷元海)
男性は二〇〇五年、職場で知り合った元妻と結婚した。しかし元妻は翌年、一歳になったばかりの息子を連れて突然姿を消し、間もなく、弁護士を通じて調停を申し立てた。理由には身に覚えのない「暴力」とあった。
息子の居場所を探ろうと、半年ほどしてから市役所に住民票の写しの交付を求めたが拒否された。「支援措置」で、住民基本台帳の閲覧が制限されていた。元妻が転居先の自治体に申請し、小牧市も情報共有して対応したとみられる。
〇九年、元妻が離婚を求めて裁判を起こしたが、判決は「被告(男性)に身体的暴力などの有責行為は認められない」と訴えを棄却。さらに、元妻の側に不貞行為を認め、元妻が慰謝料を払う形で一九年に離婚が成立した。
続きは記事を参照ください。

離婚後の「単独親権」規定 2審も憲法違反認めず 東京高裁
出典:令和3年10月28日 NHK
裁判で離婚が成立する際に、裁判所が父親か母親の一方を子どもの親権者と決める民法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、東京高等裁判所は憲法違反にはあたらないと判断し、親権を持てなかった父親の訴えを退けました。
離婚後に2人の子どもの親権を失った都内の50代の男性は、裁判で離婚が成立した場合に裁判所が父親か母親のどちらか一方を親権者と決める民法の「単独親権」の規定は法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして国を訴えました。
28日の2審の判決で、東京高等裁判所の石井浩裁判長は、「規定は、子どもの世話や教育について適切に決められない事態を避けるために、裁判所がふさわしい方を親権者に指定するもので、子どもの利益を守るという立法目的から考えても合理的だ」と指摘しました。
そのうえで、「離婚後も両方の親が親権を持つ『共同親権』を認めるかどうかは国会の裁量に委ねる段階にとどまっていると言わざるを得ない」と述べ、いまの規定は憲法違反にはあたらないと判断し、1審に続いて男性の訴えを退けました。
親権のあり方など離婚後の子どもの養育をめぐっては法制審議会で法制度に関する議論が行われています。
米前駐日大使、日本の人質司法を批判 「ケリー被告を守る必要」
出典:令和3年10月21日 毎日新聞
米前駐日大使、日本の人質司法を批判 「ケリー被告を守る必要」
米国のハガティ上院議員(前駐日大使)が20日の上院外交委員会の公聴会で、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)に問われている日産自動車元代表取締役のグレッグ・ケリー被告について「弁護人は無罪を確信している。不当な扱いを受けるケリー氏を守る必要がある。懸念は日本の閣僚レベルにも伝えてきた」と訴える一幕があった。
ハガティ氏は、次期駐日大使に指名されたエマニュエル前シカゴ市長の公聴会で、刑事事件の容疑者や被告が長期間拘束されやすい日本の司法制度が「人質司法とも呼ばれ、時代遅れだ」と批判。日産前会長のカルロス・ゴーン被告が主導したとされる役員報酬の虚偽記載についても「仏ルノーとの統合への反対派によるクーデターだった」とのゴーン前会長側の主張を紹介し、「米国は日本への最大の投資国だ。米国の経営者たちが日本でのビジネスを再考し出すことを懸念している」と述べた。
ケリー元代表取締役の事件への対応を求められたエマニュエル氏は「既に調べ始めている。大使として承認されれば、最優先事項にする」と述べた。ハガティ氏は南部テネシー州選出で、ケリー元代表取締役もテネシーに居住していたという。
公聴会ではメネンデス外交委員長が、国境を越えた子の連れ去り防止を定めた「ハーグ条約」に関しても、日本の取り組みが不十分だと不満を表明した。エマニュエル氏は「条約は履行されるべきだ」と述べた。【ワシントン秋山信一】
更新 2024-03-31 (日) 12:20:27
a:422 t:2 y:2